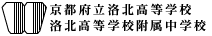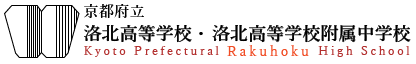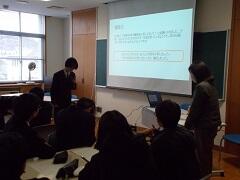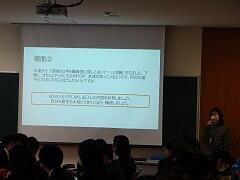- 学校紹介
- 学校生活
- 教育内容
- 洛北SSH
- 洛北SSH事業
- 年間活動一覧
- お知らせ
- 授業内の取組
- 課題探究Ⅰ
- 課題探究Ⅱ
- SHOOT Lab
- サイエンスチャレンジ
- サイエンス部
- コンテスト・学会発表
- 校外連携
- 洛北SSHだより
- 成果物(教材・資料等)
- 卒業生メッセージ
- 研究開発実施報告書
- 研究活動報告集(課題研究)
- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English
- 平成30年度以前の取り組み
- 在校生へ
- 中学生の方へ
- 卒業生の方へ
- 学校紹介
- 学校生活
- 教育内容
- 在校生へ
- 小学生の方へ
〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)
土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く
土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く
第19回 卒業証書授与式
2025年03月17日
3月17日(月)小雨の降る寒い日でしたが、第19回卒業証書授与式を行うことができました。4月からは高校生です。前を向いて、しっかり歩んでいってほしいです。中学3年生の表情は清々しく、素晴らしい式となりました。
中学3年生 家庭分野の取り組み
2025年03月13日
3年生B組 3月12日(水)
中学2年生時に「消費生活」の中で、契約と成年年齢について学習しており、今回は、その発展的な学習として、(公益財団法人)生命保険文化センターから斉藤数弘 氏を講師に迎え、「成年になるということ~契約の重さやリスクに備える方法について考える~」をテーマに、契約やリスクへの対処法、保険のしくみ等について、グループ討議や生活費の算出も交えながら学びました。特に、被害者だけでなく加害者になるリスクも考える必要があることや契約には責任が伴うこと等を再認識できたようです。
中学1年生 家庭分野の取り組み
2025年03月13日
1年生A組・B組 3月10日(月)
(一般社団法人)日本乳業協会関西相談室から中島律 氏らを講師を迎え、強い骨を作るために大切なことやカルシウムの必要性等についてお話を伺いました。家庭科の授業で学んだことを振り返ると共に、自身の食生活を見直すきっかけになりました。また、牛乳の摂取方法のひとつとして、イチゴジャムを混ぜて試飲しました。「牛乳が少し苦手だけれど、これだったら飲める。美味しい。」という感想や「別の方法も考えて試してみたい。」という声も多く聞かれました。是非、実践してカルシウム摂取を心がけて欲しいと思います。
中学3年生 家庭分野の取り組み
2025年02月26日
3年生B組 2月20日(木)
本校近隣に位置する相愛幼稚園の子どもたちと、生徒それぞれが製作したおもちゃや幼稚園にある玩具を使って一緒に遊びました。生徒たちは自分が作ったおもちゃを園児が色々工夫しながら遊んでくれることに驚いたり感激したりしていました。また、子ども達がとても可愛らしくて、「自分もこうだったのかなぁ・・」と幼い頃のことなどを思い出し、改めて親への感謝の気持ちをもったようです。感慨深い交流になりました。
心の健康学習を実施しました(中学第2学年)
2025年02月18日
2月7日に心の健康学習「自分も相手も大切にする伝え方をする」をスクールカウンセラーの残田満紀先生を講師に迎え、実施しました。ワークショップでは、あるシチュエーションを仮定し、自分の気持ちを押さえつけることなく、また相手も傷つけず、自分も相手も大切にするにはどのような声掛けができるだろうかについて、グループで話し合いをしました。質疑応答の場面でも、多くの質問があがり、コミュニケーションのあり方について考えるよい機会となりました。
百人一首大会を開催しました
2025年01月29日
1月29日(水)5・6限に、百人一首大会を開催しました。中学1年生から3年生までの学年を越えた、白熱した大会となりました。生徒たちが先生の声に耳を澄ませ、一生懸命に札を取る光景は素敵なものでした。
中学第1学年 家庭分野の取り組み
2024年12月24日
中学1年生A・B組 12月11日(水)
きょうと食いく先生の中西裕子氏(料理旅館「八千代」女将)を講師に迎え、「だしと日本の食文化」をテーマに、鰹、昆布と鰹のだしのとり方とそれぞれのだしを使った豆腐のあんかけ、味噌汁、ひじきの煮物の料理方法を。そして、和食文化等について学びました。だしの香りとともに、日本の伝統食について一層関心が高まりました。
12月12日(木)と18日(水)は、ひじきの煮物の調理実習を行いました。
中学第2学年 家庭分野の取り組み
2024年12月24日
12月19日(木)2年生A組・B組
日本損害保険協会近畿支部 大束健司氏を講師に迎え、「災害への備え」について学びました。自然災害の種類やその影響について考えるとともに、いつ起こるかわからない災害に対して、ハザードマップの活用方法や被害を最小限に食い止める準備等について学びました。
また、発展的な学習として、災害やボランティア活動、学校生活におけるリスクに対しての「保険」についても学び、自身の生活を見直すきっかけになりました。
中学第2学年 防災教育の取り組み
2024年12月16日
12月11日に、左京消防署消防課第二部の方に来ていただき、中学2年生に向けて防災教育を行ってもらいました。
講義では、火災時の動き方を実践を交えながら学びました。後半には、学校にある防災設備や避難設備の探索や、煙の疑似体験を行いました。
楽しみながらも、もしもに備える知識と意識を得られたと思います。
中学3年生 洛北サイエンスの取り組み
2024年12月10日
12月10日(火)、元種苗会社研究員(現本校教員)による特別講義「野菜の品種改良」を実施しました。私たちが普段何気なく食べている野菜、その野菜の品種開発には多くの技術と苦労があります。コンセプトを持ち品種をリリースしていく話を真剣に聞いている様子が特に印象的でした。野菜の品種改良を通して別の世界を見ることができ、貴重な経験になったのではないかと思っています。
学校生活
附属中学校
カテゴリ・リスト
 クリックで子カテゴリが表示されます。
クリックで子カテゴリが表示されます。
COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校