- 学校紹介
- 学校生活
- 教育内容
- 洛北SSH
- 洛北SSH事業
- 年間活動一覧
- お知らせ
- 授業内の取組
- 課題探究Ⅰ
- 課題探究Ⅱ
- SHOOT Lab
- サイエンスチャレンジ
- サイエンス部
- コンテスト・学会発表
- 校外連携
- 洛北SSHだより
- 成果物(教材・資料等)
- 卒業生メッセージ
- 研究開発実施報告書
- 研究活動報告集(課題研究)
- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English
- 平成30年度以前の取り組み
- 在校生へ
- 中学生の方へ
- 卒業生の方へ
- 学校紹介
- 学校生活
- 教育内容
- 在校生へ
- 小学生の方へ
〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)
土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く
土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く
- HOME
- >
- 教育内容
- >
- 特色ある取組
- >
- 令和6年度 サタデープロジェクト
- >
- 第4回 サタデープロジェクト
第4回 サタデープロジェクト
2024年12月19日
心臓のつくりを観察しよう
情熱はハートに宿っているそうですが、実際の心臓はどのような形をしていて、どのように血液を循環させているのでしょうか?この講座では、食用として入手できるブタの心臓(ハツ)を観察して、その謎に迫りました。ブタの心臓はヒトのそれとほぼ同じ大きさとされていますが、思ったよりも小さいと感じた生徒が多かったようです。ふつうはあまり触ったりすることのない実物に戸惑いながらも、心臓の動きを解説した動画などを参考に、どこから血液が入って、どのように送り出されているのかなどを、グループで話し合いながら観察しました。
草木染
ログウッドという染料を用いて草木染を行いました。ログウッドは、別名アカミノキとも呼ばれる染料で、媒染液に含まれる金属イオンにより発色が異なることが特徴です。今回は6班に分かれて、pHや金属イオンの種類による絹の染まり方の違いを確かめたあと、綿のハンカチやポーチを、媒染液の種類や濃度、手順を工夫して、好きな色に染める活動を行いました。絞り染めの方法を調べて実践した班もあり、その創造性には驚かされました。「思った色に染まらなかった」という班もありましたが、それも草木染の魅力の1つです。探究心がくすぐられた人もいたようで、「別の染料でもやってみたい」「2時間では物足りない内容だった」という感想が見られました。
Geogebra
関数のグラフや図形を自由に作って動かすことができるソフト『Geogebra』を使って、実際に出題されている数学の問題などを、グラフや図形を動かして考えました。『Geogebra』での関数の扱い方や図形の書き方を説明し、実際にある数学の問題を参考に、それぞれ工夫をして教材を作りました。数学の問題を「数式で解く」だけでなく、実際に図形などを動かして理解をすることで、数学に対する考え方が深まったように感じました。
東山でフィールドワーク
蹴上駅→ねじりまんぽ→南禅寺→哲学の道→銀閣という東山をメインとしたフィールドワークを行いました。
小雨の降る寒い一日でしたが、終わりかけの紅葉を楽しみつつ、地図を片手に1時間近く歩きました。ねじりまんぽや南禅寺では蹴上インクラインや琵琶湖疎水の役割を確認し、哲学の道では、右手の断層によってできた崖を感じながら歩きました。銀閣では、「庭に使われている石や砂が何でできているのか」ということについて地図を用いて考え、東山の微地形の成り立ちを理解し、足利義政がなぜこの地に銀閣を建てたのか仮説を立てました。
COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校
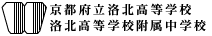
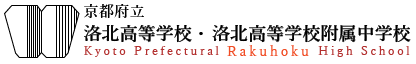






 クリックで子カテゴリが表示されます。
クリックで子カテゴリが表示されます。