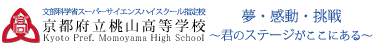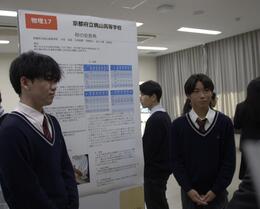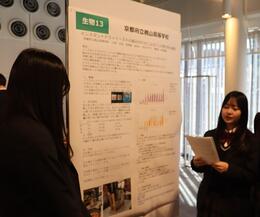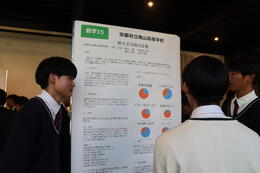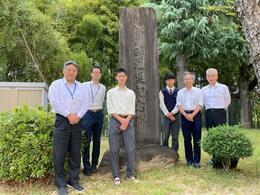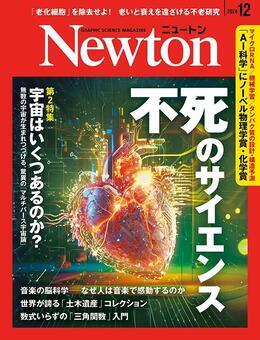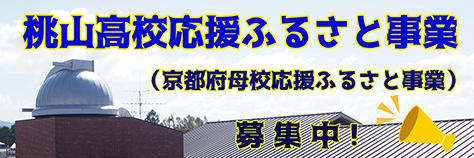自然科学科1年生は、12月12日13日に京都リサーチパークにて、サイエンスイングリッシュキャンプ(SEC)を行いました。SECは、2学期に取り組んだプレ課題研究の成果を英語で発表する取り組みです。プレ課題研究では、STEAM課題として、「粘土でできた船の浮力と形状」「氷に塩を入れて温度を測ろう」「熱による葉の変色を調べよう」「太陽光による温度上昇を測ろう」「フェルミ推定で考えてみよう」の5つからテーマを選び、自分たちで考えた実験・探究を行い、仮説・検証・考察の流れを体験しました。
SECでは、ベルリッツのネイティブスピーカーの講師の方に英語での発表方法の指導いただき、2日目の午後には発表コンテストを行いました。指導の中で、難しい内容をどうすれば聞き手に伝えることができるのかを考え抜き、英語表現や身振り手振り、目線の持っていき方など教わりました。発表コンテストでは、英語での発表だけでなく、講師の方からの質問にも英語で回答しました。
自然科学科では、3年生でも英語でのポスター発表を予定しています。今回のSECで身に着けたこと、課題に思ったことを、来年1年間大切にし、3年生でより良い発表を行えることを楽しみにしています。
コンテスト結果
First Prize Chemistry-2 Let's make sherbet easily
Second Prize Physics-3 THE STRANGEST BOAT
Third Prize Biology-1 Death rings and enzymes
Earth Science-2 LIGHT AND COLORED WATER
普通科1年生は12月9日10日に5~7組、12日13日に1~4組が京都テルサにて、サイエンスイングリッシュキャンプ(SEC)を実施しました。
SECは、2学期に取り組んできたプレ探究のまとめとして、探究内容を英語で発表する取り組みです。プレ探究では、探究の基礎として、自分たちで仮説を立て、作成したアンケート等でデータを取り、科学的に考察する手法を学びました。また、英語を用いた発表原稿・スライドを自分たちで作成しSECに臨みました。
SEC1日目の午前中は、本校ALTからConversation Skillsなどを学びました。午後からは日米英語学院のネイティブスピーカーの講師についていただき、プレゼン内容のブラッシュアップやプレゼンテーションの方法について指導していただきました。2日目の午前中は引き続き、指導していただき、2日目の午後は英語での発表コンテストを行い、講師の先生方からの質問にも英語で回答しました。また、講師の審査により表彰も行いました。
1日目は緊張していた生徒たちも、2日間英語漬けの研修・英語発表を経て、英語で話す楽しさや自信を得ることができました。来年度のGS探究Ⅱの課題研究では、今回見つけた課題を改善し、すばらしい探究にしていきましょう。
<コンテスト結果>
1~4組 会場①
First Prize 2組5班 Music and human sence
Second Prize 4組3班 About caffeine
Third Prize 4組5班 UTOPIA DREAM
1~4組 会場②
First Prize 1組7班 Sleep time
3組8班 Is my face beautiful?
Second Prize 3組4班 How to make a good impression in LINE?
5~7組 会場①
First Prize 5組3班 Do you believe in blood type?
Second Prize 6組5班 Gloomy days of the week
Third Prize 6組7班 Why we fall a sleep in class
5~7組 会場②
First Prize 7組8班 Carrying the Future !!
Second Prize 5組8班 The best memorization method
Third Prize 7組6班 The 30 degrees that guide us
GS部気象班では、外部の気象の専門家との交流を行っています。
10月11日には、京都地方気象台から2名の専門家に来校していただき、本校にある室戸台風に関する風災記念碑の話をしていただきました。室戸台風は各地に大きな被害をもたらし、本校においても校舎の倒壊など多くの被害が出ました。しかし、教員の指示に従い、生徒が的確に避難したことにより、本校の生徒教職員から1名の死者も出さずに済みました。気象台の方によると、各地に記念碑は多くあるものの、死傷者がいないことを伝える記念碑は全国的にも珍しいということでした。
10月19日には、神戸大学海洋気象研究室を訪問しました。当日は、大学生からの研究紹介や高校生からの研究発表を行いました。大澤教授や大学生から多くの助言をいただき、今後の研究が楽しみになりました。また、高校生と大学生の交流の時間もあり、進路選択や大学生活について知ることができました。