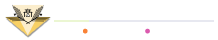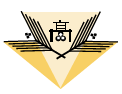11月2日(土)在校生保護者等対象授業公開を行いました。
保護者等様には、教室後方や廊下から温かい眼差しでお子様の様子を見守っていただき、生徒達は緊張しながらも安心して授業に取り組めました。
また、お子様の勉学に励んでいる様子や宮津学舎の授業を知っていただけたのではないでしょうか。家庭で、本日の出来事を話題にしていただき、さらに家族の仲を深める機会になってほしいと思います。
悪天候にも関わらず、多くの保護者等様に参観していただき感謝申し上げます。



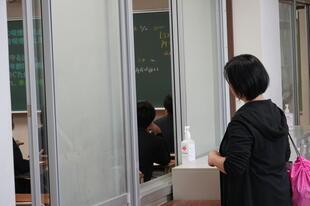
10月30日(水)放課後、ウェールズ・アベリスツイス町の高校生5名が本学舎を訪れ、書道部やICC(国際交流)部の生徒達と交流しました。与謝野町とウェールズ・アベリスツイス町は平成4年から高校生交流事業として交互に派遣を受け入れており、それがきっかけでこの取組が実現しました。
書道部との交流では、アベリスツイスの高校生に「桜」や「爽」の漢字を書く体験をしてもらいました。書道体験は初めてのようでしたが、手本を見ながら字を懸命に書いて、完成した字をお互いに見せ合い、笑顔が見られました。
ICC部との交流では、始めにグループに分かれ、好きなものを共有したりプライベートの写真を見せ合ったりして親睦を深めました。その後、ダルマ落としやけん玉、折り紙など日本の伝統的な遊びを体験してもらいました。ダルマ落としが成功したとき声に出して喜ぶなど日本文化を楽しんでもらえました。
異文化の高校生と交流することで、異文化だけでなく日本文化の素晴らしさを改めて実感する機会となりました。次回、英語でさらにコミュニケーションを取れるように英語の勉強を頑張ってください。
10月25日(金)6限目、生徒会長選挙を行いました。次期生徒会長として大江哲平さん(HR22)が立候補をしました。また、岩井那士暉さん(HR23)が応援演説者として大江さんのアピールポイントを熱く伝えました。演説後に行われた投票により、多くの信任があり、大江さんが新生徒会長として選出されました。
大江さんからのメッセージ
「私は今まで小中高で生徒会の役員になった経験がありませんでした。また、全校生徒の前で話すという経験もあまりなかったので、とても緊張しながら演説を行いました。緊張しながらも、みなさんに私がこれから会長としてしたいことを伝えることができて良かったと思っています。また、選挙を通して一つ成長できたように感じました。これから生徒会長としてさらに成長していきたいと思います。」
生徒会長がリーダーシップをとり、生徒会役員と力を合わせて、宮津学舎のさらなる発展を期待しています。

宮津学舎生徒会書記局です!
生徒会の活動を皆さんにもっと知ってもらうべく、生徒会執行部・局長にそれぞれインタビューを行いました!
色々な面から沢山の質問をしたので生徒会に興味を持ってくださると嬉しいです。
第二弾は生徒会の各局長(文化局長、体育局長、総務局長、書記局長)のインタビューを掲載します!
【文化局長】HR32 谷中星琉月さん
①文化局の紹介をお願いします
主に文化祭の企画、準備、運営を行っています。
②主な活動を教えてください
文化祭に向けて模擬店の準備や生徒会の取組など様々なことを行いました。
③文化局に入った理由はなんですか?
文化祭をより良いものにしたかったからです。
④文化局の魅力を教えてください
なんといっても人数の多さです。どの局よりも人数が多いので、様々な仕事を分担し、物事を円滑に進めることができました。
⑤一番大変だったことはなんですか?
やりたくてもたくさんの制限があり、私が実現させたかったことはほとんど叶いませんでした。そこが一番大変でした。
⑥生徒の皆さんに一言お願いします!
皆さんもご協力よろしくお願いします!
【体育局長】HR32 堀井涼雅くん

① 体育局の紹介をお願いします
体育祭を運営したり全校生徒が楽しく運動できる取組を考えています。
② 主な活動を教えてください
球技大会の企画・開催、体育祭の企画・運営
③ 体育局に入った理由はなんですか?
前年度の局長の意志を継ぎたかったのと、新たに球技大会を企画したかったから。
④体育局の魅力を教えてください
局員みんな明るく、気軽に話せる楽しい局です
⑤ 一番大変だった仕事はなんですか?
球技大会で新しい企画や種目を考える時、アイデアが出なかったり期限が短かったりしてなかなか上手くまとめられなかった
⑥ 生徒の皆さんに一言お願いします!
球技大会や体育祭、楽しんでもらえましたか?
皆さんがより楽しめる企画を考えていきたいので、どんどん意見をいただけたら嬉しいです!ご協力よろしくお願いします!
【総務局長】HR33 舘芭奈さん

① 総務局の紹介をお願いします
皆さんがより良い学校生活を送れるよう活動を行っています
② 主な活動を教えてください
靴袋渡し、挨拶運動、自転車の鍵チェック など
③総務局に入った理由はなんですか?
生徒会活動を通して学校のために何かしたいと思ったから
④総務局の魅力を教えてください
他の局とは異なり総務局は様々な分野の活動が行えること
⑤ 一番大変だった仕事はなんですか?
総務局として学校のために何ができるか考えること
⑥ 生徒の皆さんに一言お願いします!
生徒会活動へのご協力いつも有難うございます。
今後も挨拶運動や自転車点検をしようと思っています。これからもご協力よろしくお願いします!
【書記局長】HR32 谷口心彩さん

①書記局の紹介をお願いします
書記局では生徒の皆さんや外部の方々に学校の様子を生徒目線で伝える活動をしています。
様々な企画を行い、皆さんにワクワクを少しでも届けられるように頑張っています!
② 主な活動を教えてください
生徒会マスコットキャラの作成、生徒会新聞、学校HPの運用、宮通での記事掲載
③書記局に入った理由はなんですか?
元々広報活動に興味があり、新聞制作なども好きだったから。様々な企画をすることで、みんなを少しでも笑顔にしたかったから
④書記局の魅力を教えてください
インタビューなどを通して色んな人と繋がれる。楽しい企画をだいたいなんでも出来るところ!
⑤ 一番大変だった仕事はなんですか?
活動量が多く、常になにかしらの期限に追われていたり、少ない人数で分担するのが難しかったです。
でもその分みんなで協力して絆ができたと思います。
⑥ 生徒の皆さんに一言お願いします!
1年間ありがとうございました!少しでも楽しんでいただけていれば嬉しいです。これからも頑張るのでご協力お願いします。

1年間HPの生徒会記事を見ていただきありがとうございました!宮津学舎の魅力が伝わっていると嬉しいです!
次期生徒会も頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました!
10月21日(月)・22日(火)、図書委員会企画の図書館カフェを開催しました。普段図書館では飲食はできませんが、この2日間だけ特別に、ブックカフェのようにゆっくり飲み物を飲みながら、本を読んだり、語ったりできる交流の場として楽しんでもらうことを目的に企画したイベントです。図書委員がカフェのスタッフ役を務めました。昨年度好評だったため、今年度2回目の開催となりました。
イベントの出し物として、21日(月)は文科系部活動の発表がありました。写真部が9月に開催された学校祭を撮影した写真を使ったスライドショー、ICCがオリジナルの日本語訳を付けた英語絵本の読み聞かせを行いました。22日(火)は教職員による本の紹介「いいねブック選手権」を行い、3名の先生からお薦めの本を紹介していただきました。
1~3年生まで多くの生徒が来館し、大盛況となりました。いつもの図書館の雰囲気とはまた違った図書館を楽しんでもらえたようです。






10月18日(金)LHRに1年生は読書HRを行いました。好きな本や初めて読む本などを用意し、50分間集中して読書をしました。読書HRが始まる前の休み時間に、図書室に訪れて、先生オススメ本コーナーなどで面白そうな本を探している生徒もいました。「本は普段読まないのですが、久しぶりに本を読み、その良さに少し気付きました」などの感想があり、それぞれにとって有意義な時間になりました。
勉強や部活動などで忙しい日々を送っている中で、本とじっくり向き合う時間になったのではないでしょうか。これを機に、本の魅力を知り、読書習慣を身に付けてください。そして、多くの生徒に図書室に足を運んでもらいたいです。



10月17日(木)、2年生修学旅行保護者説明会及び進路講演会を行いました。
修学旅行説明会では、具体的な行程、保険の内容や料金、キャンセルについてなどの説明をしました。
進路講演会では、ファイナンシャルプランナーを講師としてお招きして、大学等で必要な経費や奨学金制度についての説明をしていただきました。将来の家計について具体的にイメージできる機会になったのではないでしょうか。
今年度の修学旅行の行き先は、昨年度に引き続き、浅草や東京ディズニーシー、横浜中華街など関東方面です。生徒にとって有意義な旅行となるように努めさせていだたきます。
本日は、夜分にも関わらず80名以上の方々に御出席していただきました。誠にありがとうございました。

10月4日(金)5、6時間目に1年生対象、学部・学科ガイダンスを行いました。大学・専門学校での学びや就職に関する知識を学び、生徒自身の進路意識を深める機会としています。大学や専門学校、企業から講師をお招きし、31種類の分野(文学部、教育学部、公務員、就職指導など)に分かれて、生徒はその中から興味・関心のある分野を3つ選び、時間帯に分けて3回ガイダンスを受けました。ガイダンスでは、大学、専門学校などでどのようなことを学ぶのか、卒業後の進路先など具体的にお話しいただきました。高校卒業後、どのような人生を歩んでいくのかさらに想像できる機会になったのではないでしょうか。
生徒の感想の中には、「自分がどんな仕事に就きたいかも大切だけど、自分が何歳になった時にどんな自分になっているか、なりたいかを想像することが大切だと学びました。想像できなかったら、興味のある仕事について調べることが大切だと知りました。」、「一年生のうちから、大学について考えておくことは大切だと分かりました。今日選択した以外の学部などについても、自分で調べたりしてみようと思いました。」などがあり自分自身の進路に向けて意欲を高めるきっかけとなりました。
講師の先生方、本日はありがとうございました。






10月4日(金)に宮津学舎説明会を行いました。丹後通学圏の全ての中学校及び舞鶴市立の中学校から多くの中学3年生及び保護者の皆様に御参加いただきました。夜分の開催にも関わらず御来校いただきありがとうございました。
説明会では校長の挨拶、教務部長から入学選抜及び進路指導部長から学校概要について説明しました。
本学舎には、次世代を担うリーダーを育成する使命があります。また、生徒、教職員ともに互いの頑張りを応援し合い、一生懸命になることの愉しさを実現できる魅力があります。そのこと等が実感していただけたのではないでしょうか。さらに本学舎の魅力を実感していただけるように11月2日(土)にオープンスクールを予定しています。宮津学舎の普段の授業や部活動の様子が見学できます。申し込みは本校ホームページ(こちらをクリック)からできます。なお、締め切りは10月18日(金)です。多くの御参加をお待ちしています。
10月10日(木)から2学期中間考査が始まります。
生徒達は、定期考査一週間前になるとアゴラ(開放型多目的教室)をはじめ教室、自習室など様々な場所で考査に向けて頑張っています。一人で集中して勉強している姿や友人同士で勉強し合う姿など一人ひとりが自分に適した勉強方法で取り組んでいます。2学期は学校祭から始まり、学校行事に専念し一生懸命取り組んできましたが、考査の日が近づくにつれ、気持ちを切り替えて学習に励んでいます。
1学期よりもさらに高みを目指して頑張ってください。