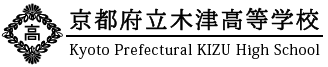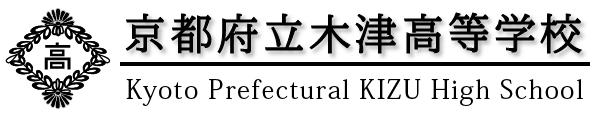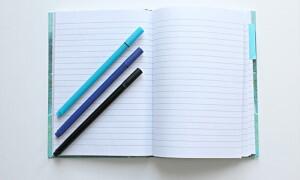教育内容
教育内容
2024年07月15日







7月13日から15日の連休中「園芸部茶業クラブ」が大活躍。
13日と14日は、宇治植物公園の「観蓮会」で早朝より「蓮葉茶」の呈茶を実施。
観蓮会に訪れた方に蓮茶をふるまいました。
15日は京都国際会議場で行われた「近畿地区高等学校PTA連合会大会」において、呈茶と販売会を行いました。
販売会は府内の農業高校・水産高校が参加。大会に華をそえました。
この他、木津川市の委託を受け、駅前花壇の整備などを行っています。
2024年07月09日
2024年06月22日











〇6月20日〔木) 木津保育園5歳児 の子供たちが「田植え体験」に訪れました。
2年生と3年生の5名が園児のサポートを行い「田植え」を行いました。
園児たちは泥んこになりながら稲を植え付けていました。
〇三者面談期間中販売実習をしました
三者面談期間中に2回 販売実習を行いました。本校の生産物はABCマーケットでもお求めになれます。
〇水田の除草作業はじまる
除草剤を使用せず稲を作っている私たちの水田稲作。7月末の中干しまで「除草作業」が続きます。
1年生も初参加し除草作業を行いました。
2024年06月19日





6月19日 システム園芸科の意見発表会を行いました。
システム園芸科では「農業クラブ」の行事としてクラス代表による「校内意見発表会」を行っています。
園芸科全員が意見発表の作文を書き全員が発表をします。今回は、学年で選ばれた3名がクラス代表として発表を行いました。クラス代表として選ばれた生徒は練習を重ねしっかりした発表を行いました。
校内発表会では3名の代表を選出します。3名は、7月に行われる「農業クラブ京都府連盟大会」に出場します。
2024年06月12日





〇6月11日 「田植え」作業が終わりました。
今年の品種は「恋の予感」という農研機構(国立研究開発法人:農業・食品産業技術研究機構)が育種した品種です。
連休明けに播種し、プール育苗にて苗を育ててきました。
本校の水田は、20年あまり「化学農薬や除草剤」を使用せず「化学肥料」も施肥せず無投入栽培を行っています。
最大の難問は、雑草の繁茂です。この対策に生徒たちによる手取り除草が稲が大きくなるまで続けられます。
〇一年生が栽培しているトウモロコシ。ぐんぐん成長しています。定期的に生育調査を実施。成長の経過を記録し見まもります。
2024年06月06日









5月末前後に設定されている「中間考査」。試験は生徒にとって一つの試練ですが、栽培管理も大きな試練となります。試験だからといって作物たちは成長を止めてくれません。1週間あまりで畑は草だらけとなります。テストが終わり、実習再開。管理作業の遅れを取り戻します。
〇販売実習スタート(ABCマーケット)
6月4日(火)より、毎週火曜日午後、近くのスーパーマーケット(PLANT木津店)で販売会を実施しました。(開催予定および時間は、本校HPで確認願います)
〇南山城支援学校生徒が野菜栽培現場で体験学習
6月5日(水)南山城支援学校高等部5組・6組の13名が来校し野菜栽培の学習と作業体験を行いました。3年野菜班がサポートを行いました。野菜栽培の学習は、南山城支援学校で販売会を実施。その担当をする生徒たちが現地を見て体験する目的で行われました。ジャガイモ収穫を体験しました。
〇管理作業大忙し
作業の遅れを取り戻すため大忙しの日々が続きます。
2024年05月19日






5月18日宇治市植物公園で開かれた「ハーブ&ローズ ファエスタ」に参加しました。
木津高校の茶葉を使った「オリジナルハーブティブレンド体験」や栽培をしている野菜・草花苗の販売を行いました。
農場では、一番茶実習も無事終了。現在「紅茶」に取りかかっています。また、各種野菜の植付けも完了しました。収穫まで栽培管理作業が目白押しです。
2024年05月19日




1年生が栽培管理をする「トウモロコシ」の植え付け(定植)を行いました。
クワで自分たちが管理する畑を耕し、整地をし苗を植え付けしました。
クワを使うことが初めての者も多く一苦労しながらの作業でした。
これから、草の管理、害虫対策、獣害対応と収穫まで管理作業が続きます。
収穫は7月中旬の予定です。
2024年05月09日



5月8日より一番茶のお茶摘み実習がはじまりました。
今回は1年生が「手摘み」により一番茶を収穫しました。一番茶実習は14日あたりまで続きます。
「荒茶生産」で「GLOBAL GAP」認証を受けている本校は、木津高が定めた「収穫規準」に則った作業衣・手順にもとづいて茶摘み作業は行っています。
収穫した茶葉はその日のうちに本校の茶工場で加工され「荒茶」となります。
荒茶に加工された茶葉は、調整加工を行いし袋詰めをして「新茶」として販売します。
販売は、6月始めを予定しています。
2024年05月05日



5月3日 京都府立山城郷土資料館主催「茶摘み体験・お茶のいれ方講座」を園芸部「茶業クラブ」がお手伝いをしました。
晴天の中、参加者全員での茶摘みをサポート。その後、採った茶葉を蒸しました。
その後、お茶の淹れ方講座を担当しました。新茶、かぶせ茶、和紅茶をそれぞれ担当したテーブルで行いました。
本校でも5月7日から新茶の収穫作業がはじまります。
2024年05月01日




1年生の基礎栽培実習え作付をするトウモロコシの種まきを行いました。
このトウモロコシを教材にし、栽培の基礎、管理の基礎を学んでいきます。
収穫は7月中旬を予定しています。
お茶摘みのシーズンに入りました。本校では来週からお茶摘みがはじまります。
2024年04月23日






〇今年も新茶のシーズンに入ります。新芽も順調に生育しています。
おいしいお茶をつくるため新芽を遮光資材で被覆しました。日光を制限することで茶葉の色合いとまろやかな味に仕上がります。
本校の一番茶摘みは5月連休明けを予定しています。今年の新茶もぜひお求め下さい。
〇木津駅西ロータリーの花壇を整備しました。
3年生草花専攻生が駅西円形花壇に花を植えました。
花を通して地域の方々に安らぎとホッとする空間をつくりたいと考えています。
2024年04月19日





「環境に負荷を与えない農業」を模索する木津高校システム園芸科では野菜温室内の害虫対策として天敵を導入してきました。
これから発生が予想される「コナジラミ類」の対策として「カスミカメムシ」を導入しました。
彼らが活躍できる環境を整えて害虫から作物を守って行きたいと思います。
2024年04月14日







木津高校の畑では今「アブラナ科」野菜の花が満開です。
一般的な畑は栽培が終わると直ぐに耕し露地状態にします。木津高校ではこの時期なるべく畑を露地状態にしないよう取り組んでいます。
それは、GLOBAL GAP の認定項目「生物多様性を保持する取組」「土壌の劣化をおさえる取組」を実現するためです。
キャベツ、ハクサイ、ダイコンの花は「ポリネーター(植物の花粉を運んで受粉(送粉)させる動物)」として活躍するミツバチやハナアブたちを守り育てることにつながります。
木津高校農場は、たくさんの生き物と共生した農業を模索して行きたいと考えています。
2024年04月07日






3月下旬から、春から夏にかけて栽培する作物の植え付け作業が大忙しとなってきました。
茶業では新茶に向けた準備で大忙し。草花は夏の花苗の移植作業がピークを迎えました。野菜は施設野菜のトマト、キュウリの植え付け。露地野菜の育苗が開始。夏作に向けて「給食堆肥」の施用など作業が盛りだくさんです。
桜の季節が終わると栽培作業はピークを迎えます。
2024年03月25日



3月25日 農林水産省近畿農政局より表記のコンクールにおいて「優良事例」として表彰を頂きました。
表彰の理由として、お茶の生産にかかわる「GAP」関連の認証への取組と生徒の取組について評価されたことです。
木津高校は、GLOBALGAP認証を京都府で初めて取得。現在まで認証の更新を続けてきました。環境に負荷を与えない持続可能な農業をめざし様々な工夫や改善を生徒たちと創ってきました。これからも、生徒たちが生き生きと活躍できる現場をつくりつづけて行きたいと考えています。
2024年03月19日







3月16日(土)、城山台防災フェスティバルに参加しました。
このイベントへの参加は昨年度に続いて二回目となります。
地元婦人会のブースでの防災クイズや避難体験、防災グッズの紹介などの手伝いや木津高産のお茶各種、パックごはんの販売も併せて行いました。
2024年03月13日


3月11日(月)、農林水産省が実施した「令和5年度近畿地域未来につながる持続可能な農業推進コンクール」において、木津高校がお茶の栽培で取り組んでいるGAP部門で近畿農政局長賞を受賞しました。表彰式は3月25日(月)に木津高校で行われます。
(以下近畿農政局ホームページの関連URL)https://www.maff.go.jp/kinki/press/kankyo/240311.html
また、令和6年度に全国的に実施される「みどり戦略学生チャレンジ」にも応募しました。木津高校が取り組んでいる「環境に配慮した農業」を伝えていきたいと考えています。
さまざまな取組を通じ、生徒達が活躍する場を広げていきたいと考えています。
2024年01月27日



1月24日(水)に3年生の「課題研究」発表会を開催しました。
2年生の後半から各専攻班に分かれ、それぞれが設定したテーマで学習活動を行いました。
今回はその結果をシステム園芸科全学年の前で発表しました。
今年の発表題目です。
1)野菜専攻班 野菜専攻栽培管理実習の作業内容分析と改善点
2)ABCマーケット担当班 本年度の成果と販売傾向分析
3)茶業専攻班A 米粉スイーツコンテストに関する報告
4)草花専攻班 木津高校農場における生き物図鑑の作成に関して
5)茶業専攻班B 日本茶アワードへの挑戦に関する報告
6)茶業専攻班C 新しいハーブーティの作成と課題
最後に 小野副校長より指導講評を頂き発表会を終了しました。
2024年01月20日




1月16日(火) 宇治茶会館(京都府宇治市宇治折居)で「南山城村手もみ技術保存会」の協力を得て「手もみ製茶」実習を行いました。
製茶は現在では機械製造が中心です。伝統的な「手揉み」によるものは、ごくわずかしかつくられていません。そのため、伝統技術の伝承はとても大切な課題となっています。
生徒達は説明を受けた後、実習を開始しました。指導を受けながら揉みを繰り返し茶葉の水分を取り除いていきます。最後は針のように細く長く形を整えます。全行程約5時間余りの作業となりました。
Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.