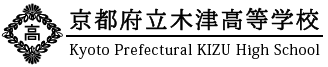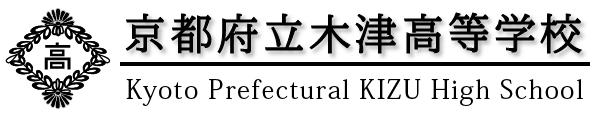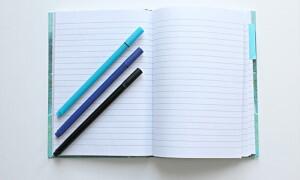教育内容
教育内容
2024年11月29日





11月28日(木) 農林水産省近畿農政局で開催された「みどり戦略学生チャレンジ近畿大会」で本校が取り組んできた「無農薬・む化学肥料で栽培を続けて24年間めの稲作」と「木津川市給食残渣利用の堆肥を活用した野菜作り」の2本を報告しました。
大会は、オンライン参加と対面参加の併用で行われ、近畿の高校から16チームが参加しました。
「みどりの食料システム戦略」は令和3年5月に策定されたこれからの農業政策方針で、「環境負荷を軽減させ持続可能な食料システムを構築する」ことを目標に定めています。
木津高校では、これに先立ち「生き物たちと共存する農業」を20年あまり前より実践し様々な取組を行ってきました。これからも未来を見すえた活動に取り組んで行きたいと考えています。
発表で紹介した「お米」は、本年度は「販売受付を終了」しています。
2024年11月25日









夏から栽培管理を行ってきた秋野菜の収穫がピークを迎えました。
11月はこれらの野菜を各地のイベントで販売する「販売実習」を行います。
これらの経験を通じよりよいものを作り販売する力を養います。
2024年11月03日










例年になく気温が高く、害虫等の発生も多く栽培管理に気を使う日々が続いています。
露地野菜収穫の第一弾として、1年生が栽培をしていた「ダイコン」の収穫を行いました。
品評会をした後、校内で販売会を実施しました。
また、各地でのイベントにも参加し販売実習を実施していきます。
本校で栽培した野菜などはABCマーケット(11月の火曜日14時過ぎからPLANTで実施)で販売実習を実施します。
2024年10月25日







10月22日から24日に岩手県で開催された「日本学校農業クラブ連盟全国大会」農業鑑定競技会に2名が出場しました。
2年生の生徒1名が成績優秀賞を獲得し表彰状を受け取りました。
会場は、花巻農業高校で、あの、宮沢賢治先生が教鞭を執っていたことで知られています。
校舎内は宮沢賢治先生が住んでいた住宅が移設展示されており公開されていました。
2024年10月20日



10月19日(土)木津川市・南丹市ホームタウンデーに参加しました。
京都サンガF.Cとサガン鳥栖戦 あいにくの雨でしたがたくさんの方が訪れて下さいました。
2024年10月20日







秋作野菜、ここ数年暑さの影響で今までの経験ではうまくいかないことが多くなってきましたが何とか順調に育っています。
○お米の収穫が始まりました。
品種が変わったためその特徴を活かしきれずうまく育てることができませんでした。例年並みとはいえませんが何とか収穫にこぎ着けることができました。今年もカヤネズミの営巣も確認できました。
○雑煮ダイコンの種まきを行いました。
お雑煮に使用するダイコンの播種を行いました。12月26日前後に収穫し新年を彩ります。
○秋野菜大きく育ってきました。害虫の動向に注意をしながら育てていきます。
2024年10月13日




10月12日(土)京都府立山城郷土資料館主催「山城生活文化セミナー」抹茶体験で講師を務めました。
第一部は裏千家同門会によるお点前披露がありました。
続く第二部で本校「園芸部茶業クラブ生徒」による「抹茶の点て方講習とてん茶試飲」を行いました。
各テーブルごとに生徒たちが講習を行い参加者めいめいお茶を楽しみました。
2024年10月09日



10月8日(火)「荒茶」で認証取得しているGLOBALGAPの更新審査が行われました。
審査当日、延期された「体育祭」と重なり更新審査を担当する生徒が更新審査に参加できない事態となりましたが、出場をやりくりしたメンバーで審査員の質問や説明を行いました。
GAPにとり組むことで、よりよい栽培現場にするためにどうするればよいのか「考えることができる」生徒に育てることにつなげたいと思います。
2024年10月01日





「京都の自然を話そう!京都の自然でつながろう!」をテーマに、9月28日・29日、京都府立植物園できょうと☆いきものフェス!2024」(きょうと生物多様性センター、自然環境保全京都府ネットワーク、京都府、京都市 主催)で本校の取組を報告しました。京都で活動をしている70あまりの団体が参加する一大イベントです。
本校が発表を行った内容は、木津川市鹿背山地区において10年来実施している「里山を取り戻す活動」です。
現在この取組は、3年生の選択科目「地域資源活用」で「かせやまの森創造社」の協力のもとで毎週月曜日午後に行っています。
このような取組を通じ、生徒たちが地域の環境を守り育てる役割を担う大切さを身につけてほしいと思っています。
2024年09月27日





〇畑の様子
10月末から1月にかけて収穫する野菜たちの作付が順調に進んでいます。
記録的猛暑の中、苗を育ててきましたが何とか無事に定植まで持ち込めました。キャベツをはじめとしたアブラナ科の野菜が栽培の中心となります。
温室では抑制トマトの栽培がはじまりました。
〇やまぶき支援学校の生徒が農業実習に来校
9月24日、やまぶき支援学校高等部2年生が農業実習に来られました。
システム園芸科3年植物バイオ選択生と共に「ハボタン」の定植作業を行いました。
2024年09月16日
Global.GAP認証審査(荒茶栽培工程)が10月8日に行われます。
審査時間:9時〜16時
場所:木津高校農場
GAP審査は「一般公開」を行いますので興味がある方は本校まで下記の内容でお知らせ下さい。
参加申込:FAX(0774-72-0032)
☆氏名
☆住所(会社等所属の場合はその名前)
☆電話番号(ご連絡先)
★中止以外の連絡は致しません。
G.A.P.(ギャップ) とは、GOOD(適正な)、AGRICULTURAL(農業の)、PRACTICES(実践)のことです。GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)認証とは、それを証明する国際基準の仕組みを言います。世界130か国以上に普及し、事実上の国際標準となっています。GLOBALG.A.P.認証は、食品安全、労働環境、環境保全に配慮した「持続的な生産活動」を実践する農場の証です(GAP普及推進機構HPより一部引用)。
2024年09月16日




9月中旬というのに30℃を超える暑さの中、1年生秋作課題の一つとなる「ブロッコリー」を定植しました。
ブロッコリーは近年需要が高まり主要野菜の一つに数えられるようになりました。
7月末に種をまき(播種)8月上旬に移植。暑い夏の期間大切に育ててきました。
収穫は10月末から12月にかけて行います。
2024年09月11日







秋作の栽培がはじまりました。
1年生はダイコンの種まきを行いました。
11月の収穫を目指し管理実習を行います。
1年生は、ダイコンの他、ブロッコリー、ハクサイの栽培も行います。
2024年08月25日


8月23日(金)、京都府学校農業クラブ連盟主催の「農業情報処理競技会」において、本校システム園芸科生徒2名がそろって「.優秀賞」を受賞しました。情報処理競技会は「文書作成」と「表計算ソフト」を駆使し出題された問題を仕上げていくもので、思考と応用力が試されます。
2024年08月09日



学校は夏休み期間中。休みといえど、作物たちはぐんぐん成長をします。
暑い時間帯、熱中症に警戒しながら管理実習を行っています。
まもなく、秋野菜の種まき・育苗の準備、花苗の移植など重要な作業がはじまります。
2024年07月31日





夏休み期間中を利用し、フォークリフト運転技能講習を行いました。
フォークリフトを操作・運転する場合、特別教育を受ける必要があります。
農業の現場でもフォークリフトが活躍する場面が多くなっています。
この講習会は、隔年で実施しています。2日間の講習に参加した生徒は、認定試験を受け合格者に講習修了書が発行されます。
2024年07月26日




夏季休業に入りました。農場では秋から冬にかけて栽培する作物の種まきや準備の時期です。
世間では、熱中症注意喚起が連日繰り返し呼びかけられていますが、作物は待ってくれません。
健康管理と休憩に留意しながら参加生徒たちは教員と作業に励んでいます。
本校は、コロナ禍以前より全員が担当してきた当番実習を改め、希望者が参加する時間外実習制度を変えています。
2024年07月26日




7月24日(水)亀岡市で開催された、京都府学校農業クラブ連盟大会 で、意見発表3部門、プロジェクト発表1部門の発表を行いました。農業クラブ連盟大会は毎年夏に開催されており、京都府内の農業関連高校より各校の代表者が発表を行います。この大会で選ばれた各部門の1名は、近畿連盟の大会へ京都府代表として参加。近畿連盟で選ばれた代表者は10月に開催される全校大会へ参加する資格を得ます。
残念ながら代表には選出されませんでしたが、とりわけ注目を浴びたのは、本校が発表したプロジェクト発表です。
カードゲーム形式で農業の魅力を伝えていくという今までにないユニークな取組。発表後展示した発表資料に多くの他校生とたちが集まり熱心に眺めていました。このゲームに関して、木津高校の「体験学習」や「学科紹介」で展示・紹介を行います。
2024年07月18日




7月17日 5月より栽培をしてきたトウモロコシの収穫を行いました。
背丈より高く育ったトウモロコシの畑に入り、自分たちが育ててきたトウモロコシを無事収穫。
ここ近年は野生動物(アライグマ、タヌキ、カラス)による被害が急増し、周囲を網などで囲っていますが、今年も100本近くが被害にあいました。
Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.