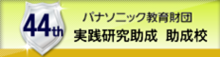平成27年12月19日(土)、けいはんなプラザにて
「Winter Collaboration 京大×南陽 ~まちづくりをあなたと~」と題して、まちづくりに関するフォーラムを行いました。
このイベントは南陽高校の生徒会と京都大学の学生が中心となって運営し、この日のために、skypeによるweb会議を通して様々な準備をしてきました。
プログラムは以下の通りでした。
プログラム:
13:30 開会
13:35 基調講演『地域力再生の今後』京都府副知事 山下晃正氏
14:15 実践発表『高校生によるまちづくり「Meet the World PROJECT」』
(南陽高等学校サイエンスリサーチ科 地域政策実習生)
14:45 ワールドカフェ テーマ:「私たちにできること~人とつながる地域づくり~」
16:50 閉会
司会は生徒会の1年生、三森君、村田さんが担当しました!
山下京都府副知事による講演では、『地域力再生の今後 ~けいはんな学研都市の将来構想と地域の活性化~」』と題して、貴重なお話を頂きました。「まちづくりは1年2年ではできない。長い時間をかけて作っていくべきなんだ」という言葉が印象に残るお話で、参加者からの質問にも丁寧に答えてくださり、とても勉強になる講演だったと思います。
南陽高校サイエンスリサーチ科1年生の実践発表では、『高校生によるまちづくり「Meet the World PROJECT」』と題して、木津川市の外国人向けハザードマップを作るにあたって、どのような取り組みをしてきたかが発表されました。地域政策実習生はこれまでに、木津川市役所を訪問して、ワークショップを実施したり、防災訓練へ参加したりしました。
ワールドカフェ(参加者が4~5人の少人数に分かれたテーブルで、カフェにいるようなリラックスした雰囲気の中、自由に対話を行い、ときどき他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら話し合いを発展させていくワークショップの1つ)では、自分が感じる地域の課題と、それに対する解決策としてどのような協働・コラボが可能かを、参加者全員でディスカッションしました。またこのワールドカフェでは、生徒会副会長、辻本さんが進行役を務めました!
最後に生徒会長、近本君のあいさつをもって閉会としました!
初の試みであった京大とのコラボレーションでしたが、たくさんの方々のご協力もあり無事に成功させることができました。
生徒会としても、今後も引き続き地域との連携に努め、学校行事にも反映させていきたいと思います。
1月5・6日につつじヶ丘テニスコート(和歌山)で行われた近畿公立高等学校テニス大会に出場してきました。南陽テニス部男子は2年連続の出場です。予選ブロック 桐蔭高校(和歌山)に2-3で負け、明石城西高校(兵庫)に0-5で負け、三国丘高校(大阪)に3-1で勝ち。ブロック3位で決勝トーナメント進出し、1回戦春日丘高校(大阪)に0-3で敗退。結果は近畿公立高校ベスト12でした。
優勝という目標には届きませんでしたが、ここまで来れたのはすごいことです。応援生徒は他校に負けない大きな応援で選手に力を与え、選手はコートの上でどの学校よりも楽しそうにテニスをしていました。選手、応援部員、マネージャー、監督の全員で一致団結し、この大会にのぞめたと思います。この経験を生かしこれからの目標達成目指して頑張りましょう!
12月22日(火)~25日(金)まで2年生は、本格的な受験勉強の基盤を構築するのを目的に、
大阪市住之江区南港にある大阪アカデミアで学習合宿を行っています。
【1日目】
開講式の後、ベネッセコーポレーションの森本典夫様に
「受験に向けての戦略、情報の大切さ、志望校の選び方、学習方法」などについてご講演頂きました。
その後、食事入浴の時間を挟みながら、22時15分まで講義や自学を行いました。
【2日目】
6時30分起床、8時30分から講義開始です。
午後学研の岡田眞奈美様に
「志望理由書・小論文の書き方」という演題でご講演いただきました。
その後、食事入浴の時間を挟みながら、22時15分まで講義や自学を行いました。
大きなトラブルや、体調不良による帰宅者等もなく3日目がスタートしています。
サイエンスリサーチ科1年生の「サイエンスⅠ」では,入学当初から科学的な探究活動を通じて「サイエンスリテラシー」を高められるような取り組みを行っています。
夏休み期間中に行われた夏季実習の一つ,「生命科学・遺伝子解析実習」(http://www.kyoto-be.ne.jp/nannyou-hs/mt/school_life/2015/08/271-2.html)のその後の活動を振り返りたいと思います。取り組んだテーマは「シロイヌナズナの花器官における表現型と遺伝子型の比較」です。
9月以降,生徒たちは実習で集めたデータの分析を十分に行い,ようやく自分たちの行った実験の目的や意味をしっかりと理解できるようになりました。高校1年生にとってはシロイヌナズナの花器官のABCモデルというテーマは難易度の高い内容でしたが,9月下旬に行われた校内発表会に向けてポスターの作成に熱心に取り組みました。
最初は手書きでポスターを作るところから始めました。「人前で発表するのはとても緊張する」,「顔が赤くなって恥ずかしい」とたどたどしく説明していた生徒たちも随分と流暢に話すことができるようになり,プレゼンテーション能力が飛躍的に向上しました。

さらに,10月下旬にはけいはんなプラザで行われた「まほろば・けいはんなSSH(スーパーサイエンスハイスクール)フェスティバル」に,11月中旬には京都工芸繊維大学で行われた「第2回京都サイエンスフェスタ」に参加しました。大学の先生に研究のアドバイスをもらったり,奈良県の高校のサイエンスの活動の様子を知ることができたりしました。
研究テーマの要約は以下の通りです。
シロイヌナズナの花器官の形成は生物の教科書に詳しく紹介されており,それはABCモデルと言われるA,B,Cの三つの遺伝子の組み合わせによってがく,花弁,雄しべ,雌しべが決定される。すなわち,シロイヌナズナの花器官は多様な突然変異体が観察されているにもかかわらず,ABCモデルを適用すればその表現型からA,B,Cのどの遺伝子が欠損しているかを判断することができるとされている。そこで,今回は無作為に抽出したシロイヌナズナ24株を対象に,実体顕微鏡で観察した花器官の表現型から遺伝子型を予想し,シロイヌナズナの花器官の形成がABCモデルで説明されうるかを検証した。まず葉の組織からDNAを抽出し,A,B,Cの三つの遺伝子の一部をそれぞれPCR法により増幅させた。次に,増幅部分を制限酵素により断片化し,アガロースゲルによる電気泳動を行い,そのバンドパターンを調べた。その結果,観察を行った24株において表現型から予想した遺伝子型は,遺伝子解析で得られた遺伝子型とすべて一致した。このことから,シロイヌナズナの花器官の形成にはABCモデルが適用されうることが判明し,さらにその変異体の出現はメンデル遺伝の法則におおよそ従うことが確認された。
また,12月上旬には学校説明会「南陽フォーラム」で中学生にも研究内容を理解してもらえるように,ポスター発表の説明の仕方を考え直しました。
授業で学ぶ座学の知識,進学に必要な受験テクニックを学ぶことも大切ですが,生徒たちは「サイエンスⅠ」の探究的な活動を通して,年齢・立場の異なる人たちに分かりやすく研究内容を説明するためのコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力,あるいはポスターを作成するための情報スキルの力が付いたことを実感できたようです。活動をサポートした教員からも生徒たちの頼もしい成長の姿が見られたという感想が聞かれました。
苦楽を共にした生命科学・遺伝子解析実習の6人のメンバーも,3学期以降はさらに自分たちの興味・関心に基づいた研究テーマをまたそれぞれ別々のグループで開始する予定です。
12月18日(金)、終業式を行いました。
校長先生から、2学期に行われた中国訪日団受入れ、体育祭、オープンキャンパスなどの行事を振り返ってのお話がありました。そうした行事を通しての仲間とのやり取りの中で相手を認めるということ、一期一会の気持ち、相手を敬うことの大切さについてお話がありました。
教務部の先生からは、2学期の評価を見て冬休みの計画を立て、年明けからの学習に挑んでほしいとのお話、また、先生が授業で50分間、生徒と集中して早く終わったと感じられる授業を一緒に作っていきたいとお話がありました。
生徒指導部の先生から、2学期の行事に対するお礼と、3学期に向けての文化祭、卒業式に向けてまた協力し合おうとの呼びかけがありました。また、貴重品の管理についての注意がありました。
進路指導部の先生からは、センター試験をあと29日に控え、点数1点の重みについての話があり、1,2年生においても今のうちに苦手を克服しておくことが大切とのお話がありました。
分掌の先生からの連絡のあと、伝達表彰式と上位の大会に出場するクラブの壮行会を行い、全校生徒で健闘を祈りました。
生徒会長も、行事についての説明を行いました。
生物の授業で人類学・骨学実習を企画・実施しました。生物実験室には人類の進化の過程が視覚的に分かりやすく理解できるように,大型類人猿(オランウータン・ゴリラ・チンパンジー)や化石人類の頭骨模型が並べられました。
地歴科の教科書には,いまだにヒトが猿人→原人→旧人→新人と直線的に進化したように記述されているものもありますが,実際にはヒトの進化の過程はもっと複雑だったことが最近の生物の教科書には記されています。
教育プログラムは,まずパワーポイントのスライドでヒトの700万年の進化史と霊長目の分類の説明がありました。環境を改変する動物としてのヒトも気温や紫外線などの影響を受け,生活環境にからだの構造や機能を適応させていることを実感できるような内容でした。さらに,遺跡から出土する縄文・弥生時代の古人骨の模型から性別や年齢,病歴,殺傷痕,生業形態などを推定する方法が説明され,断片的な骨から様々な情報を読み取ることができることを学習しました。
その後,それぞれの生徒たちは各自で化石人類の頭骨や現代人の全身骨格模型に直接触れて観察し,スケッチを描きました。
また,骨の関節面,筋肉の付着部,神経・血管の通る孔の様子を実際に確認しました。さらに,解剖学的構造(脳容積・眼窩上隆起・大後頭孔・矢上隆起・頬骨弓・オトガイ・歯列など)の違いに注目し,人類が進化の過程でどういう形質を変化させてきたのかを考察しました。
教材はすべて模型でしたが,進化の具体的な証拠となる標本の大切さを実感してもらえたようです。また,自分自身の頭の長さ・幅・高さを計測し,脳容積を推定する実習も行いました。
人類学を初等中等教育課程において学ぶことの意義は,科学的な人間観(例えば,ヒトという生き物を自然界の一員として,先入観や偏見にとらわれないで他の動物と比較しながら客観的に位置づけられるようになること)を養うことに留まらず,現代のグローバルな課題を解決するための基礎的素養を養ったり,非人道的差別や偏見を持たない国際感覚や人権意識を学ぶきっかけをつくったりすることができる点にあると言われています。
受講した生徒たちのレポートには様々なコメントが寄せられました。
「いろいろな骨を比較するのが楽しかった」
「人間の骨の仕組みは複雑で不思議だと思った」
「ヒトの頭蓋骨を見て自分のもあんなのかなあと思うと感慨深かった」
「生命の不思議さに感動した」
「貴重な体験となった」
「人類学の知識や発見はこれからの医療に役立つと思った」
「ルーツを知ることでこれからの私たちの生活に生かすことができる」
「日本史の授業で役立つ知識だった」
今回の教育プログラムは化石や骨の観察,脳容積推定などの実習を通した人類進化の学習でしたが,とても有意義な体験となったようでした。
世の中を見渡すと、学校で問題となるいじめの他に、パワハラやモラハラ、マタハラなどの職場でのいじめや嫌がらせが問題化しており、今では子どもだけに限らず大人たちも人権に関わる問題に悩んでいる様子が伺えます。
そこで今回、南陽高校では学校で起こるいじめ事象についてより理解を深めるために、10月21日に「PTA・教職員合同いじめ研修会」を企画・実施し、家庭や学校でできる取組などについて意見交流を通して探っていきました。
まずは生徒指導部長から近年のいじめの傾向と特徴を解説してもらいました。その話の中心はネット上での誹謗・中傷や仲間外しなどでした。
そこで次は副校長の司会進行で、①ネットトラブルの不安と課題、②学校・家庭としてできること、③学校・家庭の連携による三つのアイディア、の3点についてワールドカフェ形式による意見交換・ポスターセッションが行われました。保護者の方々と全教職員が一緒になって議論を交わす有意義な試みとなりました。
研修会を終えた保護者の方からは「子どもと時間をもっと有効に使い、コミュニケーションをとっていきたい」、「メール、Line、Facebookなどのネットの知識を増やそうと思う」、「先生方と直接話し合える機会が持ててよかった」という意見をいただきました。
一方、教職員からは「これからの学校の在り方とネットの繋がりについてたくさんの意見が聞けた」、「Face to faceによる対面のコミュニケーションをもっと大切にしたい」、「教育現場のガラパゴス化を改めて認識した」などの多岐にわたる意見が多数寄せられ、大人も子どもも一緒になって情報化社会のルールやマナーを学ぶ必要があることを感じる研修会となりました。
木津川市立相楽小学校の芸術鑑賞会に出演させていただきました!小学生だけでなく保護者の方々や地域住民の皆さんにも聴いていただける機会ということで幅広い年齢層に選曲しました。
また、吹奏楽と合唱のための「夜明け」も新チームになって初披露させていただきました。
演奏終了後に、「高校生になったら吹奏楽部に入りたい!」「すごくかっこよくて感動した!」といった5年生の感想をまとめた文集をいただき、音楽が持っている力を再確認すると同時に、多くの人に愛される音楽作り、チーム作りに全力で取り組みたいと思います!
追記:相楽小学校の5年生のみなさんから感想文集をいただきました!
心のこもった文集ありがとうございました!
9月18日(金)に体育祭が実施されました。この日は爽やかな秋晴れのお天気となりました。早朝から校舎内の安全確認、生徒たちの健康状態のチェック。各教室を回っていると、ふと窓の外に奈良の若草山の様子をきれいに見ることができました。教室からの眺望のよさに改めて驚くと同時に、この日も美しい緑色の山肌に心を奪われてしまいました。
さて、今年の体育祭は例年と異なり大きな変更点がありました。それは団体競技が増えたことです。一日の様子を振り返ってみたいと思います。
まずは南陽高校の伝統イベント「入場行進」で午前の部が始まりました。
こちらはパネルです。各ブロックごとに一つのテーマを表現しました。

次に「応援合戦(前半)」がありました。
「玉入れ」の様子です。
「LET'Sかけっこウォッチッチ」です。今年は精華町立いけたに保育所の園児のみなさんが参加しました。
こちらは「玉転がし」の様子です。
「兜台の合戦(タイヤ引き)」に続いて、「クラス対抗リレー(予選)」が実施されました。
そして「12人13脚」,「部局(クラブ)対抗リレー」がありました。
午後の部は「応援合戦(後半)」から開始です。
長い竹竿を使った「台風の目」に続き、「大縄跳び」、「クラス対抗リレー(決勝)」が実施されました。
「綱引き」の様子です。校長先生も参加しています。
そして最後は「ブロック対抗リレー」がありました。
こちらは最後の表彰式の様子です。
PTAの方々にもご協力をいただきました。
毎週金曜日、お昼休みにGlobal Citizen Seminarを開催しています。このセミナーの名前はALTのロリサンが考えてくれました。南陽生の皆さんに、もっと世界のことを知って欲しい、考えて欲しい、そしてその考えを発信して欲しいと願い、部活動や学科、クラスの枠を越えて企画しています。
ディスカッション、ディベート、スカイプを使ってのコミュニケーション等、様々なことをやっていこうと思っています。前回のディスカッションでは、Global Citizenとはどんな人?Global Citizenになるにはどうすればいい?などを話し合いました。
とにかく、英語で自分の考えを表現してみる。文法なんか間違ってたっていい。参加者は知っている単語を並べて自分の考えを一生懸命発表していました。
諸外国の人たちの考えを知る絶好のチャンスでもあります。是非、皆さん参加してください。
We hope more students will join us and express their ideas and opininons!