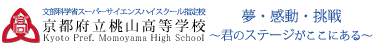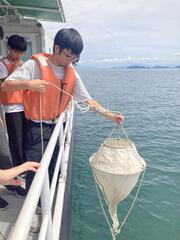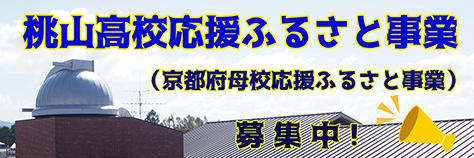2023/11/17
11月11日(土)に令和5年度みやびサイエンスガーデンが京都工芸繊維大学で開催されました。本取組はスーパーサイエンスネットワーク京都校に指定された京都府立高校の生徒が集まって行われる大規模な取組です。
桃山高校は自然科学科2年生の全生徒による合計17班のポスター発表を行いました。ポスターセッションは質疑応答が活発になり、大変盛り上がりました。課題研究を進める上で大いに参考になったと思います。
1月には桃山高校 自然科学科SSH課題研究発表会が開催されます。1年間の研究のまとめに向けて本番に向けてたくさんの知見を得ることができ、充実したイベントになりました。
2023/11/13
2023/11/09
2023/11/02
2023/10/27
10月23日(月)と24日(火)に、自然科学科2年生と対象に、東京理科大学教授・川村康文先生によるSSH講座「エネルギーと発電技術」が行われました。
この講座では、色素増感型太陽電池の作製とそれを搭載したソーラーカーの製作を通して、エネルギー変換の仕組みや効率について学びました。
作成した太陽電池が思ったほどの効率が出ずソーラーカーが動かない班がある一方で、ソーラーカーが想定以上の動きを見せる班もあり、エネルギー変換の効率化の難しさを経験的に学ぶことができました。
楽しみながら学ぶことで、物理学や工学に対する興味関心がより一層深まる取組となりました。
川村先生および学生の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
2023/09/28
2023/09/28
2023/09/25
2023/09/25
2023/09/25