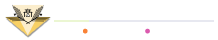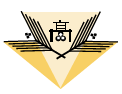体育祭では、3学年を縦割にして、赤・青・黄ブロックに分け、応援パフォーマンスやパネル、競技で競います。パネル制作は8月20日(月)から本格的に始まり、各ブロックのパネル長を中心にデザイン決め・下書き・色塗りなどの行程を進めていきます。集中力と根気が求められる作業ですが、担当生徒達は協力しながら、手分けして取り組んでいます。
当日、どのようなパネルが完成しているのか、とても楽しみです。
以下は、昨年度のパネルです。
8月27日(水)、劇団「人間座」の皆様を講師としてお招きし、演劇指導をしていただきました。「人間座」の皆様には、旧宮津高校時代から長年にわたり御指導いただいております。
演劇指導では、立ち位置の工夫や観客の視点を意識したセリフの表現、場面設定の方法など、プロならではの視点から多くの秘訣を教えていただきました。生徒たちは、講師の方々のアドバイスに真剣に耳を傾け、メモを取りながら、劇の完成度を高めようと意欲的に取り組んでいました。
一週間後に控えた学校祭に向けて、今回の御指導を活かし、各クラスが満足のいく劇を仕上げてくれることを期待しています。 また、劇団「人間座」の皆様には、貴重な御指導と御協力を賜りましたことに感謝申し上げます。






8月1日(金)中学3年生対象体験セミナーを実施しました。
授業体験をはじめ生徒や教員による学校紹介、建築科体験、部活動体験、部活動見学ツアーなどたくさんのプログラムがあり、宮津学舎の魅力を様々なかたちで中学生に実感していただきました。また、本学舎の生徒や教員と交流することで、宮津学舎の魅力である「一生懸命を応援し合える雰囲気」、「学ぶことの愉しさ」を肌で感じていただけたのではないでしょうか。
夏休み期間ではありますが、丹後通学圏すべての中学校及び舞鶴市から多くの中学生の参加がありました。また、多くの保護者の方々にも本学舎の教育活動に興味をもっていただき感謝申し上げます。この体験セミナーを機に高校3年間を宮津学舎で学びたいと思っていただけたら大変嬉しく思います。来年、皆さんと一緒に宮津学舎で青春を送れることを楽しみにしています。
全体会


体験授業



部活動体験



また、体験セミナーの他にも宮津学舎の魅力を知ることができる機会をご用意しています。申込案内は2学期以降、中学校を通じてお知らせします。宮津学舎一同、心よりお待ちしています。
宮津学舎 今後の予定
10月3日(金) 宮津学舎説明会
(宮津学舎の特色ある取組や入学者選抜について紹介します。)
11月1日(土) オープンスクール
(宮津学舎で行われている授業や部活動を見学できます。)
11月~12月予定 個別相談会
(入学者選抜や本校の教育活動の疑問についてお答えします。)
7月24日(木)、25日(金)、28日(月)の三日間、普通科1年生を対象に集中学習会を行いました。集中学習会では、講習に加えて、卒業生による講話や座談会、講演会なども実施しており、主体的に学習に取り組む姿勢や態度も養う貴重な機会となっています。
卒業生による講話では、勉強方法やモチベーションの高め方、高校生活を送る上で大切な心構えなどの話があり、充実した学校生活を送る上でのヒントを学ぶことができました。
座談会では、講話の内容をさらに深掘りしたり勉強での悩みを打ち明けたりなど、様々な話題で盛り上がっていました。
3日間の集中学習会を終え、生徒の感想の中には「自分に合った勉強方法を見つけたいと思いました」、「この学習会を機に、習慣を変えていこうと思いました」、「勉強は得意ではないけど、コツコツ頑張りたいです」などがあり、それぞれが充実した3日間を送ることができたように感じました。今回得られた達成感や学びをこれからの学習意欲につなげてください。
京都府丹後地域では、高校生が小中学生の学習を支援するプラスワンスタディという取組があります。本学舎では、その取組が7月22日(火)から始まり、参加を希望した生徒達が地域の小学校や中学校を訪れ、児童生徒の学習支援を行いました。
生徒達は、児童生徒の一生懸命に学習に打ち込む姿に応えようと熱心に勉強を教えていました。
これを機に児童生徒が学ぶことの楽しさに気付き、勉強を好きになってくれたら嬉しく思います。


7月18日(金)、一学期終業式を行いました。
校長から「高校でしかできないことがあるはずです。それをできる限り愉しむ。苦しい状況になっても一生懸命に愉しむ。駆け引きを愉しむ。これらの経験を今後に活かしてください」など生徒達へ期待を込めたメッセージがありました。
また、一学期に活躍した部活動の伝達表彰を行いました。
以下、詳細です。
【両丹高等学校総合体育大会】
○令和7年度第77回両丹高等学校総合体育大会
男子 総合3位 女子 総合2位
【陸上競技部】
○第60回京都府高等学校春季陸上競技大会
男子三段跳 第4位
男子砲丸投 第8位
女子棒高跳 第3位
女子やり投 第3位
女子やり投 第5位
○第78回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会
男子走幅跳 第4位
男子三段跳 第6位
女子やり投 第5位
○令和7年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会
男子三段跳 第8位
女子やり投 第8位
〇第80回京都陸上競技選手権大会
男子走幅跳 3位
女子棒高跳 3位
【ヨット部】
○令和7年度京都府高等学校ヨット選手権大会
兼 第79回国民スポーツ大会セーリング競技京都府選手選考会
女子420 優勝 → 第78回国民スポーツ大会 出場権獲得
男子420 3位
男子ILCA6 3位
【ボート部】
○第78回京都府高等学校総合体育大会
兼 第73回全日本高等学校選手権ローイング大会京都府予選
女子ダブルスカル 優勝
女子舵手つきクォドルプル 優勝
男子ダブルスカル 2位
○令和7年度近畿高等学校総合体育大会
兼 第75回近畿高等学校ローイング選手権大会
男子ダブルスカル 2位
女子舵手つきクォドルプル 3位
【フィールド探究部】
〇第27回日本水大賞
文部科学大臣賞
【美術部】
〇第16回京都府デッサンコンクール
協力大学賞
続いて、全国大会出場向けての壮行会がありました。
以下、詳細です。
○令和7年度全国高等学校総合体育大会
【ボート部】
女子ダブルスカル 2名
女子舵手つきクォドルプル 5名
○第 49回全国高校総合文化祭香川大会
【書道部】書道部門 1名
【写真部】写真部門 1名
代表生徒から「京都府代表として、これまでの努力の成果を発揮できるように頑張ってきます」、「全国大会で様々なことを学んで、今後に活かせられように頑張ってきます」と力強い挨拶がありました。
宮津天橋高校生徒・教職員一同、練習の成果を発揮できることを願っています。応援しているので全力を尽くしてきてください。
また、明日から、夏休みが始まります。集中学習会や講習、部活動、学校祭準備など多くの活動があります。それぞれの来たるべきときのために夏休み期間を愉しんでください。




地域高校連携事業の一環として、宮津市立図書館から「出会いのある図書館」を作ってほしいという依頼を受け、本学舎の図書委員会が5月頃からコツコツと準備を進めてきました。7月17日(木)放課後、宮津市立図書館で展示の準備をし、無事に完成することができました。
以下、詳細です。
展示期間:7月 18 日(金)~9月 24 日(水)
場所:宮津市立図書館 ※受付の右側にあります。
展示内容:『アドベンチャー』
図書委員が今までに読んだ本の中で特にこれはお薦めしたいという本を紹介するコーナーです。「アドベンチャー」に合った本を選んでいます。これを機に本に親しんでほしいという思いを込めています。
ぜひ、宮津市立宮津図書館に訪れた際は立ち寄って見てください。



7月16日(水)、PTA集会を行いました。今回は、宮津市与謝消防署救急救命士 糸井康隆様を講師としてお招きし、「あなたにしか救えない大切な命~あなたの知っている方法、間違っていませんか?~」という題目で講演していただきました。
講演では、救急救命の現状や、胸骨圧迫やAEDの使い方を学びました。実際に、マネキンで胸骨圧迫を実践してみたり、倒れた人を発見したときを想定してグループで救助の練習をしたりしました。救急救命士が到着する間、周りの人と協力しながら胸骨圧迫などの救命措置をし続けることの大切さを学びました。また、自分の知識が間違っていたことにも気付くことができ、有意義な機会となりました。
糸井様にはこのような機会を作っていただき感謝申し上げます。


7月14日(月)6限目、1年生は各HR教室で人権学習を行いました。今回は、個性と共生の時代を生きるために「差別の構造」について学びました。思い込みや決めつけがきっかけで差別が生じる可能性があることを知り、差別に発展しないような態度や行動について考える機会になりました。
生徒の感想の中には、「ネットだから、匿名だからと言って好き勝手に行動せず、ネットの向こう側にも人がいることを認識して行動するべきだと思いました。」、「見ようとしていないものは見えないということは、様々な考え、生活、個性を持つ人がいることにも気付けない、ということを学びました。」などがあり、人権感覚をさらに高めることができました。
7月14日(月)、1年生は保健の授業で心肺蘇生法を学習しました。マネキンや練習用AEDを用いながら心肺蘇生法の手順を確認しました。119番通報をする人、AEDの手配をする人、胸骨圧迫をする人など役割分担をして、実際に倒れた人を発見した時を想定しながら実践しました。
救命処置が必要な場面に遭遇した際に、適切な行動ができるように今回学んだことを活かしてください。