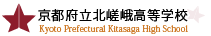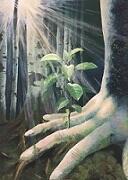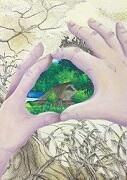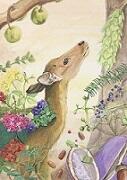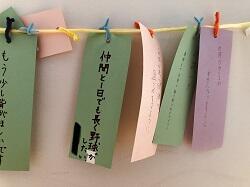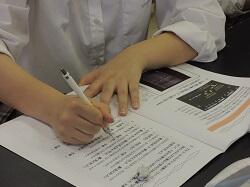創立50周年関連
- >
- 創立50周年関連
本日、3年生「生物」の授業で蚕の繭を使い、「蚕の繭から生糸を繰る」という実験が行われ、チーム対抗でその長さを競いました。
40分煮て柔らかくした1つの繭を、「さらに水につけるとふやけて伸びやすい」
という教員からのアドバイスを受け、生徒たちは黙々と繭から糸を紡いでいました。
格闘すること15分、勝利チームは「のばしたったぜチーム」(記録約9.5m)でした!
(1つの繭から上手に繰れば、約1km程度の糸をとることができるそうです。)
同じ太さで撚り続けることができたチームは、途中で切れることなく伸ばしていくことができたようです。
本校では、京都工業繊維大学から蚕の幼虫を譲り受け、幼虫からさなぎ、
成虫の産卵まで、蚕の短い一生を観察します。
無事カイコガになれる蚕がいる一方、繭を作ることはできても、
繭から出る段階で命を落とす蚕がいるなど、
命の不思議さ、力強さを生徒に教えてくれる大切な存在です。
そして人の暮らしに長く寄り添ってきたことから、
我々の生活の営みにも思いを馳せることができる存在でもあります。
ちいさな蚕を通じて、たくさんのことを感じてほしいと思います。
令和5年7月8日(土)に、長浜バイオ大学京都キャンパスにおいて、高大連携講座『自分の設計図を調べてみよう~お酒に強い?弱い?~』を実施しました。本校2年生の理系進学希望者20名が大学の設備を利用して、黒田先生のご指導の下、自分の遺伝子を扱うというDNA鑑定の実習を行いました。
生徒たちは、初めて使用するマイクロピペットの取り扱いに苦戦しながら、各自の口腔細胞を採取し、いくつもの操作を経てようやくDNAを取り出した後、PCR法で特定の遺伝子を増やし、アガロースゲル電気泳動法で各自の遺伝子型を判定しました。また、アルコールパッチテストでも遺伝子型を検証しました。
DNAを実際に大学の研究の場で操作するだけでなく、遺伝子操作の功罪について学習を深めるという社会科学的アプローチも体験でき、全員が修了証書をもらうことができました。大変有意義な1日となりました。