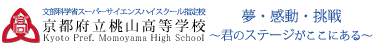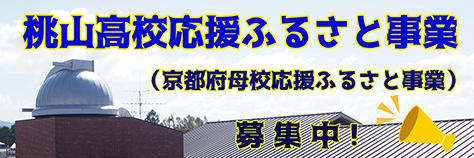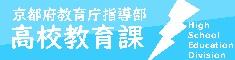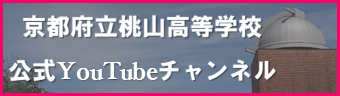スーパーサイエンスハイスクールでは、指定から3年目に、その時点における研究開発等の内容を見直し、事業の効果的な実施を図ることを目的として、外部の有識者による研究開発の進捗状況等の評価が行われます。
令和4年度に実施された中間評価の結果、本校は全6段階中上から2番目という高い評価を頂きました。
中間評価講評(抜粋)
① 研究開発計画の進捗と管理体制、成果の分析に関する評価
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されている】
〇生徒の変容について、アンケートの結果のみならず厳密な方法で評価が行われることが、今後求められる。
〇コロナ禍であっても、プログラムを工夫することで、ほぼすべての行事を計画通り実施していることは評価できる。
〇在校生や教師のみならず卒業生へのアンケートも実施しており、大学院進学や研究者・技術者への就職率が高い等を把握することで、科学技術人材育成に大きな貢献をしていることは評価できる。今後も、卒業生への追跡調査の結果を検証することが期待される。
〇ルーブリックを利用したパフォーマンス評価は評価できる。
〇会議内容は連絡や協議だけでなく、教師同士の交流や研修を重視する等、全校で取り組む体制になっていることは評価できる。
〇授業、行事、部活動を有機的に連動させて人材育成を図っていることは評価できる。
② 教育内容等に関する評価
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されている】
〇能力目標として5Cを定め、またそれを授業・行事・部活動で獲得するという戦略を明確にしている。パフォーマンス課題の成果と評価を行い、更にそれを題材に教師研修を行う等、高校全体の教育改善につなげていることは評価できる。
〇「GS科目」における探究学習のテーマを「GS探究」と連動させて5Cを3年間をかけて体系的に育成するカリキュラムを実施している。
〇「GS探究」に代表される探究型授業について、一般教科のように型にはまったものになっていないか、生徒の主体的な取組になっているのかどうか、検討することが必要である。
③ 指導体制等に関する評価
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されている】
〇「GS探究」は全教科の教師が指導を担当しており、教科間で連携することで3年間の体系的な探究型学習が実現している。また、SSH推進担当主導で担当者会議を運営することで、教師が一丸となって課題研究を推進する指導体制を構築している。
〇普通科の生徒が課題設定をする際、生徒が主体的に取り組むことができるようにするために、どう指導するかの検討が必要である。
④ 外部連携・国際性・部活動等の取組に関する評価
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されている】
〇大学等との外部連携は順調に実施している。
〇生徒のキャリア形成を意識した取組により、具体的なキャリアイメージを生徒自身が持つことに成功していることは評価できる。
〇今後、グローバルな視点を取り入れることが望まれる。
〇大学や研究機関、企業等との連携はコロナ禍でも各学年で工夫して実施している。
〇「グローバルサイエンス部」は、毎年複数の研究が外部コンテストで受賞する等、活発な活動が行われており評価できる。今後は、学校の課題研究を引っ張るリーダーとして活躍することができるよう育成を図っていく等、学校側としての支援が期待される。
⑤ 成果の普及等に関する評価
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容がおおむね達成されている】
〇研究成果の普及・発信はしっかりと行っているが、他校が自校のどのような点を評価しているのか交流を通じて確認することが望まれる。また、そのためにはこれまでの取組をより客観的に評価し、整理していくことが強く求められる。
〇他校からの多くの訪問を受けていることからも高く評価されていることがわかるが、今後は、市内からの受け入れのみならず、他校の理数探究基礎を開設するための支援をする等、研究成果を全国的に発信することが望まれる。