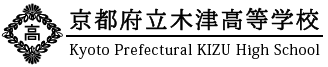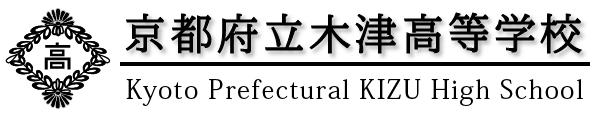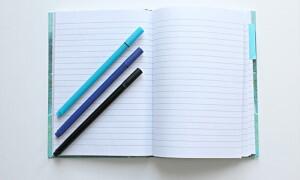学校生活
2017年12月21日


12月21日(木)午前、第2学期の終業式を実施しました。
台風21号による休校があったため1日遅れの終業式となりました。
学校長より「満年齢と数え年」についてのお話がありました。
式後、第3学年部長、教務部長、生徒指導部長からそれぞれ話や連絡と
書道部・写真部・合唱部・園芸部や税の作文・PTAの交通安全標語など今学期部活動やその他の活動で活躍した生徒に対する伝達表彰がありました。
2017年09月23日



9月15日(金)木津駅周辺の清掃活動を行いました。
早朝からたくさんの生徒が参加し、広範囲にわたってたくさんのゴミを拾ってくれました。 また、生徒会は駐輪場を利用する方々に自転車盗の危険性を知らせるとともに、ツーロックを呼びかけてくれました。今後とも、この活動に人を募って参加し、より多くの生徒に「街を綺麗にする」精神を浸透させていきたいと思います。
2017年09月23日



本校では、毎月開催されている木津駅周辺のクリーン活動に約200名の生徒が参加し、その他にも木津警察署と協同して落書き消し運動やツーロック運動、痴漢撲滅運動などに参加しています。その結果。犯罪のない安心・安全なまちづくりに顕著な功績のあった団体として「平成29年度 京都府防犯まちづくり賞」に選ばれました。多くの生徒たちの心の中に、「自分たちの街は自分たちで守る、きれいにする」という気持ちが芽生えていることを、大変うれしく思います。
また、この受賞を記念して、木津防犯推進委員協議会 木津支部・相楽支部様より、横断幕を作っていただきました。これを励みに、より一層安心・安全な街づくりに貢献していきたいと思います。
2017年08月28日





8月28日(月)2学期の始業式を行いました。
校長より「夏休み中科学部・合唱部・吹奏楽部やその他の多くの部活動が各種大会などで、3年生はそれぞれの進路に向けてよく頑張った」ということと、「今年の文化祭は『smile 笑う木津には福来たる』というスローガンで行われることを紹介し、チャップリンのモダンタイムズ使用されたsmileという曲の歌詞のように、文化祭・体育祭などの取り組みで思い通りにいかないことがあっても、他者を思いやる心を大切にして笑顔で乗り切ってほしい」という話がありました。
始業式後、の全校集会で
教務部より「今日から2学期。2学期は大切な時期なのでけじめをつけて頑張ってほしい」という話と、
生徒指導部より「困ったことやトラブルは早めに担任の先生に相談してほしい」「正門横の通路において9月1日より歩行者と自転車の通行が可能になる件」「文化祭期間中も身だしなみに気をつけて行動してほしい」という話があり、
進路指導部長より「3年生に向けて指定校推薦や出願について」「1・2年生に向けて進路希望調査の件について」連絡がありました。
その後、夏休み優秀な成績を修めた吹奏楽部と合唱部の表彰がありました。
2017年07月21日




平成29年7月18日(火)木津駅周辺の清掃活動に参加しました。
朝であるにも関わらず大変暑い中での活動になりましたが、生徒達は木津駅周辺をぐるぐる周り、多くのゴミを拾ってくれました。また、生徒会も警察の指導の下、木津駅の駐輪場でツーロックを呼びかける運動を行ってくれました。
生徒達のこのような姿を見ていると私たち教員も暑いなんて言ってられないなと感じます。生徒達に負けないように、暑さに負けないように、パワフルに仕事をしていきます。
2017年07月20日





平成29年7月12日(水)相楽会館にて非行防止教室を行いました。
講師として木津警察署のお二人をお招きし、「ネットトラブルからみんなを守るために」、「薬物乱用根絶に向けて」という演題で御講演いただきました。また、生徒会も薬物の危険性とその対策についての寸劇などを行いました。
生徒諸君からすれば、自分とは関係のない話だと思うかも知れませんが、トラブルに巻き込まれてからでは手遅れです。今回の講演で学んだことを活かし、トラブルに巻き込まれないよう十分に注意し、有意義な夏休みにしてほしいと思います。
2017年07月20日





7月20(木)1学期の終業式を行いました。
学校長より、木津高校生として、この夏休みに努力を惜しまず取り組んで欲しいことなどについて話がありました。
また、木津高校が平成21年度から毎月継続して行われているクリーン活動で「平成29年度京都府防犯街づくり賞」を受賞し、継続することの大切さについて話がありました。
式後、
1年学年部長より「ともに夢を追い目標に向かって頑張ろう」という内容で講話があり、教務部長・生徒指導部長・進路指導部長より夏休みにむけての諸注意がありました。
その後の表彰式・全国大会に向けての壮行会を行い、合唱部が美しい合唱を披露しました。
2017年06月15日
気持ちのよい天気が続いていますね!
今年は梅雨の時期にも関わらず、あまり雨が降りません・・・
そんなカラッとした気候のなか
平成29年6月15日(木)、木津駅周辺の清掃活動に参加してきました。
本日も沢山の方々が参加されて、ゴミ拾いをすることができました!
また
部活動を引退した3年生の姿をよく見かけました
自主的に清掃活動に参加している姿は、「さすが、3年生!!」と感じる瞬間でしたね!
2017年05月22日
平成29年5月15日(月)、木津駅周辺の清掃活動に参加しました。
今回の活動も前回の活動に引き続きたくさんの方が参加され、多くのゴミを拾うことができました。
前回と同様、施錠していない自転車に盗難の危険性を呼びかける活動も行っていましたが、それらと並行して痴漢禁止を呼びかける活動も行っていました。
生徒会に所属する生徒達がポスターを持って呼びかける姿は、道行く人々に強く印象づけられたことと思います。
2017年05月11日






平成29年5月11日(木)に木津南防犯ステーション活動~割れ窓理論実践運動(落書き消し)~を行いました。
ところで、皆さんは割れ窓理論というものをご存じでしょうか。割れ窓理論というのはアメリカの犯罪学者により提唱されたもので「建物の窓など1枚の割れた窓ガラスを放置すると、割られる窓ガラスが増え、その建物全体が荒廃し、いずれ街全体が荒れてしまう」という理論です。
この活動は、その理論に基づき、防犯意識を醸成するための取り組みとして木津高校生と地域住民、企業、行政、警察等が協働して取り組んでいる活動です。このように、身近なところから一つずつ改善していき、よりよい環境を地域共々作り上げていきたいと思います。
2017年05月10日




平成29年5月10日(水)に、制服着こなしセミナーを行いました。
今回は株式会社トンボからお越しいただいた講師の方に講演を行っていただき、制服を正しく着用することの意義や制服の持つ役割など、専門的な角度から話を聞くことができました。生徒には、日頃から身だしなみについて厳しく指導していますが、今回の話を聞いてその真意を感じ取ってもらえればと思います。
2017年04月25日






4月17日(月)に行われた木津駅周辺の清掃活動に参加しました。
この活動には毎月参加しているのですが、ものの30分ほどでたくさんのゴミを拾うことができました。中にはしゃがみ込んでゴミを拾ったり、溝の中に突っ込んでゴミをかき集めたりしている生徒もいて非常に熱心に取り組んでくれていると思います。
また、今回の活動には警察の方も参加され、木津高校の生徒は清掃活動に加え、警察の方の指導の下、駐輪場にある自転車に盗難防止を呼びかける活動を行いました。少しでも、自転車の盗難被害の減少に役立てることができればと思います。
2017年04月14日






平成29年4月14日(金)、新入生に対し歓迎会を行いました。
どの部活動も入部してみたいと思えるような部活動発表をしてくれ、新入生はかっこいい先輩たちの姿に釘付けでした。
新入生全員が部活動に加入し、より充実した高校生活を送ってほしいと思います。
2017年04月12日








4月11日、12日 2日間にわたって1年生を対象にオリエンテーションを実施しました。
このオリエンテーションは新入生が本校の教育活動を学び、高校生の自覚をもって充実した高校生活を送れるようにするものです。
11日は教務部・生徒指導部・保健部から、12日は進路指導部・教育推進部・生徒指導部 人権担当・第1学年部から
本校での決まり事やマナー、意識して生活して欲しいことなどについて学びました。
生徒たちはきちんと2列に整列して、真剣な様子でメモをとりながら話を聞いていました。
2017年04月10日

4月10日(月) 午後2時 さくらの花吹雪の舞う中、平成29年度入学式を挙行しました。
式では、学校長から式辞の中で「目標を高く設定し、日々の努力を地道に重ねてほしい」「良き友を多く作って欲しい」「感謝の気持ちを常にに持ち言葉に表して欲しい」という3つの話がありました。
新入生宣誓、在校生歓迎の言葉、来賓祝辞などがあり、新入生280名は落ちついた雰囲気の中、入学式を終えました。
2017年04月10日






4月10日(月)午前、第1学期始業式を行いました。
始業式に先立ち着任式を行い、今年度木津高校に着任された先生方の紹介があり、代表で吉津副校長先生よりご挨拶がありました。
始業式では、学校長より「読書は想像力を高める」「協調性やコミュニケーション能力を高めてほしい」という話がありました。始業式終了後、第2・3学年の担任団と分掌部長の紹介がありました。その後、教務部・生徒指導部・進路指導部より話の後、生徒達は新しいHR教室で新年度をスタートさせました。
2013年04月30日
課題研究では3年生の2単位で、いろいろな研究に取り組んでいます。
平成23年度の研究テーマ
○サツマイモの品種比較栽培
○ネリカ米の栽培技術開発
○木津高校オリジナルのシクラメン作り
○いろんな植物でお茶作り
○プランターでの野菜作り
○メロン栽培
○エディブルフラワー作り
平成22年度課題研究のテーマ
○スイカとメロン栽培
○木を植える
○規格外農作物に付加価値をつける
○環境稲作
○シクラメン
○砂漠で米は作れるかⅡ
○西洋わさびの栽培と商品開発
○木津オリジナルシクラメンを目指して!
○色と染め物
2013年04月30日
2:学科の学習について
(1)中心科目の流れ

(2)総合実習の流れ

1年 SP実習
(トウモロコシ・エダマメ)
(ダイコン・ブロッコリー・ハクサイ)
2年
草花・野菜・茶の栽培(ローテション)
3年
専攻に分かれての実習
(3)専攻授業
草花

鉢花栽培
(ポインセチア・プリムラなど)
花壇苗の栽培
(ビオラ・ビンカなど)
野菜

施設栽培(トマト・キュウリ)
露地栽培(ハクサイ・ナスなど)
茶業

緑茶の栽培・製造(かぶせ茶など)
茶の栽培・製造(かぶせ茶など)茶の鑑定実習
(4)特色ある専門授業
農業と環境

農業に関する基礎技術を学びます。
農業情報処理

パソコンを使えるようにし、資格取得を目指します。
植物バイオテクノロジー

バイオテクノロジーについての学習
フラワーデザイン

フラワーアレンジメントの学習をします。
毎年2月に卒業作品展を開催します。
生物活用

園芸を通して地域との交流などを学習します。
地球環境

身近なところから環境について考えるために、ゴミ拾い活動もしています。
Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.