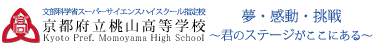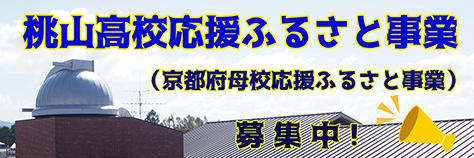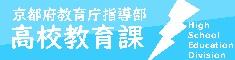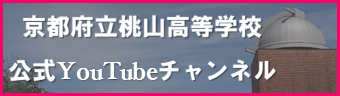Loading…

2016/06/18
6月11日(土),18日(土)に1年生自然科学科対象のSSH講座、「水質を良くする微生物たちを観察する」を実施しました。京都学園大学 教授 金川貴博 先生 にお願いしました。
京都市域の水道水はほとんどが、琵琶湖の水です。琵琶湖の水には滋賀県の生活排水がはいっています。また、大阪の水道水は淀川の水で、京都をはじめ、上流の生活排水がはいっています。従って生活排水をしっかり浄化しなければなりません。下水処理施設では、微生物の力を借りて、この処理をおこなっています。この講座では、水の浄化に使われる微生物の塊である活性汚泥について学びました。
まずは金川先生のご講演のあと、生物実験室で活性汚泥の中にいる微生物を顕微鏡で観察しました。ツリガネムシ、繊毛虫類、ワムシ類、センチュウ類、有殻アメーバ類、クマムシなど、多くの動物と、細菌叢がたくさん見られました。さらに化学実験室に移動して、活性汚泥の沈降の様子をグラフ化する実習をおこないました。
その後のお話で、汚水中の有機物が細菌にとりこまれ、それを動物がエサとして食べ、これを魚が食べ、さらにそれを鳥が食べると、「山へ帰る」ことになるのだと教えていただきました。