網野学舎
4月18日(月)の午後、生徒会執行部が主催する生徒会オリエンテーションが行われました。本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、各部が作成した部活動紹介動画を新入生が鑑賞する形式で実施しました。動画は各部の特徴がよく表れていて、部活に打ち込む先輩達の姿に、新入生達は目を輝かせていました。


4月15日(金)、今年度の久美浜学舎との遠隔授業がスタートしました。この遠隔授業は、網野・久美浜両学舎間を通信で結んで、一つの授業を両学舎の生徒が受講し、互いの意見や考えを交流するものです。今年度初となった本日は、商業科目である「ビジネス基礎」と2年生の「物理基礎」の授業が行われました。学舎間の距離は離れていても、生徒達は同じ「空間」の中で、学びを深めていました。


4月13日(水)の3時間目、1年3組を対象に企画経営科オリエンテーションを行いました。企画経営科の教員紹介と生徒による自己紹介が行われた後、年間のスケジュールや各種検定試験の説明がありました。最後は教員の指導の下、ビジネスマナーの基本である礼の仕方や挨拶などの作法を全員で練習しました。1年3組の生徒にとっては入学後初めての「商業」との出会いの場となりました。



4月13日(水)の2時間目、1年生が各クラスのホームルームで自己紹介をしました。まだ出会って間もないクラスメイトたちの前で、新入生は一人一人初々しく、時には少し恥ずかしそうに自分自身の紹介をしながらクラスメイトに向けて挨拶をしました。一つ一つの紹介に、クラス全員から温かい拍手が送られていました。



4月12日(火)、1年生を対象に新入生オリエンテーションを行いました。
1年生は教務部、生徒指導部、進路指導部、人権教育担当からそれぞれ講話を聞き、高校に入って初めて知る様々なシステムや高校生としての心構えなどについて学びました。
新入生にとっては、本日が本格的な学校生活のスタートとなりました。皆さん、学校生活に早く慣れるといいですね。


4月11日(月)、満開の桜と穏やかな春の日差しが心地よく包む中、丹後緑風高等学校網野学舎において、令和4年度入学式を挙行しました。網野・久美浜両学舎合計119名の新入生は、大きな拍手の中、喜びと緊張が入り混じった様子で入場しました。各担任から呼名を受けた後、岡田校長から入学を許可されました。
式辞で岡田校長は、あるアメリカの大手IT企業の開発責任者の精神を通して、高校生活を始める新入生に対し、「夢や目標を持ってほしい」、「新たな価値を創り出す楽しさを経験してほしい」という期待を伝えました。
続いて、網野学舎PTA会長の堀秀一様から祝辞を頂き、人の成長を妨げる「壁」を攻略するには、試行錯誤を重ねながら必ず乗り越えてみせるという強い意志をもって楽しく努力を続けることが大切だというお言葉を頂きました。
最後に、新入生を代表して、網野学舎の岸本拓也さん(久美浜中)と久美浜学舎の田中優菜さん(久美浜中)が新入生代表として、本校の規則をよく守り、生徒としての本分を尽くすことを宣誓しました。
閉式後、新入生はそれぞれの教室へと移動し、初めてのLHRを行いました。高校生としての第一歩を踏み出した新入生の皆さんの活躍を期待しています。






4月8日(金)、始業式に先立ち、人事異動に伴う離任式ならびに着任式が行われました。新たに着任した岡田泰行校長の挨拶の後、離任した大村孝志前校長のメッセージが代読されました。その後、着任した教職員が紹介され、代表して長島將之教諭が着任の挨拶をしました。


令和4年度第1学期始業式を行いました。
式辞で岡田校長は、この4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことを踏まえ、「大人になるために必要なこと」とは、先を見通した他人に対する思いやりであり、それを習慣化していくことであると、世界的な成長を遂げたある企業の取組を通して話をしました。
続いて、生徒会執行部による伝達表彰が行われ、第37回全国高等学校新体操選抜大会で男子個人総合6位に入賞した谷口央弥さん(2年2組・網野中)が校長から表彰を受けました。



3月18日(金)、令和3年度第3学期終業式を行いました。大村校長は式辞で、網野高等学校全日制・丹後緑風高等学校継承式での校長挨拶や生徒メッセージを紹介し、式の内容や様子を全校生徒と共有しました。そして一年の締めくくりとして「思えば強し」の言葉を生徒に贈り、式辞を結びました。
引き続き伝達表彰・壮行会を行いました。伝達表彰では、防犯寸劇ボランティアに取り組んだ演劇部が警察署から感謝状を頂きました。続く壮行会では、3月末に開催される全国高等学校選抜レスリング大会に出場するレスリング部に対し、全校生徒から激励の拍手が送られました。
最後に、教務部長から年間の学習時間調査の結果と3学期の成績について、生徒指導部長からは清潔感のある身だしなみについてそれぞれ話がありました。

3月9日(水)、全国高等学校新体操選抜大会の壮行会を行いました。18日(金)から19日(土)にかけて熊本県にて開催される「令和3年度第37回全国高等学校新体操選抜大会男子新体操個人競技」に、1年2組の谷口央弥さん(網野中)が出場します。なお、本校にとっては7年振り7回目の出場となります。
谷口さんは、「コロナ禍で練習にも制限はまだまだありますが、だからこそ一日一日の練習を大切に積み重ねて最善の準備をして本番に挑みます。大会本番では自分らしい演技を発揮して次の全日本選手権につながる演技を見せていきたいです。」と力強く意気込みを語っていました。

卒業式前日に表彰を受けた企画経営科3年生の5名に喜びの声を聞きました。
■全商協会4種目1級合格(4冠)
【全商簿記実務検定 珠算・電卓実務検定 情報処理検定 商業経済検定】
給田江里菜さん(丹後中)
1年生から学び始めた商業の専門分野を3年間学んだ結果、卒業目前で検定1級を4種目も合格することができました。こんなにも力をつけることができたことに自分自身驚いていると同時に、企画経営科で学んできて本当に良かったと思っています。支えてくれた先生や友達に本当に感謝しています。
■全商協会4種目1級合格(4冠)
【全商簿記実務検定 ビジネス文書実務検定 情報処理検定 商業経済検定】
谷岡京香さん(網野中)
検定試験は学校の定期試験と日程が重なることもあったので、勉強するのが大変でしたが、今まで勉強をしてきた成果が最後に表彰されてすごく嬉しかったです。この3年間いろいろな人に支えてもらったから今の自分があるのだと思います。感謝の思いを忘れずに、これからも自分の夢に向かって勉強を頑張っていきます。
■全商協会3種目1級合格(3冠)
【簿記実務検定 情報処理検定 商業経済検定】
中谷翼さん(大宮中)
高校3年間は毎日が部活動と勉強の両立の挑戦でした。遅くまで野球に打ち込み、帰ってからは短い時間でも机に向かって検定勉強に励みました。周囲の応援のおかげもあって、野球部として初の「3冠」を獲ることができました。毎日おいしいお弁当を作り、いつも笑顔で送り出してくれた母には特に感謝しています。本当にありがとう。
■全商協会3種目1級合格(3冠)
【珠算・電卓実務検定 情報処理検定 商業経済検定】
鈴木南々香さん(網野中)
やるからには絶対に合格したいと臨んだ最後の検定試験で、1級が取得できて本当に嬉しかったです。部活から帰って疲れて寝てしまっても、「勉強しなくちゃ」と途中で起きて机に向かったことも少なくありませんでした。私の3年間の努力の結果が、こうして最後に「賞」という見える形で現れて本当に嬉しかったです。
■京都府教育長賞(16名)
坂根光和さん(峰山中)
先日のホームルームの時間に賞を頂けることを知りました。心の準備をまったくしていなかったので正直驚いてしまいました。3年間勉強は大変でしたが、先生も友達も私のわからない箇所を丁寧に教えてくれたので、楽しく進めることができたし、何より学校生活はとても充実していました。お世話になった皆さん、本当にありがとうございました。
...君達の築いた「栄冠」は、君達自身の「将来」をこれからも照らしゆくことでしょう。
(取材・文 安達卓能)

今回は1年2組の国語総合の様子です。日本最古の歌物語である「伊勢物語」では、恋人や親、親友をはじめとした様々な愛情が描かれています。本時で扱った「筒井筒」は、幼馴染との恋愛が描かれる章段です。結婚後、別の女のもとに通うようになった男が、妻の詠んだ和歌に感動し浮気をやめる、という本文の記述をもとに、登場人物の心情の変化を読み解きました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、話し合い活動等にも制限が多い中での授業でしたが、ICTを活用しながら全体で読みを深めていきました。

2月9日(水)、新型コロナウイルス感染症対策を万全に講じた中、1年生が4教室に分かれて自己発見レポート報告会を行いました。これまで作成してきた自己発見レポートをもとに、高校に入学してからこれまでの1年間をそれぞれ振り返りながら、自分自身が感じたことや来年度に向けての決意などを自分らしく語りました。それぞれの発表に対し、参加者からは温かな拍手が送られていました。

2月6日(日)、地域探究・地域創生を題材とした探究活動に取り組んでいる府立高校の代表生徒による京都フロンティア校研究成果発表会が開催されました。今年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大を踏まえ、オンラインで実施されました。本校は「よし、まなボッチャ」をテーマに企画経営科の1年生が発表を行いました。講評の先生や他校の生徒達からは、一クラス一ボランティアの取り組みや京丹後市の未来を考えるゲームであるSIM京丹後(行政運営シミュレーション)の活動が評価されました。「恐丹後お化け屋敷」や「京竜の秘宝を探せ」などこれまでに企画運営を行った地域における行事などについても、プレゼンテーション発表を通して、他校生に紹介することができ、今後の地域創生の在り方について考えを深めることができ、充実した一日となりました。

2月2日(水)、2年生が進路研究を行いました。先週行われた分野別進路説明会での内容を踏まえて、志望校に関する入試情報や受験科目などについて調べました。自分の進路を実現させるためには、これからどのような勉強をしていくべきかを考える良い機会になりました。

1月13日(木)、大学入学共通テスト壮行会・直前説明会を行いました。大村校長と義村学年部長から「常に次のことを考えて前へ前へ進もう」「周りを気にするな!自分のペースで!」と励ましの言葉がありました。続いて、進路指導部の担当教員と引率教員から日程や注意事項の最終確認がありました。受験生の皆さんの御健闘をお祈りしています!

1月13日(木)、「税に関する高校生の作文」の表彰式が行われました。本校から1年1組の小路実寛さん(峰山中出身)が「京丹後地区租税教育推進協議会長賞」に入選しました。

1月7日(金)、第3学期始業式を行いました。校長式辞では、生徒会執行部が生徒信条の全文を朗読し、新年を新たな気持ちで迎えました。続いて生徒会執行部による伝達表彰・壮行会を行いました。壮行会では、レスリング部と体操部が山口生徒会副会長と大村校長からそれぞれ激励の言葉を受けました。最後に生徒指導部長から、寒さやコロナに負けないように、健康な生活習慣を保つ3学期の過ごし方について訓話がありました。

12月20日(月)、第2学期終業式を行いました。式辞の中で大村校長は2学期を振り返った後、ノーベル物理学賞の真鍋淑郎氏の言葉から、好奇心を持つことの大切さについて話しました。さらに、「伝える力」と「聞く力」の大切さ、自分の命も他人の命も大事にすることの大切さについて、全校生徒に呼びかけました。
終業式後は、令和4年度新生徒会役員の承認式が行われました。前生徒会長の奥野颯さんから激励の言葉を受けて、新たに就任した新生徒会長の川崎珀杜さんが「この丹後緑風高校網野学舎を盛り上げられるよう精一杯行動していきます。」と力強く挨拶をしました。その後、新生徒会執行部によって伝達表彰が行われました。
最後に、教務部長から学習時間調査の結果と成績について、生徒指導部長から学校生活についての総括がありました。

企画経営科は私達にとって最高の学び舎
12月5日(日)に行われた「自転車交通安全CMコンテスト」の表彰式において、協賛団体特別賞であるキョウテク賞を授与した企画経営科3年生のグループに、受賞の喜びや企画経営科に入学をして良かったことなどについてインタビューしました。
石田理咲子さん(峰山中)
今回のCM案は私が中心になって考えさせていただきました。子供達にも親しみやすくわかりやすい内容にしたいと思い、動物のキャラクターを使って自転車運転のマナーをクイズ形式にして15秒にまとめました。受賞の知らせを聞いた時は、すぐには信じられませんでした。このような賞を頂いたのは初めてだったので、すごく嬉しかったです。表彰式は立派な会場で行われましたし、たくさんの大人の方に囲まれて本当に緊張しました。表彰の時に、たくさんの方から拍手を頂いた時は、まるで夢の中にいるような気持ちでした。
将来は自分で作ったものを活かして、子供達に笑顔を届けることができる保育士になりたいです。企画経営科で、私はたくさんの力と自信をつけることができました。そして素晴らしい仲間と出会うことができました。私は本当に幸せ者だと、みんなに感謝しています。
鈴木南々香さん(網野中)
CMは商業デザインという授業の中で考え、みんなで役割を分担して作っていきました。100作を超える応募作品の中から賞に選ばれたなんて、私も信じられませんでした。表彰式は周りの雰囲気に圧倒されて緊張しました。しかし、人生初めての大きな会場で賞を授与され、ようやく本当に入賞したんだと実感することができました。卒業間近でこのような経験ができたことは、とても貴重な体験でした。この取組を通して、一人一人が自分の役割を担ってこそ、良い作品をつくることができるということを学びました。
私は将来、放射線技士の道に進みますが、患者さんを救う医療チームの一員として、私の与えられた役割を担えるように、これからも様々なことを学び続けていきたいです。企画経営科は、全員が始めて商業を学ぶので、スタートラインは一緒です。検定試験を数多く受けて合格できれば、それが3年生になった時に、希望進路の実現に大きく役立ちます。夢に近づけたという意味で、私は企画経営科に入学して本当に良かったです。
吉岡璃子さん(丹後中)
自転車の「ながら運転」はとても危険だということを、いくつかの例を示して正解か不正解かを子供達でもわかるように工夫しました。15秒という短い時間の中で、伝えたい内容をまとめることに苦労したので、入賞したと知ってびっくりしました。表彰式では、他の受賞作はどんな内容だろうかと興味津々でした。でも、私達の表彰で名前が呼ばれたときには、我に返って急に緊張しながら壇上に登りました。多くの人の前で堂々と発表できる人間になりたいと思い、一生懸命勉強して企画経営科に入学したことが私にとっての第一歩でした。専門的な勉強は難しくてとても大変でしたが、先生を含め、周りのみんなが本当に良い人ばかりで、私がわかるまで何度も親身になって教えてくれました。私にとって、このクラスは最高のチームであり最高の仲間達でした。中学生の皆さん、進学するならぜひ企画経営科をおすすめします。
卒業後は、小さい頃からの夢だった美容師の資格を取り、企画経営科で学んだ経営の知識やチームワークの大切さを活かして社会で活躍していきたいです。
...「企画経営科は最高です」と口を揃えて話してくれた彼女達。しかし、何よりも「最高」なのは、真剣に学び実践し、結果を出し、そして仲間と共に喜び合う、まさに彼女達の姿そのものだと私は思いました。
(取材・文 安達卓能)
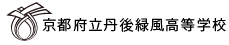

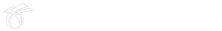
 クリックで子カテゴリが表示されます。
クリックで子カテゴリが表示されます。
