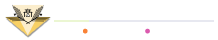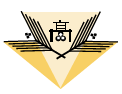フィールド探究部(F探)が受賞した
「全国ユース環境活動発表大会全国大会 先生が選ぶ特別賞」と
「日本自然保護大賞 子ども・学生部門 大賞」
の伝達表彰を行いました。
「賞をいただいたことは、全国でF探の活動が評価されたということであり、
これを自信として、これからも頑張ってほしい」との校長先生の言葉に、
部員たちは、誇らしげに、力強くうなずいていました。
引き続き、3月25日からオンラインで開催される
「全国高校生マイプロジェクトアワード全国summit」に出場する
藤本和奏さん(HR22)の壮行会を行いました。
校長先生からの激励の言葉に、藤本さんは
「先輩たちの思いを引き継いで活動してきた。summitでは精一杯頑張りたい」
と決意の言葉を述べました。
summitには2年連続の出場となります。
全国で活躍するフィールド探究部。これからもいろんな「探究」にチャレンジし
世界を広げていってください。
美術・書道作品展の開催に代えて、作品集を発行しました。
2年生は進路HRとして、受験を終えた卒業生と語る会を実施しました。1つしか学年は違いませんが、受験という大きな山を乗り越えた先輩から、この1年間の経験を話してもらい、やって良かったこと、辛かったこと、おすすめの参考書など、たくさんのアドバイスをしてもらいました。
これまでの本校PTA活動の実績・功績が認められ、令和3年度「優良PTA文部科学大臣表彰」を受賞しました。
この賞は、文部科学省がPTAの健全な育成と発展に資することを目的として、毎年度、優秀な実績を上げているPTAを表彰するものです。
本年度は、国公立幼稚園・認定こども園の優良PTA団体13団体及び高等学校・中等教育学校の優良PTA団体20団体が表彰団体として決定し、その1団体に本校PTAが選ばれました。
表彰式は第70回全国高等学校PTA連合会全国大会で行われる予定でしたが、オンライン開催となり、11月17日に京都府教育委員会の方が来校され、伝達表彰を執り行っていただきました。
今年度は、昨年度に続いて文化祭の中止によりPTA模擬店やPTA作品展示の取組を行うことができないなどPTA活動にも制限がありましたが、交通安全街頭登校指導やPTAだよりの発行など、PTA運営委員の方々を中心に地区役員の方々の御協力により実施することができました。
来年度も引き続き、PTA活動に御理解と御協力をお願いします。
1月26日(水) 第5回文化部会を行いました。
今年度最後のPTAだより228号の発行に向けて、紙面のレイアウトを行いました。
第6回文化部会は、新型コロナウイルスの感染拡大によって第5回文化部会の翌日から「まん延防止等重点措置」が実施され、中止となりました。
第5回文化部会が文化部にとっての最後の部会となりました。PTAだよりの発行に向けて、構成や校正をお世話になった文化部員の皆様、1年間ありがとうございました。
12月7日(火) 第3回PTA交通安全街頭登校指導を行いました。
気温がだんだん寒くなってきていますが、朝から元気に挨拶をする生徒もいました。道路の凍結や雪の降る季節からだんだんと暖かく春の陽気に眠くなる季節になってきましたが、生徒たちには安全に登下校をしてもらいたいです。
11月25日(木) 第4回 文化部会を行いました。
主な内容は、PTAだより227号の校正(文章等の誤りを訂正・確認)作業を行いました。
第3回文化部会で構成(レイアウト)したものが仮製本され、文章の誤字脱字等の確認しました。