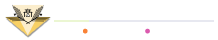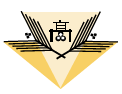7月27日(水)から3日間、1年生を対象に集中学習会を行っています。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、学校を勉強の場として、朝から夕方まで集中して学習に取り組んでいます。
また宮津高校を卒業した3人の先輩に来ていただき、受験に向けた勉強の方法や大学生活について話してもらいました。それぞれ目標としていた大学に向けて、どのように工夫して勉強し合格を勝ち取ったのかという話や、自身の将来に向けて現在どのような大学での生活を送っているのかなど詳しい話をしてもらいました。そして先輩の講話を聴くだけでなく、その後設けた座談会では1年生から多くの質問があり、より具体的な話から自身の将来に向けてどんな勉強をしていけばよいのかイメージができたのではないかと思います。
今回の集中学習会のテーマは「『変わる』きっかけを手に入れる3日間に...」です。仲間と共に学習に励み、自分が変わるきっかけを作ってください。
7月20日(水)、大掃除・LHR・終業式を行いました。
LHRではHR担任が一人一人にコメントを添えて通知票を手渡しました。クラス毎及び個人での今学期の振り返りを基に、目標を達成した人はそれを励みに、目標にあと一歩届かなかった人はその悔しさをバネに新たな目標の達成に向けて頑張ってください。
また、1年生の建築科では作業服の配布も行われました。生徒達は自分が作業服を着て、建築実習に懸命に取り組む姿を想像しているようでした。
伝達表彰・壮行会を行った後、終業式では校長先生のお話がありました。各学年の生徒へ向けて力強い、熱いメッセージを伝えると共に、「強いということは自分の弱さを知っていることだ」と話されていました。自分の弱さを知り、それを克服するためにどう動くかを考えることも宮津天橋高校で培って欲しい力の一つです。


伝達表彰では以下の成績を残した生徒を表彰しました。
第74回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会 女子フィールド総合 2位
第72回近畿高等学校ボート選手権大会 女子舵手付きクォドルプル 優勝(京都勢初の大会2連覇)
第33回近畿高等学校ヨット選手権大会 女子シングルハンド 3位(このカテゴリー初めてのインターハイ出場権獲得)


また、全国大会出場が決まった以下の生徒の壮行会も行いました。
ボート部 令和4年度全国高校総体ボート競技 女子舵手付きクォドルプル
ヨット部 令和4年度全国高校総体ヨット競技 女子シングルハンド 第77回栃木国体
書道部 第46回全国高校総合文化祭東京大会 書道部門
写真部 第46回全国高校総合文化祭東京大会 写真部門
そして、4年間宮津天橋高校で働かれていたAETのネイサン・ニューベリー先生が母国に帰られることになり、お別れの挨拶をしていただきました。
1学期が終わり、夏休みが始まります。生活リズムを乱さないように自分を律しながら、各々充実した夏休みを送ってください。
7月19日(火)、京都府警察署の方をお招きし、全学年を対象とした薬物乱用防止教室を行いました。
近年、SNSの普及も相まって、未成年をターゲットにした違法薬物の取引が増えており、京都府内でも高校生が違法薬物の事件に巻き込まれるケースが複数報告されています。また、講義の中では違法薬物の他にもSNSにまつわる誹謗中傷といった事例などのお話もしていただきました。違法薬物やSNSの利用に対する正しい知識を身につけ、自分の安全を自分の力で守れるよう、今回の学びを今後の生活に活かしてください。


7月15日(金)、1年生にBYODタブレットが配布されました。配布時には使用するときの注意事項を伝え、学びに向けた使い方ができるように指導しました。また、生徒はタブレットの使い方を知るために、宮津天橋高校のホームページを検索してみるなど、簡単な調べものを行いました。タブレットを使った授業の導入によって、更に学びの幅が広がります。宮津学舎では従来の学習法と最新のタブレット学習のそれぞれの利点を生かし、学びを深めていきます。昨日の授業では生徒たちはとても楽しそうにタブレットを使っていたので、この楽しさを勉強への意欲につなげてください。
7月12日(火)宮津市立府中小学校の「総合的な探究の時間」において、同小学校卒業生の藤本和奏さん(HR32)が、自身の所属するフィールド探究部の活動とタンポポの研究について講話を行いました。また、質問の時間では、荒木翼さん(HR34)が加わり、2人で小学生たちの疑問に回答してくれました。
府中小学校では府中の歴史を学ぶ学習が進められており、今回は地元の高校と自分たちの地域に関わるフィールド探究の活動を知り、またタンポポの研究から探究のプロセスを学ぶことで、自分たちが暮らす地域に対する愛着を深めてくれる機会になりました。

7月6日(水)、人間座の方にお越しいただき、文化祭で2,3年生の各クラスが取り組む演劇の指導をしていただきました。今回は、演劇の題目の選び方やどのような演劇が良いかなどを具体的に助言していただきました。各クラスから2~3名の代表生徒が出席し、積極的に質問も行っていました。1学期期末考査を終え、学校祭に向けての取り組みが本格化していきます。3年ぶりに行う学校祭が、素晴らしいものになるように力を合わせましょう。
全国高校生マイプロジェクトアワード全国Summitで「ベストマイプロジェクト賞」を受賞したフィールド探究部の藤本和奏さんがテレビ取材を受けました。
藤本さんのたんぽぽの研究に関するインタビューが放映されますので、是非ご覧ください。
放送日時
7月2日(土) 9時00分~12時00分
7月3日(日) 21時00分~24時00分
※各日とも、30分のニュース番組『日テレNEWS24』内で計6回放映されます。
ご覧頂くにはCS放送の有料契約が必要です。
インターネットでのライブ配信(無料)でも視聴可能です。
6月24日(金)、定期考査1週間前になりました。連日猛暑が続いていますが、暑さにも負けず生徒達は考査に向けて学習に取り組んでいます。本日も多くの生徒が自習室に集まって、学習をしていて分からなかった箇所を先生に質問するなど、熱心に学習に励んでいます。土・日も計画的に学習を進めていきましょう。
6月17日(金)、6限のLHRは今年度1回目の学校祭ホームルームでした。各クラスでのクラス取組や体育祭のリーダー決めの話し合いをしました。昨年は文化祭を開催できなかったこともあり、生徒たちの話し合いは熱を帯びていました。
文化祭のクラス取組では合唱や演劇、展示を行う予定です。建築科の3年生は展示として校門アーチを作るなど、今年度も力を入れた作品が見られそうです。合唱や演劇を希望しているクラスでは、教室や図書室で過去の文化祭の映像を見てイメージを膨らませました。先輩がどのような文化祭を作り上げていたのかを参考にして、より素晴らしいものになるようにクラス、学校全体で盛り上げていきましょう。
6月3日(金)、2年生を対象に人権学習講演会を実施しました。視覚障害というハンデを抱えながらも教員として精力的に活動されている、丹後緑風高校の安達先生を講師としてお招きし、「闇が深ければ深いほど、夜明けは近い」をテーマにご講演頂きました。
安達先生は自身の経験として突然難病の宣告を受け人生に絶望しながらも、自分に使命があると自覚し人生を歩んでいらっしゃる話をしていただきました。またどのように授業を行っているかも実演していただき、その授業の準備の大変さと教育に対する熱意を感じました。
生徒たちは真剣に話を聞いており、自分が人生で困難なことにぶつかった時この話を思い出して励みにしたい、安達先生の授業を受けられる生徒は幸せだ、といった感想を述べていました。