スーパーサイエンスハイスクール(SSH)
育て!未来の科学技術系人材 羽ばたけ!世界へ
文部科学省よりSSHの指定を受けた学校では、科学技術系人材の育成のため、各学校で作成した計画に基づき、独自のカリキュラムによる授業や、大学・研究機関などとの連携、地域の特色を生かした課題研究など様々な取組を積極的に行っています。
府立高校では、
平成16年度から洛北高等学校(洛北高等学校附属中学校)
平成22年度から桃山高等学校
平成24年度から嵯峨野高等学校の3校が指定を受けています。
さらに、府立嵯峨野高等学校は、平成25年度から令和3年度まで全国のSSH校の中でも、特に拠点的な役割を担う科学技術人材育成重点枠校(主な取組:京都サイエンスフェスタ、アジアサイエンスワークショップ)の指定を受けていました。
府立高校のスーパーサイエンスハイスクール3校の取組は、京都府教育委員会が行うスーパーサイエンスネットワーク事業を通して、京都府全体の理数教育の発展に貢献しています。
 先進的な科学技術、理科・数学教育を通じて生徒の科学的な探究能力などを培う高等学校等を指定・支援し、将来国際的に活躍しうる科学技術人材を育成する取組です。 平成14年度の事業開始以来、全国各地の指定校において様々な特色ある取組が行われており、現在、卒業した生徒たちが国内外で科学技術人材として活躍し始めています。 →科学技術振興機構(JST)のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)のページはこちら |
府内SSH指定校が開発した主な成果物(教材・ルーブリック等)の一覧
※成果物(教材、ルーブリック等)の詳細については、各校のHPで御確認ください。
府内SSH指定校の成果発表会(令和7年度)
| 校名 | イベント名 | 開催日時 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| SSN京都関係校 | みやこサイエンスフェスタ | 令和7年6月8日(日) | 京都大学 |
| 京都府立嵯峨野高等学校 | Sagano Global Forum for student research(生徒研究成果発表会) | 令和7年6月13日(金) | 京都府立嵯峨野高等学校 |
| 京都府立桃山高等学校 | 自然科学科英語ポスター発表会 | 令和7年6月13日(金) | 京都府立桃山高等学校 |
| 京都府立嵯峨野高等学校 | 探究の質向上を目指した教師のスキャフォールディングに関する研修会 | 令和7年11月21日(金) | 京都府立嵯峨野高等学校 |
| SSN京都関係校 | みやびサイエンスガーデン | 令和7年11月22日(土) | 京都工芸繊維大学 |
| SSH指定校 | 京都府立洛北高校・京都府立嵯峨野高校・京都府立桃山高校による3校合同SSH成果報告会 | 令和7年11月22日(土) | 京都工芸繊維大学 |
| 京都府立桃山高等学校 | 自然科学科GS探究Ⅰ発表会 | 令和7年12月12日(金) | 京都テルサ |
| 京都府立洛北高等学校 | 数学探究チャレンジ | 令和7年12月14日(日) | 京都府立洛北高等学校 |
| 京都府立桃山高等学校 | 普通科GS探究Ⅰ発表会 | 令和8年1月27日(火) 令和8年1月29日(木) | 京都テルサ |
| 京都府立嵯峨野高等学校 | 探究成果発表会 | 令和8年1月30日(金) | 京都府立嵯峨野高等学校 |
| 京都府立桃山高等学校 | 自然科学科SSH課題研究発表会 | 令和8年1月31日(土) | 京都府総合教育センター講堂棟 |
| 京都府立桃山高等学校 | 普通科SSH課題研究発表会 | 令和8年2月10日(火) | 京都府立桃山高等学校 |
| 京都府立洛北高等学校 | 課題研究発表会 | 令和8年3月11日(水) | 京都府立洛北高等学校 |
※各SSH指定校において開催される発表会等について、学校別に掲載しています。
※参加方法や内容等については、各校のHP等で御確認ください。
府立洛北高等学校(洛北附属中学校)

京都Scienceコミュニティ連携企画「パスタブリッジコンテスト」
2025年10月25日(土)に、京都Scienceコミュニティ連携企画「パスタブリッジコンテスト」を実施しました。
全国のSSH校と京都府立高校間をオンラインでつなぎ、各校同時にパスタで橋を作り、その出来を競うものです。昨年よりも参加校が増え、20校、64チームのエントリーがありました。
熱い戦いが繰り広げられ、最終的に22.1gのパスタで4000gの重量を支える橋を作った千葉県の市川学園チームが優勝しました。
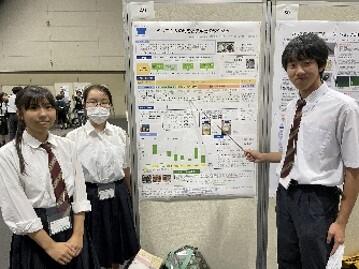
高校生ポスター発表
2025年9月6日(土)に、ポートメッセなごや第2展示館で「日本動物学会第96回名古屋大会 高校生ポスター発表」が行われました。
本校からはサイエンス科の3年生3名が、「ダンゴムシの好む香気成分の同定~彼らはビール愛好家~」と題して、一年間の成果を高校生や研究者の方へ発表し、多くのアドバイスや感想をいただきました。
また、他の高校生の発表を見ることで、研究を進めるアイデアを得ることができました。

和歌山Factoryツアー
2025年8月20日(水)に、希望者27名で、日本製鉄関西製鉄所和歌山地区と花王和歌山工場を訪問しました。
日本製鉄では、製鉄の工程について解説していただき、様々な工程を見学しました。花王和歌山工場では、コラボミュージアムでの実験や展示を通して、界面活性剤の仕組みや環境に配慮したものづくりについて学びました。
特色の異なる二つの工場でしたが、どちらの現場からもより良いものを作ろうとする情熱が伝わり、日本の「ものづくり」の奥深さに触れる貴重な経験となりました。

「しっぽ学」について学ぶ
2025年8月4日(月)に、公益財団法人テルモ生命科学振興財団の企画に4名の生徒が参加し、生命科学分野の最前線で活躍する研究室を訪問しました。
京都工芸繊維大学応用生物学系の東島研究所では、先生の講義の後、有精卵の胚発生を観察し、「しっぽ」に関するユニークな研究について学びました。
この企画に参加した生徒は、「興味のある分野への理解が深まった」「進路について考える良い機会になった」と前向きな感想を述べていました。

島津ぶんせき体験スクール
2025年5月29日(木)に、8名の生徒が島津ぶんせき体験スクールに参加し、島津製作所本社を訪問して、実験・分析装置体験と、島津製作所ショールーム見学を行いました。
生徒たちは、ペーパークロマトグラフィー及びカラムクロマトグラフィーの実験を通じて、クロマトグラフィーの原理を学びました。また、高校ではなかなか実施ができない分析手法を経験し、とても満足していました。

EXPO2025大阪・関西万博に参加
2025年4月23日(水)に、大阪・関西万博で開催された「EXPO KYOTO MEETING~和のこころと地球の未来~」に14名の生徒が参加しました。
このイベントは、京都を代表する高校生ユースによる、ふろしきやリメイク着物のステージパフォーマンスや「いのち輝く未来社会」について語るトークセッションなどを行う企画です。
生徒たちは、本番までの短い期間の中で、他校やメンター達と準備を行い、様々な場面で立派に活躍をしていました。

校外学習
2025年2月21日(金)に、総合地球環境学研究所を訪問しました。
京都の地形のでき方、窒素循環の課題、インドの大気汚染への取組について、3人の研究者の方々にお話しいただきました。また、研究所内にあるクリーンルームや低温保管室、微量元素も検出できる質量分析装置など、設備の紹介もしていただきました。
研究所内の見学は、時間の関係上できませんでしたが、研究者の方からお話を聞き、地球環境についての謎や課題にどのようなアプローチがなされているのか、知見を広げることができました。
府立桃山高等学校
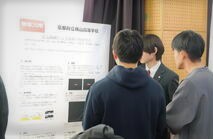
ポスター発表交流会
2025年12月10日(水)に、宮城県立仙台第三高等学校の生徒が来校しました。
本校の自然科学科の生徒と、探究活動の成果についてポスター発表と交流を行い、積極的に楽しく議論をしていました。
この交流を糧に、SSH課題研究発表会に向けて、生徒たちが自律的に探究活動に励むことが期待されます。

植物の簡易組織培養
2025年11月7日(金)に、京都教育大学の梁川先生による「植物の簡易組織培養」と題した講座が行われました。
組織培養の理論を学んだ後、市販の殺菌剤と肥料を混ぜた寒天培地を作り、塩素滅菌やアルコール無菌操作などを簡易に行う手法を用いて、実際に植物組織(シンビジウム、シラン、セイロンベンケイソウ)を培地へ植え付ける体験をしました。

国立台南第二高級中学との交流
2025年10月30日(木)に、台湾の国立台南第二高級中学から生徒30名が来校しました。
2022年度より、希望生徒を対象にオンライン交流を重ね、3月には本校生徒が台南第二高級中学を訪問しており、今回の来校はその一環として実現したものです。
当日は、これまで交流してきた生徒に加え、高校2年生文系クラスを中心として、茶道や折り紙、書道の体験、英語でのディスカッションやキャンパスツアーなど、日本の文化や学校生活を紹介しながら交流を深めました。

手動PCRでブタの品種を鑑定しよう
2025年10月15日(水)~17日(金)に、長浜バイオ大学の福井先生による「手動PCRでブタの品種を鑑定しよう」と題した講座が行われました。
マイクロピペットの使い方を始め、手動PCRや電気泳動などの遺伝子実験における基本操作や概念を学ぶことができ、生徒たちも興味をもって熱心に取り組んでいました。最終日には、生徒たちへ修了証書が手渡されました。

琵琶湖湖上実習
2025年9月21日(日)に、滋賀大学環境総合研究センターの「びわ湖・瀬田川オブザベトリ」においてSSH事業「琵琶湖を探る」を実施しました。滋賀大学教育学部教授石川俊之先生のご指導の下、午前中は実習船に乗って採水や透明度測定などの水質観察を行い、午後からは、採集したプランクトンの観察や琵琶湖に関する講義を受けました。生徒たちは五感で琵琶湖を感じるという貴重な体験をしました。

グローバルサイエンス部 夏合宿
2025年8月3日(日)~5日(火)に夏合宿を行いました。
一日目は、鳥取砂丘や鳥取大学乾燥地研究センターへ行き、乾燥地帯の文化や農業について学び、一生のうちに一度しか開花しないアガベの花や天の川を見ました。二日目は、井倉洞へ行き、自然のダイナミックさや美しさを体感し、岡山理科大学生命科学部准教授山本俊政先生から「好適環境水」の研究について講義をしていただきました。三日目は、博物館へ行き、カブトガニを観察したり、標本の管理方法などを学びました。生徒たちは、とても充実した日々を過ごしました。

天体観測会
2025年4月28日(月)から29日(火)にかけて、校内で天体観測会を実施しました。 夜中に雲が出てきて観察しづらい時間帯もありましたが、新月だったので、普段は見えにくい星でも肉眼で観ることができ、天体望遠鏡では、火星と金星を観察しました。
府立嵯峨野高等学校

探究交流会
2025年12月10日(水)に、SSH校である宮城県仙台第三高等学校の生徒44名が来校され、探究交流会を行いました。
嵯峨野高等学校の生徒会役員が学校紹介を行ったり、仙台第三高等学校の生徒が仙台に関するクイズ大会を開催したり、午後からは、専修コース二年生が所属するラボごとに分かれてお互いの探究内容について発表・質疑応答を行うなど、一日を通してたくさんの交流を行うことができました。
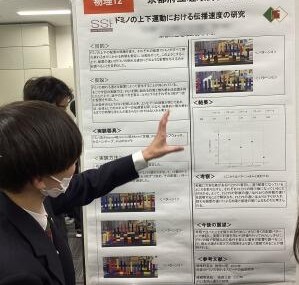
みやびサイエンスガーデン
2025年11月22日(土)に、京都工芸繊維大学でみやびサイエンスガーデンが開催されました。
このイベントは、京都府教育委員会と京都府内のSSH指定校が主催し、日々の探究の成果をポスターセッション形式で発表するものです。
本校からは、40件のポスター発表を行い、他校の生徒や先生方、来賓の方々と活発な議論や交流を行いました。

SSH公開授業研究会
2025年11月26日(水)に、SSH公開授業研究会を開催しました。
今年度は、「教科・科目での探究学習」と「探究を支援する教員の足場かけ」をテーマとして設定し、京都府内だけでなく、他府県からも多くの教員、大学生、大学院生の方々が来校されました。午前中は、パフォーマンス課題や文献調査など、探究的な学びを取り入れた授業が公開され、生徒たちは、いきいきと楽しそうに取り組んでいました。午後からは、立命館大学OIC総合研究機構客員研究員 蒲生諒太氏を講師に招いて教員研修を行いました。

サイエンスレクチャー
2025年9月26日(金)に、京都大学大学院農学研究科の丸岡毅さんから「ムシのフンってどんな味?」というタイトルの講義を受けました。
丸岡さんは、飼っていたガの幼虫に桜の葉を食べさせたところ、フンがとても良い香りをしていることに気づき、大胆にもお茶として飲んだところとてもおいしいことを発見されました。飲食店やメディアから注目を浴び、様々な人と関わりながら現在も活躍されています。
講演後は生徒たちからの質問が続き、終了後も残って話を伺う生徒もいました。

ジャパンフィールド・リサーチin熊本
2025年9月13日(土)~15日(月)に、熊本県玉名郡和水町「ゆるっと!ひふみ亭」を拠点とした森林や竹林、土壌などのフィールド調査を行いました。
三日間の中で、熊本県立の高等学校の生徒や先生、さらに、東海大学農学部の井上弦教授や学生と交流したり、前 和水町教育長の岡本貞三先生から「和水町の自然について」の講義を受けました。出発前の予報では天候が危ぶまれ、野外活動が行えない可能性もありましたが、活動を妨げるほど天候は悪くならず、計画通り調査活動を行うことができました。
これら取組については、2025年11月22日(土)の「みやびサイエンスガーデン」で研究成果を発表する予定です。

東京・つくばサイエンスツアー
2025年7月30日(水)、31日(木)に、サイエンスツアーを行い、10名の生徒が参加しました。
一日目は国立科学博物館の見学、東京大学先端科学技術研究センター極小デバイス理工学分野の岩本敏教授による特別講義および研究室見学、卒業生からの講話を実施しました。二日目はつくば市に移動して、地質標本館、JAXA筑波宇宙センター、国土地理院地図と測量の科学館を見学しました。生徒たちは二日間で化学の面白さを味わうことができました。

第69回システム制御情報学会研究発表
2025年5月25日(日)から27日(火)に、神戸市産業振興センターで第69回システム制御情報学会研究発表が開催されました。
3名の生徒が2つのテーマ(「ルービックキューブを用いた耐量子計算機暗号のアルゴリズム」、「辺連結度を中心とした交通ネットワークの評価指数」)でポスター発表を行いました。
発表を行った両者はともに、優秀発表賞を受賞しました。

