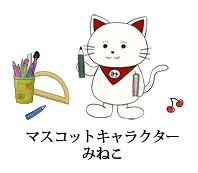学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 「地域に対する若者の意識調査をし...
「地域に対する若者の意識調査をしてみよう! ~アンケート調査の基礎に関して専門家から学ぶ」
みなさん、こんにちは!
今回、紹介する高校生たちの探究活動に関しては、
過去に何本も書いてきているのですが、
もう少しお伝えしたいことがあるので、今暫くお付き合いいただけますと幸いです。
***
【「京丹後市民の幸福度~このまちの魅力と可能性」チームの探究活動】
"人口減少"に歯止めをかける手立てとして、
「どうすれば京丹後市に人を呼び込めるのか」について
検討するところからチームの活動がスタート。
そして様々な人々からお話しを聞くことを通して、
段々と考え方に変化が生じていったメンバー。
「人口を増やす」ことに注力するのではなく、
既にこのまちで生活をしている
「市民の幸福度が高ければ」必然的にまちとしては、
とても良い状態なのではないか、という考え方に移っていきます。
地域の方への幸福度に関するヒアリングの様子については、
以下の記事にまとめておりますので未読の方は、
お時間のあるときにご一読ください。
※これまでの記事
vol.2 「Tangonian代表/長瀬さんへヒアリング」
vol.3 「丹後暮らし探求舎相談員/坂田さんへヒアリング」
vol.5 「京都府地域アートマネージャー/甲斐少夜子さんへのヒアリング」
〈幸福度に関する実態を調査するためのアンケートをとってみよう!〉
5人の方へのヒアリングを通して、
高校生たちの地元に対する印象は、
随分ポジティブなものとして受け止められるようになりましたが、
実際のところ、高校生の若い世代は、
京丹後というまちに対して、どのような印象を抱いているのか
大人が感じているまちに対する想いとは、
隔たり(ギャップ)があるのではないか。
もしあるのだとしたら、高校生たちは
"何に対してネガティブさを感じているのか"。
そういった実態を把握することが、
そのギャップを埋めていくための
手立てのアイディア出しに役立つのではないか。
そんな風に考えた高校生たちは、
峰山高校生対象にアンケート調査を実施することを決めました。
ここで相談したのが、同志社大学社会学部社会学科の准教授、
轡田竜蔵先生。
轡田先生は、地方に住む若者の幸福や意識に関して
専門に研究されており、
これから調査を進めるにあたって助言を仰ぐのに
先生に匹敵する人はいない!
ということで、早速相談してみることにしました。
〈轡田先生とのお話〉
轡田先生 「みなさん、こんにちは!
同志社大学の轡田 竜蔵といいます。
どうぞよろしくお願いいたします!」
―こんにちは! 本日はどうぞよろしくお願いいたします。
「事前にざっとみなさんの探究活動について話は聞いているんだけど、
再度、これまでどんな取組をしてきたのか教えてください。」
―僕たちは、今後初め人口減少していく京丹後市に課題を感じ、
少しでも京丹後市に住む人や関わる人を増やすための解決策を
提案することを目的に活動をしていたのですが、
色々な人のお話を聞く中で、人口減少という問題を
避けては通れないという現実にぶち当たりました。
そこで発想を転換して、どうせ人口減少に歯止めを
かけられないのであれば、
ここに住む人たちの幸福度を上げていく方が、
結果的に持続可能で良いまちに繋がっていくのではないか、
と考えました。
そこでU・Iターンの5名の方にご協力いただき、
京丹後市に関する想いやここで暮らすにあたって
得られる幸福感についての聞き取り調査を行いました。」
「それはすごく面白い視点だね!
そして5人に聞き取り調査をしたの?
大変だったでしょう。
丹後の人は、とても熱い方が多いから頭がパンクするくらい、
毎回情報のシャワーを浴びていたんじゃない?(笑)」
※轡田先生は、ご専門の研究に関わるフィールドワークを
よく丹後で実施されているため、
丹後のキーパーソンについてはよくご存じでいらっしゃいます。
―すごく大変でした(笑)
毎回1時間~長い人で2時間程度、インタビューをしたので
話を聞き終わる頃には、ヘロヘロになっていました。
でも、話を聞くことで僕たちが気づかなかった丹後というまちの姿が
はっきり見えてきて、その過程がとても面白かったです。
「どんな話が出たの?」
―それぞれの方から色々なエピソードを聞いたのですが、
形は違えど共通することが大きく分けて2つ出てきました。
1つは、地元出身・そうでない人関係なく、
想像以上に強い繋がりがあり、
誰かのチャレンジややってみたいことをみんなで応援しよう!
という風土があるということ。
もう一つは、ものを生み出して楽しむ、
つまりクリエイター気質の人が多いということが
分かってきました。
「おお、良いところに気づいたね。
お話しを聞いた5人は、それぞれ異なるタイプのクリエイターだと思うから、
とくに印象に残っているエピソードをもとに丹後の特徴だと
捉えられそうなキーワードをあげていこうか。」
―岡村さんは、「音楽」を皮切りに分野を超えて様々なクリエイターが
集えるスタジオを作りたい、というお話しをされていました。
現に今、外部から訪れる様々なアーティストが
作品の制作期間中に滞在するためのスペースを
自宅の一部を開いて運営されたりしていました。」
「なるほど。岡村さんは所謂"現代のトキワ荘"を作りたいみたいだね。」
―"トキワ荘"って何ですか?
「あ、世代じゃないから知らないか。手塚治虫は知ってる?」
―あぁ、知ってます!「鉄腕アトム」の人だ!
「そうそう。トキワ荘っていうのは、手塚治虫を皮切りに藤子不二雄、
石ノ森章太郎、赤塚不二夫といった著名な漫画家が
居住していたアパートのことだよ。
今も語り継がれる名作がここから沢山生まれたのは、
お互いが刺激や影響を受け合う関係性にあったからだろうね。
新しい移住者の繋がりが豊かで、原住民との関係性も緩く広く
繋がっている丹後だからこそ、色々な分野の人が出入りできる場があれば、
さらに面白いまちになる、と岡村さんは考えられていそうだね。」
―クリエイトしていく、という意味では
「何もないからこそ、0から1にする楽しみがある」と、
お話しを聞いた多くの人が共通して仰っていました。
船戸さんは、ハロウィンパーティーをするために
クラブの代わりにアピアを会場にして企画されたとか(笑)
参加者それぞれが得意なことを持ち寄って、
みんなで披露しあったら本当に面白いパーティーになったと聞きました。
甲斐さんは、外部から訪れるアーティストさんのコーディネートをする中で、
何気ない日常の風景がアーティストの視点を通して見つめ直したときに
ガラッと変わる瞬間が楽しい、と仰っていて。
余白があるからこそ、何にでもなる、そんな可能性を秘めた地域、と
捉えていたところが、新鮮でした。
「いいね。これまでの話から、丹後を表す重要なキーワードとして
"クリエイト(ものづくり)の楽しさ" "余白"というのが出てきたね。
じゃあ、さっきもう一つ挙げてくれていた
"応援してくれる人が多い"ということについても掘り下げていこうか。」
―これは、坂田さんや長瀬さん、船戸さんが仰っていたのですが
とにかく丹後の人々は、誰かの新しい挑戦を応援してくれる、
後押しして支えてくれる人たちが多いとお伺いしました。
船戸さんのアピアでのハロウィンパーティーの話もそうですし、
坂田さんは移住者として丹後に来てから、
丹後内外の人々の交流、コミュニティ形成に挑戦されていますが、
これまで地域になかった新しい、よく分からないものを
地元の人が受け入れて背中を押してくれたから今の自分がある、と
お話しされていました。
長瀬さんも一度地元を出てから、様々なお仕事を経験されたあと
丹後に戻ってくる選択をし、起業をして、
今では「ローカルと世界(グローバル)の交差点」をコンセプトに
全く新しい観光業を展開されていますが、
何度も地元の人たちに助けられたからこそ、
今こうして面白い仕事ができているんだ、と。
これも長瀬さんが教えてくださったのですが、
主に人は3つのタイプ(テイカー、ギバー、マッチャー)に分かれるらしく、
統計的に見て「ギバー(giver)」タイプの人が成功を収めてるようなんです。
「ギバー(giver)」とは「与える人」と訳され、見返りを求めず、
他者に色々なものを与えることに喜びを見いだす人のことらしいです。
どうやら丹後は昔から、「お裾分け文化」が根付いているようで、
「ギバー(giver)」の人の割合が多い地域であると、
お話しを聞いた方々は口を揃えて仰っていました。
長瀬さんは、受け取った恩を次は時代を背負っていく若い世代に送りたい、
そんな想いでお仕事と向き合われていました。
好きな言葉は「恩送り」だそうです。
「おおお、すごいね。これで丹後の全貌が段々見えてきたんじゃない?
丹後の人々は、新たに外から入ってくる文化に対して寛容で、
応援してくれる気質があるということ。
これまでの話もまとめると、「クリエイターのまち」
「作っていく余白のあるまち」「応援・後押しをしてくれる人々が多い」
「施しの文化がある」といった特徴がありそうだね。
昔から職人が多く、"物作り""手仕事"といたものと密接な関係にあった丹後。
そういった環境のせいなのか、自分の手で暮らし・生活を作っていくことを
大事に考えている人が多いような印象を受けます。
このように考えていくと、ものを作り出していく、
所謂、"クリエイティブ・マインド"を一定持つことこそが、
この丹後という地域で暮らすことで得られる「幸せ」の手がかりに
なるかもしれませんね。
今回のヒアリングをしてみて、
自分達の中での新しい発見は何かありましたか?」
――僕たちは、この探究活動をするまでは「丹後には何もない」と
思ってたし、正直、卒業した後、一度ここを出たらもう戻ってくる、
という選択肢は考えていませんでした。
だけど、実際にここに暮らす人々のお話を聞いて、
「何もないからこそ、自分の手で何でも作り出せる可能性で溢れている」と
いうことや、チャレンジを応援してくださる人たちが
沢山いることに気づいて、
もっとこの地域と関わりを持ち続けられる方法を模索したい、と
考えるようになりました。
だけど、きっと僕たちと同じ年代の人たちは、
このことに気づいていないと思います。
丹後って、実は自分達が思っている以上に魅力がある場所なんだよ、と
いうことを伝えるような発表ができたら良いな、と思いました。
「それは素晴らしいね。
今の話を聞いていて、今後の活動の方向性として、
僕から助言できるとしたら、方法自体はいくつかあると思う。
あとは、君たちがどんな風に活動をまとめていきたいのか、
によってやり方を選んでもらう、という感じかな。
例えば、君たちは「人口減少に歯止めをかけるための方法」を
考えるところから、市民一人ひとりの「幸福」について
着目するようになったんだよね。
その「幸福」というのに着目するのであれば、
今我々がこれまでの活動を振り返って、キーワードを挙げていったように、
ヒアリングをしたことをもとに「この地で幸福に暮らすための条件」を
自分達なりに探し出す、ということを目指すのも1つ。
後は、最後に言ってくれていたように
ターゲットを若い世代にするのであれば、
若い世代がこの地域で暮らすにあたって今感じていることの実態を
調査する必要はあるよね。
そのとき、多くはアンケートやヒアリング、という形を取ると思うんだけど、
どう質問をするのかによって、得られるデータの内容が変わってくるから、
自分達が"何を明らかにしたいのか"を明確にする必要がある。
それがはっきり分かっていれば、どんな聞き方をすれば良いかを
考えることが出来るよね。」
―確かにそうですね。
僕たちは、この活動を通して、地域の人々と緩やかに繋がりを持つことが
大切だと思ったので、現状、若い世代の人たちは、
地域にそういった同世代以外の繋がりを持っているのか、ということを
知りたい、というのと、持っている人が少ないという仮説を前提にする場合、
どんな風にしたら、若い世代の人も地域と繋がっていけそうか、
というところを考えたい、と思っています。
「すごく良いね。
例えば、君たちは京丹後市で活躍する
クリエイターたちのお話しを聞くことで、
地域に対するイメージがアップしたんだよね。
ということは、もしかしたら、他の高校生でも自分の身の周りに
ロールモデルとなるような大人の存在があれば、
地域に対する想いはポジティブである可能性が高い、と過程できるよね。
ロールモデルの存在の有無が、その人のまちに対する想いに
どれほど影響を及ぼしているのか、を調べるのであれば
『あなたの周りにロールモデルとなる大人はいますか?』という、
質問をすればいい。」
―おおお、なるほど!
それはすごく面白そうですね。
「そんな風にして、現状の若者はどんなコミュニティを持っているのか、
それはどのような方法で繋がっているのか、
現状まちに対してどんな印象をいだいているのか、
既存の地域コミュニティと関わりを持ちたいと思っているのか、
どうしたらもっと多くの若者が地域コミュニティとの
関わりを持ちたいと思えるのか、
というようなことを問うような質問を検討したら良いと思います。
実は、過去に京丹後市が、市民の幸福度についての
アンケート調査をしており、
その質問事項と結果が、京丹後市のHPに掲載されているので、
そちらも参考にすると良いですよ。」
―すごく参考になります!
そんなものも有ったんですね。早速、調べてみます!!
「rootsに行けば、僕が過去に広島県のとある地方で
若者の意識調査をした時の研究内容がまとまっている本があります。
以前、寄贈させてもらいました(笑)
そこにも、その時に使用した質問用紙を載せているので、
参考にしてもらえるのではないか、と思います。」
―ありがとうございます!
次に僕たちが、やるべきことが見えてきました。
これからのアンケート作成が少し楽しみになってきました。
今日、聞かせて頂いたお話しを参考に、質問事項をみんなで練ってみます。
「少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
最終報告会は、直接聞きに伺う予定なので、発表を楽しみにしていますね!」
―何と! ちょっと緊張してきました......(苦笑)
良い発表が出来るように頑張ります。
****
〈コーディネーターより〉
このグループは、ヒアリング調査をするにあたって、
できる限りヒアリング対象者が活動するフィールドに出向き、
そして毎回1時間~2時間たっぷりと情報のシャワーを浴びて、
いつも頭がパンクしそうになりながら岐路につく、
という活動をしていました。
この膨大な情報をどのように整理するのか、というよりも
本当に纏めきることができるのか私も心配していたのですが、
轡田先生の問いかけによって、彼らが話しを聞いた中で
どんなことが印象に残っていたのか、そこから何を感じて、
丹後に対してどんなイメージを抱いたのか、ということが
みるみるうちに整理されていき、そのたびに彼らの表情も
すっきりしていくのが分かり、側で見守っていた私自身、
とても爽快な気分になりました!
面白かったのは、あれだけ沢山の人たちから様々なエピソードを聞いた中で、
高校生たちがどのエピソードがとくに興味深かったのか、という視点を知れたこと。
「そのお話しが、一番印象に残っているんだ!」
という新鮮な気づきがあり、聞いていてとても面白かったです。
轡田先生と彼らのやりとりを見ていて改めて気づいたことがあります。
それは、振り返る際の「問いかけのフレーズ」が
いかに重要な役割をしているのか、
ということについてです。
私も毎回、ヒアリング後に彼らとともに振り返りをしていましたが、
今回轡田先生にさらに深いところまで掘っていただいたお陰で、
乱雑していた情報が一本化されたことに加えて、
彼らがこれまでヒアリングしたエピソードをもとに自分達の言葉で、
「丹後というまちが持つポテンシャル」について
変換していく作業ができました。
どのような問いかけをしてあげれば、ベストなのか。
何を明らかにすれば、次のステップへ踏み切ることができるのか、
彼ら自身が現状を把握し、次に何をすべきなのか自分達で理解するためには、
今どんな問いを投げかけてあげたら良いのか。
轡田先生を前にした彼らの様子を見ていると、
その表情の変化から「学びスイッチ」が入った事が分かりました。
轡田先生の前では、構えを解いて武装解除ができるという安全性を
彼らが自然に感じ取ったのだと思います。
そこからは、「学び」のモードが入った彼らはどんどん吸収していくのみ。
彼らが今行っている、その行為そのものに
「学び」の本質が集約されていると感じました。
「学び」というのは、師から教えられたことを、自分なりに受け止め、
かみ砕き、整えて、付け加えるものがあれば付け加えて、
次の代に「繋ぐ」ということです。
自分達のこれまでの活動が、最終的にどこに行き着くのか、
よく分からないまま、何とか道なき道を歩んできた状態から、
轡田先生という先導者に出会って、
目の前が開けた、目指すべきところが見えた、
そんな時間になったと思います。
「僕たちが知った丹後というまちの姿を
同世代や後輩達にも伝えるような発表にしたい」
最後に彼らがそう宣言してくれたことが、
何よりもこれまでの「学び」を体現してくれたのだと、
これまでの彼らの長い活動が走馬灯のように蘇り、
感慨深い感情が溢れてきました。
「こうしたらいいんじゃない?」と言ってあげることは簡単です。
活動が行き詰まった時に生徒よりも経験を積んでいる大人から見れば、
「こうすればもっと良いのにな」とか
「こうした方が効率が良いのに」というようなことも
見えてしまうこともあります。
だけど、それは大人から見た「正解」であり、
彼らの「正解」ではありません。
彼ら自身が自分たちで気づく、自分達が何をしたいのか、
を明確にすること、
その上で何が自分達の「正解」なのかを見いだしていく、
見守る側はこの過程を大切にしながら、
彼ら自身が自分たちのゴールに向かって足を進められるように
促していく姿勢や忍耐強さが必要になります。
ですが、この作業が実に難しい。
「問い」の練習は、大人側も日々鍛錬する努力をしていかねばならない、と
実感する時間となったのでした。