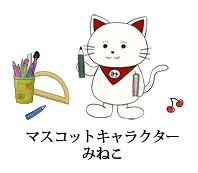学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 【京丹後市民の幸福度~この地域で...
【京丹後市民の幸福度~この地域で生きていくということ、そしてそこから見える可能性~〈坂田真慶さんへヒアリング〉vol.3
京丹後市民の幸福度について調査をしている高校生たちの活動はまだまだ続きます。
今回は、丹後暮らし探求舎の坂田真慶さんにお話しを伺います。
坂田さんは2017年に京丹後市に移住をし、
丹後で生活する人たちが楽しく暮らし、働けるように
様々な形で伴走支援を行なわれています。
最近は、地域と関係人口をつなげる「まちまち案内所」の
運営や地域での場作りが主な仕事。
町歩きと温泉に入ることが趣味という、
どっぷりローカルに浸かった坂田さんから、
どんなお話しが聞けるのでしょうか。
※これまでの記事は以下からチェックしてみてください。
****
――これから坂田さん自身のこの地域で暮らすにあたって感じている
"幸福感"について聞いていきたいのですが、
その前に経歴を教えていただいても良いですか。
実は僕たち、ここに来る前に坂田さんのプロフィールに
目を通してきたのですが、
情報量が多すぎてちょっと混乱しています......(笑)
一時は海外での生活のご経験もあるようですが。
そうですね。色々なところに住みました(笑)
僕は東京都荒川区の下町で生まれ育ちました。
コミュニケーションが多く生まれる下町で育ったからか、
昔から人との関わりとか
ローカルな部分に深く潜り込んでいくことが好きで。
国際関係に目を向けるようになったのは、15歳くらいの頃かな。
当時は国際連合に入って、世界の様々な問題を
解決出来るような人になることが夢でしたね。
でも大学で国際関係とか国際政治を学んでみると、
僕のやりたいことと国際連合などがやっていることに
大きなギャップがあることに気がついて......。
僕は自分の手の届く範囲の中で起こっている社会課題や地域課題に
向き合いたかったのですが、国連の組織はやはり官僚世界。
見ているところが違ったんですよね。
それでどうしよう、ってなって20代は進路迷子でした。
途中で中国やインドネシアでの生活も経て、
紆余曲折ありながらもひょんなことから京丹後市と繋がって。
何だか分からないけど、この地域であれば色々とチャレンジできて面白そうだ、と
思って気がつけば移住していました(笑)
――いや、本当に面白いですね。
海外にも出て、でも結局丹後に留まっちゃったという(笑)
本当に人生何があるか分からないよ(笑)
――でもそれだけ丹後には魅力を感じられた、ということでしょうか。
そうだね。今でこそ、徐々に丹後の中で地元民や移住者が集って
何か一緒にやったり、面白い活動をしている人が増えてきたけど、
僕がここに来た5年前くらいはまだ地域活動があまり活発でなかったり、
独自で動いている人もいたけど地域全体でその繋がりはよく見えなかった。
目立った動きが無かったからこそ、新しい挑戦ができる余地だったり、
地域のポテンシャルを感じてここに移住することに決めました。
それで色々してたら、もう5年が経つんだね......。
あっという間だわぁ。
――特に縁のない場所で、全く新しいことを始めようとするのは
結構勇気のいることだと思うのですが、ご不安などはなかったんですか。
そんなに感じなかったね(笑)
やっぱりそこは下町育ちだからか、ローカルに入り込んでいく、
ということ自体がすごく面白くて。
地元の人たちと時間をかけてコミュニケーションを取りながら
関係性を作っていく。
そうしているうちにいつの間にか地域に溶け込んでいる。
関係性がしっかりできていると、何か新しいことに取り組みたい時でも
協力してくれる人が出てくる。
地域との相性も良かったんだろうね。
――なるほど。
では丹後の好きなところを教えてもらってもいいですか?
やっぱり、老若男女関係なく繋がれるところかな。
外から来た者に対してもすごく寛容で受け入れてくれる人が多いと感じますね。
――丹後に寛容な人が多い、という話はこれまで別の方へのヒアリングでも
出てきました。
それはなぜだと思われますか?
でもこうして地元の人や移住者関係なく色々出来るようになったのは、
ここ5年くらいの間かな。
過去にはそんなに雰囲気が良くない時代もあったと聞きます。
特に丹後は地場産業としてちりめんで経済を盛り上げてきた背景があって、
それが段々廃れてきてからは地域全体が低迷してしまって。
それでもここ10年くらいの間に移住者、
またUターンで戻ってきた20代、30代の若手中心に少しずつ地域を盛り上げよう、
という動きが出てきたように感じます。
それが今になって見える化されてきた。
点であったのがそれぞれ結びついて線になっていく感じ。
それをさらに強化(面に)するために地元民も巻き込んでみんなで何とかしよう、
と動き出したのが最近だね。
――なるほど。そうだったんですね。
では丹後にあったらいいな、と思うことは何でしょうか。
やっぱり映画館などの文化的施設は欲しいかな、と思うね。
あとは"良い仕事"かな。
丹後は雰囲気は令和だけど、仕事環境としては昭和だと思うのね。
恐らく進学等で、高校を卒業したら大部分の若者が一度はここを出ると思う。
でもこれから人生を過ごしていく中で、
例えば子どもができたタイミングで子育ては
のびのび出来そうな丹後でしたいな、とか
家庭の事情などでやむを得ずこちらに戻って
来なければならない時があるかもしれない。
そうなった時に良い職場、良い仕事が見つからない、となると
やっぱり魅力は半減しちゃうよね。
あとはせっかく面白いことをやっていてもそれを継ぐ人が出てこなかったら、
なくなってしまうこともあるかもしれないよね。
継続できるシステムみたいなものはどこかのタイミングで
構築しなきゃいけないのかな、って考えたりはしています。
――確かに。
魅力的な仕事ができそう、何だか面白そうなことが起こっていると分かれば
ワクワクしながら地元に帰って来れそうです!
因みに今の段階で、将来的に丹後に戻ってきたいな、という考えはあるの??
――あ、とりあえずまず進学を考えているので丹後から出ることは確実なのですが、
戻ってくるかどうかはまだ分かりません(笑)
そうなんや(笑)
でも一回外の世界に出ることは、必要でとても大切なことだと思います。
外に出ることで初めてじっくり自分の地元のことが理解できると思います。
他の地と比較することによって、
丹後のこんなところが良いな、好きだな、とか
こういうところは足りてないな......とか。
色んな世界を見て、視野と選択肢を広げてください!
――ありがとうございます。頑張ります!!
では、この地域で暮らしていて坂田さんが幸せだと感じるのはどんな時ですか?
まずは食べ物とお酒が楽しめて、温泉があることかな。
あとは最近町歩き(散歩)が好きなんだけど、
町を歩く度に何か新しい発見があるところが面白いよね。
程よい余白と可能性を感じるのもこの地域の魅力だと思います。
先ほども話したように一時は、この地域も暗い時代があって、
可能性がないな、何もないな、と思われていました。
だけど今は、色んな分野の人たちがその枠組を取っ払って繋がれるようになって、
アイデア一つで可能性が広がっていく感覚を実感値として
味わえるようになってきた。
どういう繋がり方をすればもっと面白くなるかな、と
考える余白があるところもこの地域で暮らす楽しさだと思っています。
――僕たちは、この地域に住んでいて正直何もないところだと思いながら
この探究を始めたのですが、今まで色々な人にお話を聞いてきて、
ここで今すごくワクワクするようなことが起こっているんだと気づきました。
そうやって地域を面白くするぞ、と動いている人たちの存在は
未来を明るくしてくれているように感じます。
もちろん、地域に「余地がある」ということは
まだまだ足りていない部分もあるということで。
でも見方を変えれば、それはこれからどんなものにでも変容できるという
ポジティブな捉え方が出来ると思います。
多様な人たちが集って、アイデアを出し合って面白いものが生み出されていく......
こういう場を地域に設計していくことが大事だと思います。
こういう環境がある地域は、
「幸せ」という一つの条件が満たされていることになるのかもね。
――なるほど。とても興味深いです!
では、坂田さんの今後の展望をお伺いしてもよろしいですか?
やっぱり僕は「場を作る」ことが好きで。
全然異なる分野の人たちがアイデアを出し合って出てくるものを
形にしていく過程に面白さを感じています。
普通に暮らしていたら出会わなかったような人たちが出会える「場」を
地域に設けておくこと。
面白い出会いが偶発的に生まれるような環境を設計し、関係を繋いでいくこと。
そして何かチャレンジしたい、一歩踏み出したい、と考えている人たちを
寛容に受け入れ、応援できる環境を整えること。
そういうまちづくりをこれからもしていきたいと考えています。
そのためにもともと長く丹後で暮らしている人たちのコミュニティ、
受け皿となる地域側を温めておく必要があると考えています。
色々な人たちとより良い未来を作っていくための
「共デザイン」を実現していきたいですね!
****
坂田さん、素敵なお話をお聞かせいただきありがとうございました。
地域の暮らしを全力で楽しむ坂田さんのお話は、
高校生たちにとってもとても刺激あるものとして伝わったと思います。
「丹後で暮らすこと」でどんな幸せを感じるのか。
未来の丹後はどういう姿になっているのか......。
「課題」を深刻なものと捉えず、
どうすればもっと面白くなるのかを考える坂田さんの考え方は、
高校生たちが人生をより面白く、豊かに生きるのにとても役に立ちそうです。
この調査が最終的にどのようなゴールを迎えるのかはまだ分かりませんが、
楽しみに見守ってきたいと思います。