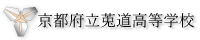学校生活
先日、乳脂肪分の高い乳製品(生クリームが適している)を遠心分離して、乳脂肪を取り出す実験を行いました。適当な遠心分離機がなかったので、今回は人力で分離していきます。乳製品を容器に入れ、ひたすら振り続けました。やがて乳脂肪分どうしがくっついて水分と分離していき、乳脂肪の塊となっていきました。この塊は一般的にバターとも呼ばれています。
動物性の油脂は常温では固体ですが、少しの加熱で融解し、液体になっていきます。今回分離した乳脂肪にも同様の性質があることを確かめるため、加熱実験をしてみました。加熱するのに適当なものを探したところ、科学部の畑より収穫したジャガイモがあったので、ジャガイモを茹でて加熱し、そこに分離した乳脂肪の塊を置くことで、どのような変化が見られるかを確認してみました。その結果、茹でたジャガイモの熱によって乳脂肪の塊が融解し、北海道などの地域で「じゃがバター」と呼ばれる状態になりました。有意義な実験結果が出たことで、部員達はみんな喜んでいました。




※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
みなさんは鳥の標本を見たことがありますか?科学部では現在、鳥好きの部員がヒヨドリとキジバトの剥製作りを行っています。冷凍していた鳥(学校内で事故死していたもの)を解剖して臓器などを取り出して乾燥させた後、空っぽになった鳥の中身にタコ糸を巻きつけた金属の棒を入れて、鳥の体にまるで生きているような立体感を与えていきます。鳥の剥製作りは慎重かつ注意深く行わないとたちまち失敗してしまう、なかなかに難しい作業です。完成まで気が抜けませんね。


哺乳類は恒温動物なので、クマ類やコウモリ類など冬眠(冬ごもり)をする一部の種類を除いて、冬場でも普通に活動しています。よって、センサーカメラでしっかり撮影されるわけですが、寒さにより活性が低下しているのか、撮影数は少なくなる傾向にあります。
そんな中でも多いのはやはりニホンジカで、今回回収したデータでも、ニホンジカがたくさん撮影されていました。今回は雌ジカばかりが写っていたのですが、グループになって行動している様子が確認できるものが多かったです。ニホンジカの行動は雌雄で異なり、繁殖期ではないときは、雄ジカは単独生活していることが多いです。それに対して、雌ジカはグループになって行動しています。学校林にもそんな雌ジカのグループがよくやってきます。
今回はそれだけでなく、カメラの前で長時間くつろいでいるグループも撮影されました。カメラが作動するときはLEDライトが発光するので、カメラの前にいたらずっとライトで照らされているはずなのですが、ふてぶてしくも休息モードに入っているようでした。ライトに対するシカの反応性はかなり個体差があるように思います。多くは照らされたらすぐに逃げるのですが、中にはまったく気にしていない個体もいて、実に面白いものです。








※この記事は科学部の部長による活動報告です。
皆さん、こんにちは、部長です。
冬野菜がますます美味しい季節になってきましたね。科学部は学校の中庭の一角に畑を作ってサツマイモやジャガイモ、トウモロコシなどの様々な作物を作っています。先日の部活では秋に植えたジャガイモの収穫をしました。これは、去年サツマイモを収穫した後の畑を耕して、3年生の先輩が実験に使って残っていたジャガイモを植えたものです。
冬はなかなか畑仕事ができませんが、こういう機会で作業ができるのは畑好きとしては嬉しい限りでございました。


10月の終わりにサツマイモを収穫した後、畑の一部にジャガイモを植えました。植える時期が少し遅かったこともあって、上手く育つか不安だったのですが、元気な葉をつけて、立派に成長してくれました。
最近の寒波で葉も枯れてきたし、とりあえず収穫してみることにしました。土を掘ってみると、小ぶりですがちゃんとイモができていました。一畝しか植えなかったので収穫量は少ないのですが、このジャガイモをどう利用していくか、今から楽しみです。




※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
みなさんは動物の骨がどのようになっているかすぐに想像できますか?科学部ではとある部員が、ウシガエルの骨格標本の製作を行なっています。4年前に捕獲され、冷凍されていたウシガエルを鍋で煮て、骨を取り出し、現在骨の仕分けをおこなっています。ピンセットを使い、細かな骨も見逃さずに仕分けていく作業はなかなかに骨が折れる作業ですが、完成が楽しみですね。
「科学部部長のひとりごと」はこのたび第15回を迎えることができました。始めてからまだ半年も過ぎていないのに、自分でもここまで多くの記事が書けると思っていませんでした。読んでくださっている皆様に、この場を借りて厚く御礼感謝申し上げます。そしてこれからも「科学部部長のひとりごと」をどうぞよろしくお願いします。


※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
みなさんは米は年に一度しか取れないと思っていませんか?実は2回とれるんです。科学部では秋に稲を刈り取った後、刈り取った後に残った茎をそのままにしておき、もう一度稲を育て、このほど収穫しました。二度目の収穫となった稲は緑色で、中身に実が入っていなかったり、水が入っていたりと結果的には失敗に終わってしまいました。しかし、「これってこうしてみたらどうなんだろう?」と考えて、実行したことはなかなかに興味深く、また面白いことでした。


年が明けて2025年になり、3学期が始まりました。学校林では冬休み期間もセンサーカメラが動物を狙っていました。データを回収したところ、やはり冬になって寒いのか、撮影数は秋より確実に少なくなっていました。
そんな中、今回はテンの写真がいつもより多めに撮影されました。テンはあまり有名な動物ではありませんが、里山ならどこにでもいるようなイタチの仲間です。ふつうのイタチ(ニホンイタチ、チョウセンイタチ)が河川の近くなどの水場でよく見られるのに比べ、テンは森林でよく見られます。よって、学校林ではイタチよりもテンの方が多く撮影されますね。
テンの体色は季節による変化や個体差が大きく、黄色っぽいもの、茶色っぽいもの、顔も黒くなったり、白くなったり、実に多様です。ふさふさの毛皮は高級品であり、さわり心地が最高で、首巻きに使われたりするみたいです。
日本にいるイタチの仲間にはアナグマもいます。アナグマは学校林でもよく見られますが、冬ごもりをするのため、春から秋にしか撮影されません。ところが、最近は12月になっても撮影されており、今回はついに年末に撮影されました。アナグマは冬ごもり中でも、暖かい日には外に出て水を飲んだりします。このまま温暖化が進むと、冬でも見られる動物になっていくかも知れませんね。








※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
新学期も始まり、皆様いかがお過ごしでしょうか?科学部でも新年度の活動を始め、最初の活動日では、学校の裏山に入って去年設置したセンサーカメラの回収を行いました。今年はいったいどのような動物が見られるでしょうか?楽しみですね。
※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。あけましておめでとうございます。
今回は科学部の活動について紹介したいと思います。
<今年度の活動>
○学校の裏山にセンサーカメラを仕掛けて動物調査
○学校の裏山で野鳥の鳴き声調査
○畑や田んぼを作って作物の栽培(イネ、サツマイモ、トウモロコシ、ジャガイモ)
○宇治川を中心とした魚類調査
○アクトパル宇治で夏休み合宿
○京都府高等学校総合文化祭(自然科学部門)での研究発表
○莵道祭での展示発表、レジン作り体験、演示実験
○骨格標本作り(シカ頭骨、ウシガエル)
○野鳥の剥製作り(キジバト、ヒヨドリ)
○施設見学(宇治市植物公園、京都大学総合博物館)
○発酵の実験、酵素の実験、浸透圧の実験、葉脈標本作り
○中学生部活動体験
○やましろ未来っ子サイエンスラリーのアシスタント
2024年は私のみならず、多くの部員にとって科学部で様々なことに挑戦し、部活としても新しいことに取り組むことができた非常に有意義な1年間でした。2025年も科学部での色々な活動をゆるーくお伝えして行けたら良いなと思っておりますのでお楽しみに。
それではみなさん、今年もよろしくお願いします。
2学期の期末考査の期間中もずっと学校林で動物を狙っていたセンサーカメラのデータを回収してきました。設置場所を変えてから2回目のデータ回収なので、どんな動物が撮影されているか楽しみにしながら記録していきました。
その結果、水場の前に仕掛けているカメラで、またもムササビが撮影されました。一緒に撮影されている動画を見る限り、やはり水を飲みに来ているようですね。なお、今回は同じ場所でニホンリスが撮影されています。ムササビとニホンリスは、どちらもネズミ目(齧歯目)リス科の動物で、同じグループに分類されます。シルエット(姿・形)も似ており、パッと見るだけだと間違えてしまうこともあります。ただ、大きさはムササビの方が上ですし、何よりムササビは夜行性でニホンリスは昼行性と、活動時間が違います。体の大きさや撮影時間に注目することも、写真から動物を同定するためには必要なことです。







9月に刈り取ったイネは、10月から11月にかけて脱穀・精米され、何とか白米の状態にまで持ってくることができました。もっとも、手作業による脱穀なので、精米機のようにはきれいにできず、ほとんど玄米に近い感じでしたけど。夏休みに水の管理が上手くできなかった影響なのか、粒の大きさもあまり大きくなりませんでした。
そして2学期終業式の放課後、調理室を借りて、この精米を実際に炊いて、お米としてのはたらきを確認する実験が行われました。引退した3年生達も、これは気になると集まってきました。
まずは精米の量を確認すると、およそ6~7合くらいでした。最初は2合もできれば上出来と考えていたのですが、想像以上の収穫量になりました。このうち5合分を水で研ぎます。糠がたくさん残っていたので何度も研ぎ直しましたが、ほどほどのところで炊飯器に入れ、炊き上げます。結果として、お米として十分なはたらきを確認することができました。
何もかも手探りの状態で始めた科学部の米作りですが、さまざまな失敗と試行錯誤を経て、目標であった「部員1人あたり1個のおにぎりがつくれるだけの米を作る」ことを達成できました。普通科の高校で米作りをすることはあまりないので、部員にとって貴重な経験になったと思います。







※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
みなさんは植物にも動物のように標本があるのをご存知ですか? 科学部では、「葉脈標本」と呼ばれる植物の標本の作成を行いました。学校の裏山で拾い集めたヒイラギやサカキなどの植物の葉を水酸化ナトリウムで煮て柔らかくし、歯ブラシを使って葉肉の部分を取り除き、乾かすと「葉脈標本」が出来上がります。植物によって作ることが難しかったり、葉脈だけを見ることによって、普段葉を見るだけでは見つけることが難しい発見をすることができます。楽しいですね。


※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
最近、シマエナガがブームとなっていますが、みなさんは鳥はお好きですか? 科学部ではとある鳥好きの部員の考案で、学校の裏山にやってくる鳥の鳴き声の調査を始めました。ボイスレコーダーを用いて、裏山に入って鳥の鳴き声の録音を行い、どのような鳥が鳴いているのかを調べます。これまで取り組んだことのない調査でまだまだ手探りの状況ですが、何か面白いことが分かれば、ここで報告できたら良いなと思っています。お楽しみに。
なんやかんやで「科学部部長のひとりごと」はこの度、第10回を迎えることができました。部長といたしましては、科学部の魅力や活動をできる限りお届けしていきたいと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。


※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、そしてお久しぶりです。部長です。
科学部では学校の裏山にカメラを仕掛けて、裏山にやってくる動物を調べています。期末テスト明けからは、裏山の新しい場所に仕掛けたカメラの回収を行い、いつどのような動物が何回撮影されたのかを調べています。この調査が科学部で裏山にやってくる動物の調査を行う上での基本中の基本の調査になるので、気が抜けません。
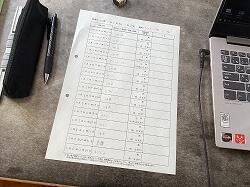

現在、科学部の備品として3台のセンサーカメラがあります。2021年10月から2024年9月の3年間にわたって、これらのカメラを学校林の特定の3ヶ所に設置し、ずっと同じ場所で撮影を続ける定点調査を行ってきました。3年分の撮影データは、場所の違いによる撮影される動物の違いや、倒木の有無と哺乳類の関係性など、さまざまな研究に活用することができました。
これらのカメラを3年ぶりに回収してメンテナンスした後、1台は前から設置していた水場に、2台はこれまでと別の場所に設置しました。そんなデータを回収すると、今年もムササビが撮影されていました。ムササビは2021年から今の季節にだけ撮影されるようになった動物です。今年も来てくれたっていう感じですね。カメラを地上に設置している関係上、滑空している姿が撮影されていないことだけが残念です。いきなりムササビが撮影されるとは、センサーカメラ調査の再スタートとして、非常によい形になったと思います。








※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
最近の部活では収穫した稲の精米を行っていました。精米機を使うのではなく、瓶にもみすりを終えた玄米を入れ、木の棒でひたすら突いて茶色い玄米を白米にしていきます。完全に白くするのは難しいのですが、スーパーで売られている様なお米に限りなく近い白色を目指して、ひたすら腕を動かし、ようやく全ての精米が完了しました。感慨深いですね。

※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
先日、「科学部冬遠足」と題して京都市にある京都大学総合博物館に出かけました。歴史や自然科学に関する展示を見た後、バックヤードの見学に参加しました。普段は入れないバックヤードでは、魚類をはじめとする様々な動物のホルマリン漬けや骨格標本を見ることができました。オオサンショウウオやリュウグウノツカイのホルマリン漬けに実際に触れる貴重な体験ができました。
科学部では学校の外でも様々な活動を行っています。学校の中だけにとどまらない科学部の活動にこれからもご期待ください。
※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
科学部では、毎年畑を作って、様々な作物を育てています。今年はサツマイモとトウモロコシを作りました。そして現在、ジャガイモとタマネギの栽培を始めました。どちらも来年春の収穫を予定しています。まだまだ収穫するまで時間がかかり、タマネギに至ってはまだ苗を作っている状態ですが、来年に向けてまた一つ楽しみが増えました。
※この記事は科学部の部長による活動報告です。
みなさん、こんにちは、部長です。
科学部には発酵実験専用の機械があります。先日これを使って発酵に関する実験を行いました。強力粉や乾燥した酵母菌(イースト菌)、スキムミルクなどを機械に入れて加熱します。2時間余りかかってようやく加熱が終わると、とてもふわふわとした焼き上がりになりました。今後はイースト菌を使わずに同様の実験をしたいと思っています。結果がどうなるかわからないだけに今からワクワクが止まりませんね。
なんやかんやで「科学部部長のひとりごと」も第5回を迎える事ができました。ご覧頂いている皆様にこの場をお借りして厚く御礼感謝申し上げます。
Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.