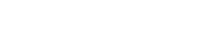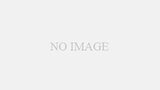5年生への障害理解教育の講師派遣依頼をいただき、盲学校での学習内容や方法を伝えたり、「見える」ということ、「見えない」ということについて一緒に考えたりしました。
【写真】視覚の役割や点字ブロック等の説明を聞いている様子

盲学校は教科学習に加えて点字や歩行の学習をしていること、見えにくさにも色々あるということ、視覚障害者スポーツなどについて話しました。また、「色はどうやってわかるの?」「洋服の組み合わせはどうしているの?」「スマホは使えるの?」「買い物はどうやってしているの?」など、子どもたちからの質問に本校理療科の全盲の教員が回答しました。見えないことで不便なことはありますが、ユニバーサルデザインの普及で障害のある人もない人も暮らしやすくなってきているということ、工夫することで生活しやすくなることがあるということを伝えました。また、点字教科書や拡大教科書、単眼鏡やルーペなどの視覚補助具にも実際に触れてもらいました。
アイマスクをしての折り紙体験では、見える時と見えない時で角を合わせて折る時に何を頼りに折るのか、折る時にどういった情報が必要なのか等を一つ一つ確認しながら進めました。
【写真】アイマスクをして折り紙に挑戦している様子

歩行体験では、アイマスクをして見えない状態で歩く、白杖を使って点字ブロックを頼りに歩く、手引きを受けて歩くことを体験し、違いを確かめました。見えない時には視覚以外の聴覚、触覚等からの情報がより重要になることが実感できたと思います。それぞれの体験後、手引きや白杖、点字ブロックがあることで安心感につながるということ、困っている人がいたら声をかけてみよう等、児童から多くの意見がでました。
見える人も見えない人も、みんなにとって過ごしやすい世の中になりますように。
【写真】アイマスクをしての白杖歩行体験の様子