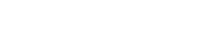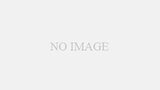今年の夏は暑く長かったので、誰もがひどく体力を消耗したのではないでしょうか。涼しくなったのを喜ぶのもつかの間、急な気候変化に調子を崩し、咳をしている人が増えています。実は東洋医学にはこういった変化に対応する知恵がたくさん含まれています。
本校の理療科生が東洋医学の授業で必ず勉強する内容に「五行色体表(ごぎょうしきたいひょう)」というものがあります。世界をつくる要素を木火土金水の五つと考え、それぞれに当たる臓腑や季節、気候要因、色など、様々な要素を表にしたものです。
これによると、金に当たるのは、肺・秋・燥・白。秋は乾燥するため、肺(呼吸器)を痛めやすく、白いものを摂るのが良いというのですが、薬膳の考えで白い食べ物には潤いを与える作用があるということになっており、ちょうどこれに合致します。
では実際に、喉や肺を乾燥から守り、潤いを保つのに良い飲み物、食べ物として、どんなものが考えられるでしょうか。
先ずは飲み物。温めた牛乳や豆乳にはちみつ(はちみつにも潤いを保つ効果があります)を加える。牛乳のカルシウムは精神安定作用もありますから就寝前に飲むのが効果的です。ただし、はちみつは一歳以下の子供には与えないでください。お茶類、ウーロン茶、緑茶、紅茶、もらったけれど何となく飲まずにいる健康茶などに、乾燥したクコ(クコは白くはありませんが潤いを保つ効果があります)やナツメを加える(ナツメは乾燥に効くものではありませんが、疲れて食欲がおちている体を元気にします)。お茶には少し甘みが加わり、味変にも使えます。また、ガラスポットで出すと見た目にきれいです。慣れない飲み物はちょっと、という方は、紅茶をレモンティーにしてはちみつを加えれば酸甘化陰(さんかんかいん=酸っぱいものと甘いものを合わせると潤いが保持しやすくなる)で効果的です。同じ理屈ではちみつレモンも良いでしょう。
次に食べ物(料理)。簡単にできるのは、湯豆腐に白ごまを振ったり、たれに練りごまを加えたりする。豆腐や大根のスープ。材料がこれだけでは味気ないので、皮付きの鶏肉を入れれば、肌の乾燥にも効果があります。もちろん、豆乳鍋やミルクスープにしても良いですし、更にクコを浮かべればエスニック感が出ておしゃれです。
東洋医学、「医学」だといって難しく考えず、楽しく生活に取り込んでいきたいものです。
理療科では、視覚に障害のある方で就労にお困りの方の入学相談を随時募集しています。お気軽にご相談ください。
【相談先】
京都府立盲学校 花ノ坊校地
TEL:075-462-5083(担当 教務部)