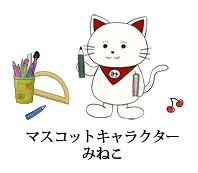学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 「継承」って何だろう?考え続けた...
「継承」って何だろう?考え続けた1年間の旅路~vol.2
前回の記事で紹介した2年生の伝統継承チームの
その後の活動について。
(前回の記事はこちらをご覧ください!)
*****
「丹後の伝統を次世代にも継承していきたい!」
そんな想いで始まった彼女たちの探究。
「継承する」とは一体どういうことを示すのか、
定義づけするところからこの旅は始まった。
「私達が考える"継承"とは、伝統をできる限り
そのままの状態で保存し、次に受け渡すことだと思っています」
彼女達の考えでは、「継承すること」は
守るべきもの、形を変えずできる限り過去の人の想いを
そのまま未来へ繋げる、というものだった。
それが、Kaicoのワークショップで出会った甲斐さんのお話や
提灯屋の小嶋さんとの対話がきっかけで、「継承すること」の
定義が揺らいでいく。
自分たちはどこに向かっているのか、
果たして向かう先にはどんなことが待ち受けているのか、
不透明のまま、それでも前に進まなければならず、
模索しながら歩みを進める。
この過程が如何にも「探究」であり、
彼女を見ていると私の中の「探究欲」も湧いてくる。
ぜひ最後にみんながどんな景色を見るのか、一緒に
見届けたくなったのである。
彼女達は、甲斐さんや小嶋さんと話したことで、
「継承」とは決して"そのままの状態を守る"必要はないと
考えに変化が生じるとともに今現在、伝統に携わる人々の
想いを伝えることを何かしらの形で成し遂げたいと決意する。
ではそれを誰に伝えるか。
伝えたい人を具体的にイメージしていく。
「やっぱり、自分たちと同じ年代くらいの若い人にも
関心を持ってもらいたいよね」
「観光客の人に知ってもらうのもいいんだけど、
どちらかというと地元の人が地元の伝統の魅力に気づいたり、
地域に"新しい伝統継承の在り方"を考え広めようとしている人が
いるんだってことを知ってもらえるようなものがいいよね」
そんな風な話し合いの末に彼女達は、自分たちが出会った人や
実際に足を運んだ場所で感じたことを伝える為のパンフレットを
作ろうという考えに至る。
「パンフレットの表紙は、できればちりめんを使いたいよね。
手に取ってくれる人が実際に触れられるものにしたい」
そんなアイディアも出てきて、
すでにパンフレットの出来上がりが楽しみになる。
ちりめんといえば、このチームの中の一人が
着物好きで元々伝統継承について探究をしようと決めたのも
それが理由であったという。
彼女の祖父は機屋を営んでおり、幼い時から美しい着物が
身近にあって物心ついたころには自然と好きになっていたそうだ。
「着物バザーなんかにもよく行くのですが、
そういった企画をよく請け負っている機関が
"丹後織物工業組合"さんなんですよね。
機屋さんのとりまとめ役のようなことをされていたりするのかな、
と思うんですけど、ここに見学に行くことはできますか?」
高校生自らがこうして情報を集め、自分の意志で
ここに行きたい!と選べるのはとても喜ばしいことである。
早速工業組合さんにアポイントをとって
見学に行くことに。
見学は工業組合さんの組織や
どういった役割を担う施設であるのかについての説明、
また丹後ちりめんの歴史の変遷について話を聞くことから始まった。
工業組合さんの主なサービスの1つは「加工」作業を
担っていること。
各機屋さんから織り上がってきた絹織物などの繊維に
含まれる不純物を取り除いてシルク本来の美しさと
光沢を発揮させるための加工だ。
また薬品メーカーや研究機関等、様々な組織との連携をはかっているため、
生地加工や研究開発が可能な体制となっている。
生地の製造は丹後に広がるそれぞれの機屋さん、
そして精錬・加工・染色は工業組合さんが担う、といったように
産地内で全てが完結するワンストップ生産体制が整っていることが
丹後ちりめんのブランド化に一躍買っている。
また実際に丹後地域にある機屋さんで織られる生地の
特徴を実際に商品を見たり、触ったりしながら学ぶ。
「この生地は貝殻が織り込まれていて、見る角度よって
違って見えるんですよ!」
と担当の方が見せてくれた生地は大層美しく、高校生たちも
その技法に魅了されているようだった。
「中々着物など着られなくなった今、新しい取り組みなどは
されているのですか?」
「現在は化粧ポーチや財布、鞄、パジャマやマスクなど
時代に合わせて手に取りやすい商品が様々生まれていますね。
インテリアとして洒落た空間演出なんかに使われることもあり、
最近では海外でも展示会を行ったりして、人気がありますよ!」
伝統産業の分野は変化が少ないと思われがちだが、
長い歴史を紡ぐ中で守るべき箇所は押さえながら、
常に柔軟に変化してきたことが伺える。
そしていよいよ工場見学へ!
見せていただいたのは、生地の入荷から出荷に至るまでの
一連の作業場の様子。
最初に目にしたのは、各メーカーさんから
織り上がった大量の布!!
この大量の布にメーカーの要望に合わせた加工を加えていく。
汚れ落とし、精錬加工(不純物を落として絹本来の美しさを出す加工)、
生地加工...。
驚くべきは、その加工作業に人の力が大いに働いているということ。
勿論加工には優れた機械を使用する。
だが、汚れが本当に綺麗に落ちているのか、
生地の長さが正確であるのかの確認作業は目視と手作業である。
特に織物には水が欠かせないが、天候や季節によって
室内の湿気の度合いも変化するため、微妙な調整が常に必要な
繊細な仕事であるが、それも勿論人の五感が頼り。
熟練された技術を持つ職人が時間をかけて1つ1つの織物と向き合っているのだ。
「ここは精錬加工をする場所です。
この作業を一手に引き受けるここ、織物工業組合では
工場から70メートルほど西にある竹野川から水を汲み上げて、
利用しています。この川の水は軟水で量も豊富。
この水をさらに良質なものに加工することで、しなやかで
柔らかい風合いのシルクになります。
昔から、精錬工場は豊かで美しい水があるところに作られることが多く、
つまりは自然環境が良いところ、ということ。
良い絹は良い水のあるところで生まれるんですよ」
織物と向き合う職人さんは「水を読む」人だ。
晴れの日。雨の日。四季の移り変わり。
自然に左右される水は当然のことながらその質が日によって変わる。
精錬職人たちは、その一定でない水の質を正確に読み取り、
コントロールするのが最大の仕事。
どんな日でも、同じ質の織物を仕上げることができるのが、
一流の職人の証でもある。
ここにもまた奥深い「伝統」があった。
工場見学を一通り終えて最後に向かったのは、
展示場で使ったという建物の中。
最近では海外向けのイベントも多く開いているようで、
イベント時は広いスペースを織物などを使いながら空間を区切り、
ブースを設けて、様々なメーカーの商品が楽しめる洒落た空間に
様変わりしたようだ。
ここでもまた守るべきものは守りつつも、
時代の変容に合わせて伝統が変化していく様を見た。
高校生たちが最終的に「継承」について
どういった答えを出すのか。
もう少し隣りで見守ろうと思う。