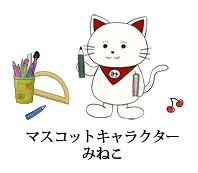学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 伝統継承するとはどういうことだろ...
伝統継承するとはどういうことだろう?~活動の過程で揺らぐ定義~vol.1
こんにちは!
地域コーディネーターの能勢です。
本日紹介するのは、2年生の
とある探究プロジェクトのチームについて。
彼女達は「伝統を継承するためには何ができるか」を
テーマに探究活動を進めています。
****
このチームは3人のメンバーで
構成されているのだが、
まずそれぞれが異なる点に関心を持っている、
という点がユニークだ。
一人は「古い町並みや建物」に魅力を感じてるという。
もう一人は「ちりめん」が好きで、
特に着物を愛してやまず、
さらにもう一人は「伝統」そのものにも
関心をいだいているが、
どちらかと言えばそれらを
"どのようにして分かりやすく伝えるか"に
着目しており、複雑なものを可視化させる、
つまりデザインに落とし込むことに
興味を持っている。
それぞれの興味関心は違えど、
「伝統をどう残し、次に繋ぐのか」という点に共通点があり、
チームになったという訳である。
一番初め、彼女達は「伝統継承とは何か」について
自分たちなりに定義づけしてみることから始めた。
話合いのもと定まったのが
「古くから受け継がれる技術や技法を残し、
それを後生にも出来る限り
保存した状態で伝えていくこと」
その定義のもと、では自分たちの考える
「伝統継承」がどのような手段であれば
実現が可能なのかを検討していく。
その時出てきたのは「パンフレット」を作ること。
彼女たちはどうしてパンフレットを
作ることに行き着いたのか。
まず1つにパンフレットは
丹後を訪れる人の多くが気軽に
手に取りやすい、と考えたから。
またパンフレットには、手に取ってもらったときに
伝統的なものに実際に触れてもらう機会にするため、
素材としてちりめんを使用したい、と話していた。
そんな訳で、ひとまずパンフレットに掲載したい情報を
整理し、実際に現場に訪問する日取りを決めていく。
ここの情報は是非とも載せたい!
実際にここには自分たちで足を運んでみたい!
そうやって出てきた場所は、
網野町八丁浜にお店を構える提灯屋さん「小嶋庵」さん
平成15年1月に文化財に登録された久美浜にある豪商稲葉本家
丹後ちりめんの文化を様々な形で継承するための活動を行っている
丹後織物工業組合さん
これらの場所に
ヒアリングも兼ねて訪問することが決まったが、
その前にrootsで何やら彼女たちの探究に
関連しそうな興味深いイベントが開催されるとのことで、
コーディネーターから訪問前にぜひ参加してみるよう、持ちかけた。
ワークショップの企画者は、丹後広域振興局で
アートマネージャーをしている甲斐さん。
実は甲斐さんも地域の人々にアートを身近に感じてほしい、
という想いからまちづくり×アート、
伝統×アートといったように
アートと様々なものを掛け合わせて
人々を巻き込んでいく形の参加型ワークショップを
これまでも数多く企画されている。
きっと彼女達の良きアドバイザーに
なってくださるに違いない、と思ったのだ。
ワークショップの内容は、地域の方々の家に眠っている
要らなくなった着物やネクタイなどの布製の小物類を
使って、町のあらゆる場所に存在している「色々な形」を
切り取り、端切れに縫っていくというものだ。
「色々な形」というのは、町の中にある何気ない日常の風景、
屋根の瓦や道端のポスト、窓の模様に思い出のある景色など。
参加者は、町を歩き、自分の感性で面白いと感じたものを
写真に収め、その写真に写った「形」を布(地域に眠っていた
布製品、つまりはその多くが着物であり、伝統的なちりめん)に
型取り、切り取る。その切り取られた布を端切れに縫い付けていく。
縫う、という行為はその人を一定時間同じ場所に留める
拘束力を持つ。
それがある意味、このワークショップの
主の目的なんだと思う。
必然的に参加者たちは縫う行為を通して、
交流をすることになる。
そう、対話だ。
彼女達もチクチクと手を動かしながら、同時に
言葉も紡いでいく。
自分たちがどうしてこの探究を始めたのか、
何に興味を持っているのか、悩みなどについて。
ワークショップ終了後には、
みんなとてもすっきりした
表情を浮かべていた。
甲斐さんや偶然居合わせた他の参加者の方との交流や
現代アートと伝統の掛け合わせといった
新しい形の体験は、彼女達に何らかの
インスピレーションを与えたらしい。
「私達は伝統継承を
"原型や昔から受け継がれる想いや
技術をできる限りそのままの状態を保ったまま、
その良さを伝えること"と考えてきたけれど、
それだけが正解じゃないのかもしれないね」
まだ自分たちの答えは見えていないが、
ワークショップでの体験は
少し自分たちの問いや定義に
揺らぎが生じた出来事となった。
そのワークショップの後に出向いたのは、
網野町の提灯屋「小嶋庵」さん。
江戸時代から続く老舗の提灯屋「小嶋商店」
京都の祇園南座前に行くと掲げられている
あの真っ赤な提灯に皆さんも見覚えがあるのでは
ないだろうか。
あの提灯を手掛けているのも実は「小嶋商店」
寺社仏閣などの歴史的建造物につきものの伝統的な提灯は勿論、
ショップのインテリアとしての現代的でお洒落な提灯まで
幅広く手掛けている。
その10代目となる兄弟の兄である小嶋俊さんが
2021年に網野町に移住して起ち上げた新たな工房が
「小嶋庵」なのだ。
ご家族での移住を決意したのは、コロナ禍の世の中に
なったことがきっかけ。
先が見えない中、世界中が塞ぎ込んでいたあの時期、
都市部から離れて遊びに来た八丁浜。
目の前に広がる景色に子供たちの目が輝いたという。
「自分が見たかった光景が今実現している。
ここが好きや。子どもたちにも伸び伸びと育って欲しい。
家族が笑顔になれる場所に拠点を持とう」
移住を決断した一番の理由は、家族の幸せを願ったこと。
そしてもう一つ、小嶋さん自身が感じていたこと。
「先が見えないことが、逆に僕にとってはワクワクすることに
感じた。"どうなるかわからないこと"に挑むことが
出来ていなかったここ最近。環境をガラッと変えて、
新しい土地で新しい挑戦をしている自分を想像する方が
圧倒的に楽しい気分になったので。」
新しい工房の目と鼻の先には丹後の美しい海が広がる。
大自然の中に佇む工房は、元機織り工場の建物。
扉を開けると自然の竹の良い香りがふわっと漂う。
そして目を引くのは、天井の高さと何の仕切りもない、
広い空間。解放感のあるその空間で、小嶋さんや奥さん、
そしてご近所のお母さんたちや若手の移住者などが
提灯を作るのに必要な部品をそれぞれ作る作業をしている。
その横では、子供たちがワイワイキャーキャーしながら
遊んでいて。
「ダイバーシティ」ってきっとこういうことを言うんだろうなぁ、
というような光景が広がっている。
「僕はこの空間を色々な人の集まる場に
したいと思っているんです。」
そう話す小嶋さん。
近所の子どもたちが「何やってるんかな」
「今日もおっちゃん、提灯つくってるんやろか?」って
気軽にぱっと入って来れるような開けた場所にしたい。
どんな人でも入れるように門を開けておく。
例えば、今ここで一緒に働いてくださる人たちは、
生まれも育ちもここ、網野町の若手のお母さん。
小さなお子さんもいて、工房に赤ちゃんも一緒に連れて来られる。
「子ども同伴OKにしていたり、赤ちゃんがぐずったら
今日はここまでにしましょう、なんて臨機応変に働いてもらっています。
こういう風にしているのも今後一緒に提灯を作れる人を
育成したいと考えているから。新たな職人を育てるのも
僕の仕事だと思っています。」
フレンドリーに話してくださる小嶋さんに
すっかり魅了された様子の高校生たち。
小嶋さんの工房では、ミニ提灯を作る体験ができる
ワークショップも企画されており、せっかくなので
高校生たちもオリジナルの提灯作りにチャレンジ★
提灯のベースになる竹の型に糊をぬり...
そこに貼り付ける紙を準備する。
表にくる紙はとても薄いので、裏側に台紙となる紙をもう一枚
貼り付けて補強。
それを先ほど糊を縫った型にペタペタ貼っていく。
一周ぐるっと紙を貼り付けて、乾かせば...
じゃーん♪
オリジナル提灯の完成!!
最後に彼女たちは、こんな質問を投げかけた。
「小嶋さんにとって"伝統継承"とはどういうことだと思いますか?」
「僕にとって伝統継承とは"時代の流れにあった方法で、
昔から受け継がれてきた素材を使って、
今目の前にいる人をワクワクさせること。
そのままの形や型を守ることだけが、決して継承だとは
思いません。まず人々の興味関心をそそらないことには
扱っているもの自体を知ってもらうことすらできませんから。」
ワクワクさせるものを作り出すこと。
面白いと興味を持ってもらうこと。
そのたの手段は多様であっていいということ。
伝統=形・型(昔ながらのもの)を守ること
と考えてきた高校生らにとっては、この答えは斬新で
とても新鮮だった。
「伝統継承」は自分たちが思っていたよりも
もっと寛容であっても良いのかもしれない。
先の甲斐さんとの交流の時もそうだったが、
まずは人々に興味を持ってもらうことから全てが始まる。
それはどうしたらいいのかな。
定義の揺らぎは、探究の学びがぐっと深まる瞬間でもある。
これから自分たちなりの「伝統継承」を形にしていくための
アクションをそれぞれが考えていってくれるだろう。