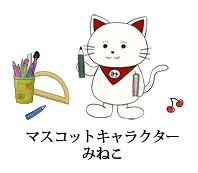学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 「福祉」って何だろう?~「高齢者...
「福祉」って何だろう?~「高齢者の健康維持に欠かせないこととは」という問いを深める活動
突然ですが、皆さんが
「福祉」から思い浮かべることは
どんなことがありますか?
介護?ボランティア?
身体的に不自由がある人を介助すること?
それはどれも間違ってはいません。
ですが「福祉」の世界はもっと広いのです。
今回紹介するのは、
「高齢者の健康維持に欠かせないこと」を
テーマに探究活動をしている高校2年生の物語。
彼・彼女らが探究活動を通して
「福祉」とどのように向き合うようになったのか。
また活動自体は現在進行形で続いているので、
今どんな風に動いているのかについて綴ろうと思う。
***
私が初め、このチームの高校生たちと接点を持ったのは
彼らの方からとある相談を受けたことがきっかけだった。
「高齢者の方々と交流をしたいのですが、
そういった場所に繋いでもらえませんか?」
ふむ。なるほど。
高齢者と関わりたいか。
だがそれだけでは、情報としては不十分だ。
なぜ関わりたいのか。何に興味を持っているのか。
これまでの取り組みで何をしてきたのか。
今どのような状況なのか...。
知りたいことは山ほどあるので、まずはじっくり
高校生達へヒアリングをしてみることに。
そこで分かってきたのは、一人は進路の選択肢として
言語聴覚士に関心を持っているということ。
そしてもう一人は、まだ具体的な進路は定まっていないが
何となく福祉分野に興味をいだいているということ。
そこで尋ねてみる。
「進路のことも含めて、二人が福祉という分野に興味を
持っているとうことは分かったんだけど、
そもそも福祉の概念であったり、今地域でどんな取り組みが
行われているのか、どんなことが課題とされているのか、
などについて調べてみたりしたのかな?」
すると一旦、互いに顔を見合わせた後、
首を横に振る二人。
そうか。それならまずは、問いの焦点を絞っていくこと、
すなわちどこに目を向けて深ぼっていくのか、を
考えるところから始めた方が良さそうだ。
そんな訳で、まず二人に紹介したのは、
社会福祉士の資格を持ち、ハローワークで就労支援を
している野村さん。
そもそも福祉とは何か、どんな職種があるのか、
その人達はどのような連携体制を取っているのかなど、
福祉の基礎となる知識について
丁寧に解説してくださる方だ。
野村さんはご親切にも
「高校生のための福祉基礎講座」なるものを
開催してくださった。
たっぷりと解説を聞かせていただいた後、
情報量の洪水を浴びて恐らくまだ混乱状態に
陥っているであろう高校生たちに質問してみる。
「野村さんのお話しを通して、何か新たな気づきや
学びがあったかな?」
すると二人とも大きく頷いて見せた。
「これまでただ漠然と福祉=高齢者や障害を持った方を
介助することに携わること、というイメージを漠然と
持っていましたが、もっと幅広い関わり方、職種があり、
選択肢も多くあることに気づけました。」
「福祉の概要について知ることができたので、
次はこの中から改めて自分たちがどの点に着目すべきなのかを
整理し、今後何をしていくのかについて検討する必要が
あると思いました。次にすべきことが見えてきたので、
今回お話しを聞けてとても良かったです!」
福祉について、理解が深まる機会になったようで
良かった。
そして次に提供した情報は、この丹後地域の中で
福祉の中のとくに「地域医療」という分野で
ご活躍されている二人の人物について。
一人は、京都全域に展開しているゆう薬局
の薬剤師である船戸さん。
京都北部のエリアのとりまとめ役をされており、
薬剤師として地域でのケア活動に力を入れる。
もう一人は、シャルコー・マリー・トゥース病という
神経難病を抱えながらも、言語聴覚士として
日々奮闘している笠井さん。
薬剤師と言語聴覚士。
職種は違うが二人に共通しているのは、その仕事への向き合い方。
「目の前にいる対象者の方、そしてその人を取り巻く
人々の幸せを願うこと。この仕事は、人を幸せにする力がある」
そういう信念と覚悟を持って、人々と、そして地域と
向き合われているのがこの二人なのだ。
高齢者福祉についてテーマに調べている高校生達には
ぜひとも会わせたい人たちであった。
これまでにお二人が取り上げられている記事は
たくさんあったので、それらをシェアし、
お二人の活動についてまずは調べられるだけ調べて、
印象に残った点や疑問に思ったこと、聞いてみたいことなどを
纏めるよう話した。
その上で、10月の中旬。
そのお二人をゲストに招き、「これからの地域医療」を
考える対談イベントを実施!!
お二人が揃うことなど滅多にないので、
これはすごい、と大人側も興奮!!
なぜ今、薬剤師が地域に出るのか、
地域医療の体制は今どのような状況にあるのか、
そして今後高齢化社会が進んでいく中で求められる
地域社会の在り方とはいったいどんなものなのか、
最期まで人間らしくあるように、話すことや食べることに
携わる言語聴覚士の覚悟ややり甲斐、
お二人のご経験に基づいた様々なエピソードを
聞かせていただいた。
しかもこの日はゆう薬局さんの若手職員(新人)向けの
研修も同時に行われたため、新入社員(1年目)の人々も
見学に来てくれて。
大学を卒業したばかりなので、高校生とも距離が近く
ワークショップでも悩み相談を聞いてくれたりなど、
とても充実した時間になったのだった。
最初の相談は「高齢者の方と交流したい」
そこから、気がつけばこんな風な出来事を通して
地域と繋がっていった高校生。
最初の想像とは違ったかも知れない。
思いもよらない方向に探究が進んでいったかもしれない。
それでも、交流の後の二人の顔はいつだって
充実感に満ちあふれていたから、こういう機会を
作って良かったなぁ、と心から思う。
探究は偶発性の連続だ。
このアクシデントをどう捉えるのか、で
学びの質も変わってくる。
きっとこれまでの取り組みを通して、
高校生たちの「探究する目的」はより具体的に
なったのではないか、と思う。
その上で、「高齢者の方々との関わり方」について
再度検討してくれたら、最初に思っていたよりも
より深い関わり方ができるんじゃないか、って。
「自分で気づくこと」
「地域の面白さを知ること」
「関わり方、考え方は様々であること」
「"交流"ひとつとっても、目的によって手段を検討する必要があること」
「福祉をちょっと違う場所から見つめてみること」
学校を飛び出して、地域と繋がっていくことで
もしかしたら新たな自分に出会えるかも知れない。
興味深いことが見つかるかも知れない。
代わり映えのしない日常に、少しの光が差すかも知れない。
高校時代になるべくそういう経験をしてもらえたら
いいなぁ、と思いながら今日も高校生達の探究を
隣で見守っている。