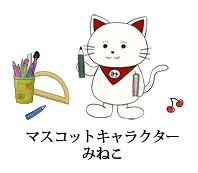学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 「ふくし」のリアルを知ろう!~「...
「ふくし」のリアルを知ろう!~「人文科学の教室」を実施しました!
福祉業界って、大変だって聞くけど実際どうなの?
そもそもどんな仕事があるの?
福祉と医療の違いって......?
保育に関心はあるけど、現場で働いている保育士の人たちは
どんな想いでそこに携わっているんだろう?
高校生たちのそんな疑問にお答えすべく、
みねやま福祉会からゲストを招いて福祉業界のリアル知るための
特別授業、「人文科学の教室」にて「Be Real フクシ」を
実施しました!
※「人文科学の授業」とは...1年に数回、放課後に開催している
特別授業。様々な分野について、より深く掘り下げるため、
その分野の専門家である講師を招いて行われる講座式の授業。
これまでの例として「美術」「心理学」「文学」等
多様な切り口でテーマをふかぼる興味深い授業が展開されている。
*****
今回の授業は、これまでやってきたものと少し違う。
それはワークショップ型であるということ。
そしてゲスト(講師)が複数人いるということ。
(普通講師は一人であるが、今回は何と7名来ていただいた!)
前半は参加者を5つのグループに分け、各グループに一人ずつ
ゲストに入ってもらう。
ゲストは、現役大学生や福祉会の若手職員ら。
なるべく高校生たちと近い年齢の人々と交流することで、
高校生らが進路の選び方(何に迷い、どう考え、どうやって決断したのか等)の
ヒントを得られたり、同じ福祉業でも働き方は多種多様で、
若い世代の人々にどんな活躍の場があるのか等
知ることができる。
若手職員のみなさんが高校時代にどんなことを考え、
どのように進路を選び、実際働いている現在はどのような想いでいるのか。
当事者の人々の「リアル」な話しは、きっと高校生らにより
「リアル」に響くはずだ。
初めに全体へ向けて、講師陣たちの自己紹介を聞く。
保育士、ケアワーカー、介護士、企画開発担当、場作りをしている人、
そして大学生......。
社会人のみなさんの職種は本当に多種多様に渡っていて、
これが全部福祉事業に関わることなの?と、参加者達は
驚きを隠せない様子。
また大学生メンバーも2名来てくれていたのだが、
一人はみねやま福祉会の内定者、またもう一人は現在福祉会で
インターンをしているとのことだが、二人ともどうやら
福祉を専門に学んでいるわけでもなさそうだ。
何となく、今回のゲストがどんな人たちなのかを把握したところで
次はグループごとに自己紹介!
今どんなことに興味をもってるのか、推しは何か、今の気持ちなどを
みんなでシェアしていく。各テーブルごとにとても盛り上がっており、
幸先の良いスタート。
場の空気が和らいだところで、講師陣のお話しを聞くターンに。
保育士、ケアワーカー、介護士の方々のクロストーク。
同じみねやま福祉会に所属していても、それぞれ働く場所が
異なるため、仕事内容ややりがいもそれぞれによって違ってくる。
介護施設では100歳になるおばあちゃんの誕生日会をしたという
エピソードがとても印象的で。
ご本人はもちろん、ご家族やその人と関わってこられた方々へ
ヒアリングをし、100年間を振り返って、思い出に残っている事柄を
年表に纏める。するとその人の人生がまるまる浮き上がってくるわけだ。
「あのときの丹後はああだった」
「このときとてもしんどかった」
「このときが人生における転機だった」
おばあちゃんが歩んできた100年間。
おばあちゃんの喜怒哀楽を隣で一緒に感じ取る。
「誰かの人生にここまで深く関わる仕事があるでしょうか。
人はみな等しく年老いていく。でも最後まで自分らしくありたい。
日常の何気ない幸せを感じたい。その人の思いを大事に、
安らぐ時間を過ごせるように日々仕事と向き合っています」
また保育士の方は子どもたちの成長を間近に
感じられることが何よりもやりがいだ、と語った。
「初めはお母さんと離れて、知らないところに連れてこられて
不安ですごく泣き叫ぶんですよね。
だけど毎日会って、大丈夫だよ~!ってコミュニケーションを
とり続けていると、ある日心を開いてくれる瞬間があるんですよ。
初め泣き叫んでいた子が、私を見て一生懸命腕を伸ばしてくる姿
何て見ると、もう溜まらないですよね(笑)」
ケアワーカーの方は、自分の存在が関わっている子どもたちにとって
とても大きいものなのだ、と感じる瞬間が一番やり甲斐を感じるようだ。
「障害のある、ないに関わらず、その子自身が何をしたいのか。
やりたいことが実現できる機会を僕たちは提供できるように
日々仕事に取り組んでいます。勿論、ハードルはあります。
上手くいかないことも沢山あります。それでも、その子にとっての
"できた"という体験はすごく大切なんですよね。
チャレンジしてみたい、こんなことがやってみたい、とその子自身から
出てくること自体が、僕の存在を認めて"この人だったら大丈夫だ"と
安心してくれているからこそ、だと思っています。
心を開いて自分自身のことを話してくれる瞬間や、
あまり笑ってくれなかった子が笑顔をみせてくれるようになったりすると
本当に嬉しいですね」
福祉のお仕事って本当に幅が広いんだなぁ、と感じると同時に
人の人生の全ての段階に関わっていることも分かる。
そして、それぞれの人々の"しあわせ"をとことん考えること、
"しあわせ"に生きるために人に寄り添うことを
大事にされているのだと実感した。
そしてワークは後半戦。
ここからはテーマに分かれて、それを話題に
ゲストと参加者が交流する時間。
① 大学生活のこと
② 福祉と医療
③ 福祉とまちづくり
④ 仕事と福祉
こんな風に4つのセクションに分かれて、自分の聞きに行きたい
テーマのテーブルに集まる。
集合したら、それぞれがゲストに質問したいことを紙に記入して
1つの袋の中に入れる。
後は時間になるまでひたすら袋の中の質問をゲストが引き、
出た質問についてゲストが答え、またその話題をさらに
その場で掘り下げていくというもの。
必然的にゲストと高校生らが対話する機会となるし、
自ら関心のある話題(テーマ)を選んでいるので、
みな関心を持って人の話を聞ける。
真剣に話しを聞いたり、疑問に思ったことを問うたり、
時々笑いが起こったり、楽しそうに交流している姿を見て、
この場にいるみんなが"自分ごと"としてこのワークショップに
参加しているからこそ、この光景を見ることができたのだ。
みんながこうも積極的に参加してくれる放課後の「特別教室」
とても素敵だな~と感じた。
今回のこの取り組みをきっかけに人数を絞った形での
分野別ワークショップ型の"人文科学の教室"はニーズが
あるかもしれないな、と密かに思ったのであった...。