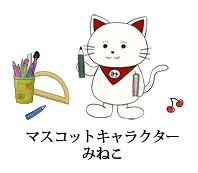学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 【地域の建物の有効な活用法につ...
【地域の建物の有効な活用法について考えたい!~学年・学校を越えたチームを結成★】
「建物の余っているスペースを有効活用して、地域の人々にとってもう少し
使いやすいようなアイディアを出してもらえたりしないかな?」
そんな相談があったのは、今から約10ヶ月ほど前に遡る。
京丹後市役所峰山庁舎の近くにNTT西日本が所有する建物が存在しているが、
建物の一部は現在、地域の方々の交流の場として使用されている。
但し、基本的に昼間しかオープンしておらず、小・中・高の児童、生徒は勿論、
仕事をしている社会人などは利用しづらいのが現状だ。
もう少し、幅広い地域の人々に利用してもらうために、
より地域の人々のニーズに沿った形を考えたいが、
そのアイディアを地域の若者たちに出してもらえないだろうか、
という声がNTTさんから上がってきたのだ。
その相談に協力すると手を挙げた二人の高校生がいた。
彼らは3年生。
2年生の時に「丹後の20年後が持続可能であるためには」というテーマで
探究活動に取り組み、当時UIターンの人々にインタビュー調査を
実施したことがきっかけで、丹後地域の新たな魅力を再発見し、
地域活性のためには「地域内での繋がり」が重要だ、
という結論を出してくれた。
今回の「地域にとってより有益な建物活用を検討してもらいたい」という相談は、
彼らの行っていた探究活動の延長線で実施できそうだ。
さらに言えば、彼らが導き出した地域活性の鍵となる「地域内の繋がり」が、
実際活性にどれほどの影響を及ぼすのかについての検証もできる可能性が高い。
とても嬉しいことに、3年生の二人は地域と関わることにとても積極的で、
こちらが何も言わずとも自分たちで次の動きを考え、準備をしてきてくれる。
2年生の時の探究での成長がこういうところで見られるのだから、とても感慨深い。
そんな風にしてスタートしたプロジェクト。
まずは、活用方法のイメージを膨らませるため、
実際に現場に足を運ぶところから始まった。
使ってもよい、と提示されているスペースは
建物の入り口を入ってすぐの広い部屋1つ分。
実際に現場を見てみると、想像していたよりも奥行きがあり、
上手く活用できれば、色々な用途での使い方ができそうだ。
「スペースが広いから机並べたら、結構な人数入りそうやな。
自習室として使い勝手が良さそう」
「案外、防音がしっかりしてそうやから、
楽器の練習場所として使うのもありかも!!」
「自習や仕事場として使える日と、イベントなんかをやる日と、
用途に合わせて使い方を変えるのもありかも」
「そもそも中高生とか社会人が使えるようにするには、開館時間を変えてもらう
必要があるけど、そういうことも提案できるんかな?」
こんな風に直接見ることで、アイディアが広がっていく。
NTTの担当の方も、まずは実現可能性の事は考えず、
一度理想的な活用法の提案をしてもらいたい、と言う。
そこで、次にコンセプトを決める。
「やっぱり、高校生視点で考える"交流拠点"を作りたいよね」
話合いをした結果、ここに行き着く。
そうと決まれば、高校生のニーズ調査をしなければならない。
「ひとまず峰高生にアンケートを取ってみよう!」
自分たちとしての意見もあるが、「地域の場」を作るには、高校生たちが
現状、どんな場を求めているのかを把握しておく必要がある。
その後に峰高生対象に実施したアンケート調査の結果、今の高校生たちが
切実に求めているものが何であるのか、が見えてきた。
「学校に自習室はあるけど、先輩が使っていると後輩はどうしても遠慮する。
それに下校時間があるから、塾に通っていない生徒は学校から出た後、
行き場がない。自習出来る場所があったらいいっていう意見がすごく多い」
「お、自習室として使うのにちょっとした飲食が出来るスペースや
自販機なんかがおいてあったらいい、っていう意見も結構あるで!」
「部活の練習スペースとして使えても良いんじゃない、って話しを自分たちも
していたけど、やっぱりそういう意見もちらほら見受けられるな」
「自習スペースと多目的で使えるスペースの共存は流石に難しそうだから、
例えば曜日によって使用目的を変えられる、といったような工夫も必要かも」
「社会人の人との交流などをするなら、やっぱりある程度夜遅くまで
営業できる体制が求められるよね」
このようにアンケートを取ることによって、
今高校生が切実に求めているものが浮かび上がってくる。
NTTさん側からは、一旦実現可能性などを抜きにして、
まず高校生視点から、一番理想的だと思えるスペースの環境を提案してほしい、
と言われているため、自分たちの理想やアンケート結果を基にプレゼンを作成する。
そして、いよいよNTTさんへ向けて建物活用に関するアイディアを発表する段階に。
「高校生が中心となって働きかけ、地域と繋がっていく場所」を
コンセプトにこれまで自分たちが考えてきたアイディアについてや、
現状高校生たちが何を求めているのかについて、
アンケート調査の結果を基に示していく。
それらを実現するための現状の課題点も挙げ、
その課題点をクリアしていくために企業側にも
協力してもらう必要がある点なども伝えた。
プレゼン後、NTTの担当の方からフィードバックをもらう。
「まず初めに、時間の無い中できっちり提案書を仕上げてきてくれてありがとう。
驚いたのがこのアンケート。
回答者が400人近くいるけど、よくこんなに回答者集められたね。
アンケート調査って呼びかけても中々回答が集まりにくいのに......。」
「より多くの回答を得るために学年団の先生やそれぞれのクラスの担任の先生方に
協力をお願いしたんです。アンケートに回答してもらう時間を取ってもらったことで、
多くの回答を集めることができました!」
これまでも高校生の探究活動において、
調査の一環としてアンケート調査への協力を求める事例は多くあった。
だが、Teamsに流す程度であったため、回答率は良くなかった。
今回、できる限り多くの高校生の意見を自分たちの活動に反映させたい、
という彼らの強い想いと、行動力が
探究活動に新たな決まりを作ることにも貢献した。
「校内アンケートを採る際には、探究の授業の一部を使って、
そこで回答してもらうようにする」
授業中にアンケートに回答してもらうよう呼びかければ、
必然的にその時間はアンケートへの調査協力のために使われる。
つまり回答率がぐんと上がる、ということだ。
彼らが積極的に動いたことが、こうして後輩達の探究の授業を
より進行いやすいような決まりを定めることに繋がった。
私は4年間、この峰山高校の探究に携わってきたが、
少しずつであるがこうした変化が年々見受けられ、
着実にパワーアップしてきているのを実感している。
道なきところには、道を作れ。
きっとこの先も探究を積み重ねていく限り、先輩から後輩へと、
思いは受け継がれていく。文化ができ、物語は紡がれていく。
今回、この建物活用のプロジェクトに関わってる3年生の彼らには、
リミットがある。受験を控えていること、そしてその先に待つ卒業。
でも彼らの表情はとても清々しいものであった。
「僕らが何をやってきたのかをちゃんと伝えることができれば、
場所の活用や地域活性、まちづくりに興味のある後輩たちが
ちゃんと引き継いでくれると思うんですよね。
2年生の時から継続して探究をやってきて感じたのは、
もちろん大変なこともあるけど、それ以上に地域に出ると面白いことが
沢山あるんだな、ということに気づけたこと。
僕たちが考えているよりも、丹後って結構良いところなんだな、
ということが分かったんです。
だからそういうことも含めて、
後輩たちにバトンを渡せたらいいな、って思います」
何と頼もしいことか。
そして彼らは、驚くべき事にこの「後輩にバトンを繋いでいくこと」を
有言実行するのである。
彼らは自分たちが卒業することを見越して、
この活動を学年や学校を越えた形でプロジェクト化することに決める。
メンバーを集めるためにプロモーション動画を作成、
これまでの経緯や今後の取り組みについての構想を盛り込み拡散。
1年生の探究でまちづくりなどをテーマにしている高校生を中心に
声掛けなども行った結果、1年生数名と清新高校に通う3年生が
プロジェクトに参加してくれることに!
学校や学年の枠を越えてメンバーを集めて実施するプロジェクトは
3年前の卒業生が有志でアニメーション動画を作った時以来になる。
ここまで探究活動を続けてくれるだけでもすごいのだか、
その先のことまでを見越して活動してくれるとは、
本当に頼もしい高校生たちだな、と心から感心したのであった。
このプロジェクトが今後どのように動いていくのか、とても楽しみである。