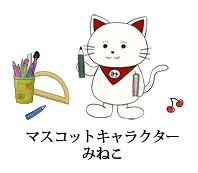学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 「ロスになってしまう丹後の食材を...
「ロスになってしまう丹後の食材を"本当に必要としている人"にシェアしたい」~SDGsゴール②「飢餓をなくそう」を達成する
1年生の探究学習のカリキュラムの軸は「SDGs」
2030年までにSDGsの17項目あるゴールが世界で全て達成されていることが
持続可能な社会を目指す上で重要なことである、と定められている。
指標であるが、1年生の探究ではこの17項目のゴールの中から1つ、
「達成したいゴール」
「将来の理想的なまちや社会を想像したとき、達成できていたら良い」
と考えるゴールを選ぶ。
そして同じゴールを選んだ人同士でチームを組み、
「理想な状態」→「世界/地域の現状把握」→
「現在行われている課題解決のための対応策の調査」→
「高校生の自分たちにできること、解決策のアイディアを出す」
ところまでをまとめてプレゼンをしてもらう、というのが
ミッションだ。
今回紹介するのは、ゴール②「飢餓をなくそう」を選んだ
ある高校生たちの物語である。
***
彼女たちの想いは、初め「独居の高齢者の方に栄養のある料理を提供したい」
というところから始まった。
その想いを深掘っていくと、1つは彼女達が育ってきた環境が
影響していることが分かってきた。
彼女達の祖父母は、自営業で小さな農家を営んでおり、
毎回どうしてもロスが出てしまうのだという。
たとえ商品として店頭に並ばないものであったとしても
質は変わらないし、食べられる。
できる限り多くの人にフードロスの現状を知ってもらいたいし、
それらを食べてもらいたい。
まずは、そういった身近な生活から見えている課題に
関心をもってたこと。
そして次に「誰に食べてもらいたいのか」について。
地域の課題を色々と調べている中で、京丹後市の現状として
少子高齢化が進み、お年寄りのみで暮らしている家庭が多いという事実。
しかも一人暮らし率も高いようなのだ。
彼女達は「飢餓」というものを
「栄養状態が悪く、きちんとバランスの取れた食事ができていない」という
意味で捉え、独居の高齢者の方々は毎日の献立を考えることも大変であること、
また生活の中で対話をする機会が少ないとぼけてしまうリスクも高まると
考えられること。そして高校生側は、お年寄りとの交流する機会が少ない
といったようなことから、「地域の中に若者とお年寄りが交流できる機会を
生み出せば、お年寄りにとっては生きがいが生まれ、若者にとっては
自分の存在が誰かの役に立っているという実感を持つことができる。
その手段として、若者(自分たち)が栄養の整った食事を届ける、
というのはどうか。そしてその食事にロスになってしまう食材を使えば、
食品ロスを減らす為の糸口にもなる」と考えたのであった。
だがここで、1つ問題が発生。
第三者への食事の提供となると、衛生面のことなどから
ハードルがぐん、と上がる。
最終的には地域と繋がっていく形を考えたいけれど、
まずは身近なところで実験的に料理を振る舞えそうなところは
ないだろうか?
そんな時、先生からこんな話を聞く。
「学校の先生は毎日とても遅くまで仕事をしていて、
特に若手の独身の先生は、家に帰ってからまともなご飯を作る
気力や余裕などは中々ない。だから毎日栄養バランスの取れた
食事をできている人って、案外少ないと思うよ」
この話がきっかけとなり、彼女達はターゲットを
「独居の高齢者の方」から「若手の独身である教員」に変更。
これでコンセプトが固まった。
ここからプロジェクトが動き出すのだ。
企画のコンセプトが決まれば、次に何を提供するかを考える必要がある。
調べてみると過去にも似たようなコンセプトのプロジェクトがあったり、
社会貢献を目的とした企業での取り組みで参考になるような事例が
たくさん出てくる。
そういったものを元にしながらレシピを考えていく。
最終的に"野菜のたっぷり入った栄養満点の豚汁とさつまいもご飯"に決定。
汁物に拘ったのは、ロスの問題を減らすことにも繋がると考えたから。
汁物であれば、食べる人が好きな分量をお椀によそうことが可能だ。
「食べる人自身が自己判断で、食べれる分量を受け取る」
これもレシピの裏に込めた想いだ。
レシピが決まったところで、いよいよ食材の調達へ。
フードロスを減らすことを目的としているため、
野菜農家さんやお肉屋さん、お米農家さんなどに
今回の企画趣旨を説明し、余っている食材、売ることのできない
B品の提供にご協力いただけないかどうかを交渉する。
この時間のかかる作業を全部自分たちで役割分担をし、
放課後の時間なども使いながら懸命に取り組んでいる姿を見て
どれほど感動しただろう。
彼女達の本気さが伝わってくる。
交渉は話をするだけではない。
実際に生産者の方のフィールドに出向き、畑仕事のお手伝いや
生産者の方々の思いなどをヒアリングさせてもらったりした。
食べてもらうことの先に、誰かの思いがある。
作り手さんの想いを知り、それを伝えていくことが
自分たちのミッションである。
少しでも誰かの関心に引っかかれば、
身近に豊かな食材があることに気づいてくれる人が一人でも増えたら、
食を通して地域での新たな繋がりを生み出せたら...。
そんな想いを持って懸命に動いたことが、きっと
地域の方々にも伝わったのだろう。
関わる人々が本当に親身にお話しを聞いてくださり、
企画への協力にも快諾してくださった。
このプロジェクトに関わらず、これまでも地域の沢山の人々の
サポートによって、多くのプロジェクトが実現してきた。
温かい気持ちの上にこの探究の授業が成り立っているのだと、
高校生たちが地域に出る度に実感するのである。
こうして食材も無事に調達することができ、
いよいよ企画本番。
2学期の期末テスト最終日、お昼までに学校は終わるので、
お昼過ぎから家庭科室にて調理を開始。
何と30人前を用意する、ということで、大量の野菜を
刻む作業から始める。同時にブロック状になっているすじ肉を
解凍し、煮込んで柔らかくする。
ここで使用したのは、牛すじだ。
ご協力頂いたお肉屋さん(にく屋さん 優)で、余っていたのが
このタイプのお肉であったのだ。豚汁ならぬ、牛すじ煮込み汁、と
何やらグレードアップしたものを提供出来そうだ。
大量の野菜、肉を刻んだ後はお米を炊く。
軽量カップがなかったため、はかりで計って必要分の米を研ぐ。
30人分ということもあり、かなりの量である。
全ての下ごしらえの工程を終え、あとはお米が炊き上がるのと
お味噌汁を時間をかけて煮込んで、完成するのを待つのみ。
ここまでで2時間ほど。テスト後、疲れているというのに
すごい集中力である。
暫く経って、お米が炊ける。
目分量の部分もあったが、良い感じに仕上がっている。
とても美味しそうなさつまいもご飯だ。
だがすごいのは、ここからが本番だと言うこと。
何とこれからさつまいもご飯で30人前以上分のおにぎりを握るという。
「日々私達のために遅くまで働かれている先生方に
少しでもほっこりできる時間を提供したいんです。
栄養満点、ボリューム満点のご飯を喜んで食べてもらえたら、
こちらも嬉しいので!」
なんと頼もしいのだろう。
彼女達の愛情の深さに驚く。
自分たちも相当疲れているはずであるのに、
そんなことはおくびにも出さず、寧ろとても楽しそうに調理をする
彼女達の姿にこの子達はこれからどこまで成長するのだろうか、
どんなところを目指していくのだろう、と未来までもが
楽しみになったのである。
そしていよいよ提供の時間に。
とくに告知することもなく、ゲリラ的に行ったので
どれくらいの先生が食べに来てくださるか多少の不安はあったが、
続々と多くの先生方が入って来られるではないか......!
大鍋に入った豚汁、もとい牛すじ煮込み汁を見て、
先生方から歓声が上がる。
「これ自分らで作ったん?すごい良い匂いしてる!」
「具だくさんやなぁ......!!これは食べごたえありそうや!」
さつまいもごはんの特大おにぎりも配ると
その場にいる人たちはみんな目を輝かせた。
「うわぁ!おにぎりまで握ってくれたんか!美味しそうやなぁ」
いよいよ試食タイム。
一口お汁を啜った先生方から感嘆の声が。
「あぁ......。これは旨いわぁ。野菜のだしがよう出てんなぁ。
こんな野菜って甘かったんやなぁ」
「お腹が満たされて幸せですね」
「おにぎりも食べ応えがあるし、さつまいもご飯が美味しいわ」
沢山の先生方からお褒めの言葉をもらって、
少し硬い表情であった彼女達の顔にも笑顔が浮かぶ。
また今回は材料の提供にご協力頂いた生産者の方々にも
お礼の想いを込めて、牛すじ煮込み汁定食を食べてもらいたい、
ということから協力していただいた地域の方々にも
集まってもらっており、そこにも届けにいく。
ボリュームたっぷりの豚汁を見て、地域の方々からも喜びの声が。
「うわぁ!とっても美味しそうにできてる!」
「うちで獲れたニンジンがすごい入ってる(笑)」
「おにぎりもおっきい!これは仕事終わりに嬉しいなぁ」
配膳が終わり、席についたらみんなで一緒に
「いただきます!」
美味しい、美味しいとみんなが喜び、
終始和やかな時間が流れていた。
企画を立て、交渉をし、生産者さんへのヒアリングや
農作業体験を経て、材料調達、そして「疲れている先生方をねぎらいたい」
という想いのもと調理し、提供するところまでを自分たちでやりきった。
これだけのことをやるのにもちろん探究の授業の時間だけでは、
到底足りない。放課後の時間や休みの日も使って、進めてきた結果である。
ここまでやるのに本当に大変だっただろう。
ただでさえ多くの課題をこなさなければならなかったり、
部活があったり、習い事に通っていたりと、高校生らは本当に
めまぐるしい毎日を送っている。
その中でまずこの企画を実施まできちんと持っていったことに
賞賛の拍手を送りたい。
またごはんというものを通して、新たな出会いが生まれ、
たくさんの人たちが幸福感で満たされた。
この体験は、これからも彼女たちの支えにきっとなるはずだ。
色々な人々との出会いの中で、自分が大切にしたいものや
新たな自分の一面、挑戦してみたいことなどを
発見していってもらいたいな、と切に願う。