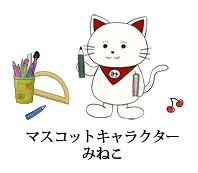学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 【いさなご探究Ⅰ】地域交流会を実...
【いさなご探究Ⅰ】地域交流会を実施しました!~1年生探究の授業vol.1~
こんにちは!
地域コーディネーターの能勢です。
峰山高校では、探究のメインとなる学年は2年生。
2年生では、自分の興味関心のある
テーマについて問いを立て、
それを検証したり、自分なりの答えを
導き出すための取り組みを学校内に限らず、
地域を活用しながら行います。
つまり、自ら「地域に出る」という選択を取っていい、
ということですね。
自ら地域、社会と出会いに行く、
という積極性が試されるわけです。
では1年生は探究の授業で何をしているのか、というと
「地域と出会う」ということをテーマにしています。
何か初めてのチャレンジをするとき、
例えばスポーツでも音楽でも、
どんな分野でもそうだと思いますが、
まずはその分野のことについて
知る必要があります。
そして、だんだんと上手くできるようにするためには
やり方について学び、練習をすること。
1年生では、2年生の探究活動で自ら考え、
積極的な行動をとれるように
その方法や考え方を学びます。
そのファーストステップとして「地域と出会う」
つまり地域を知る、という時間を設けています。
地域から、様々な分野でご活躍されている方々をお招きし、
今地域で起こっている問題(現状と課題)について
シャアしていただいたり、
それに対してどんな取り組みがなされているのか、
どんな想いをもってそこに向き合われているのか、
などについてお話しを伺いました。
そしてその話を聞いた生徒たちは
そこから浮かびあがる新たな疑問点や、
これまで自分が調べてきたことに対して
より深く追求するための質問を投げかけます。
地域を知ることは、今起こっている問題に対して
自分はどう向き合うべきなのかを考えるヒントに繋がる。
地域交流会では、何と15名の方々に
講師としてお越しいただきました!
「つくる責任 つかう責任」のテーマは、
網野町で地域おこし協力隊をしながら、
丹後エクスペリエンスという
会社を起ち上げた八隅さんにお越しいただきました。
生徒たちも楽しそうに話しを聞いています!
ここでは、海ゴミをテーマに
丹後の海岸の現状についての話を皮切りに、
今私たちが向き合うべき
"より良い社会を築いていくためには
どいういったところに着目すべきなのか"
について検討する時間になりました。
漁師でもあり、猟師でもある山中さん。
今回は「海の豊かさを守る」の文脈から
お話していただきました。
命をかけて自然と対峙することの
難しさや尊さのお話しをしていただきました。
探究すること=本気で生きることには
「情熱」を持つことが、いかに重要なことなのかについて
気づくことができたのではないか、と思います。
「ジェンダー平等」では、京丹後市市民課から稲川さんに。
学校生活の中では、あまり感じることのない男女差の問題。
ですが、社会にはまだまだ根強くこの問題ははびこっています。
改めて「平等とは何か」について考えるきっかけになりました。
「不平等をなくそう」のテーマでは、
国際交流協会の麻田さんに
お話ししていただきました。
そもそも丹後で不平等って起こってるの?と
最初は疑問を持っていた生徒たちでしたが、
実は身近なところにもたくさんの種類の"不平等"が
起こっていることが分かります。
物事が複雑に絡みあって起こっているので、
何か一つのことをすれば解決できる、
というような単純な話しではありませんが、
誰かがそこに関心を持って向き合わなければ
何も変わりません。
どんなに小さなことでも、
より良い結果を生むために起こした行動は
立派な一歩。
生徒たちは悶々と悩みながらも、
今できることについて懸命に考えます。
こちらは「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の教室。
講師はエコネット丹後の川内さん。
自然エネルギーを一通りご自身で試している川内さんの
お話しはものすごく説得力がある。
情報収集をするだけでは、何の解決策にもならない、
実践こそ、価値のあるものだ、と説く川内さんの話を聞いて
生徒たちは深く共感している様子でした。
京丹後市の「寄り添い支援総合サポートセンター」から中村さん。
「貧困をなくそう」のテーマからお話しをしていただきました。
この施設では、市民のみなさんの生活に関する
様々な困りごとについての相談を聞き、
解決策を一緒に考える取り組みをしています。
「貧困」についてのの捉え方が変わったと
話す生徒たちもいました。
ここは「飢餓をゼロに」の教室。
担当していただいたのは、
京丹後市社会福祉協議会のみなさん。
社会福祉協議会で取り組まれている
フードバンクについてや、
学校ではあまり触れられない
お金の使い方・管理の仕方についても
お伝えいただきました。
「不自由なく生活を送る」って、
実はかなり自分でコントロールしないと難しいし、
ちょっとしたトラブルが原因で
これまで当たり前に送ってきた
"日常"が一変することもある。
そもそも社会の福祉の仕組みが
整備されていないと
「不自由なく生活する」ことは難しい。
"当たり前"を見直すことに繋がっていればいいなぁ。
このように1年生の授業では、
地域に出会う機会を作っています。
この記事は、地域交流会の前半について
紹介させていただきました!
後半については、また別の記事で綴りたいと思います。
それではまた次回の記事をお楽しみに(@^^)/~~~