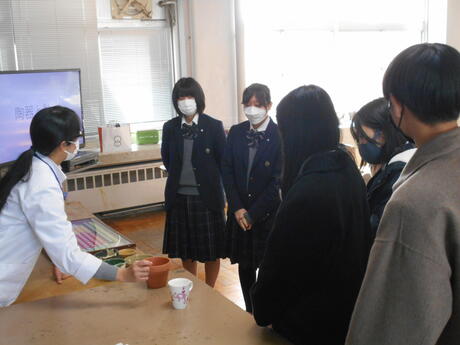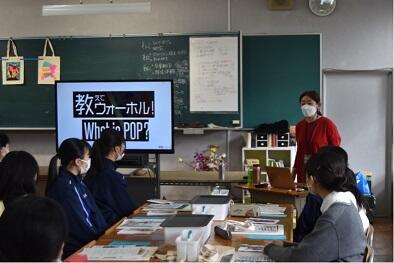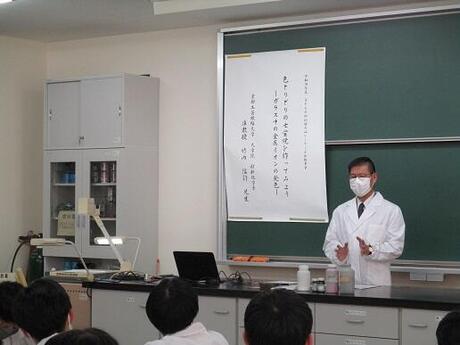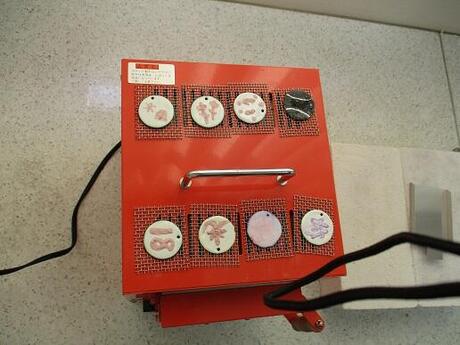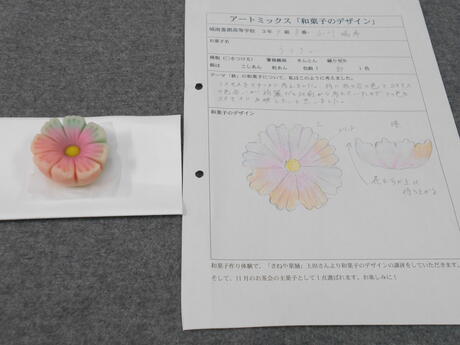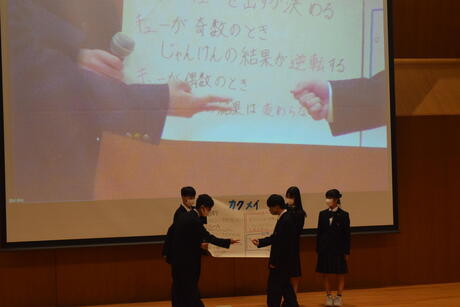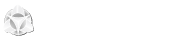2022/12/20
2022/12/16
2022/12/01
2022/11/30
2022/11/04
GSP 高大連携授業「理数化学」
教養科学科では、1年次から目的・進路意識を高め、探究心や創造力を培うため、大学や研究機関との連携授業を通して様々な取組を行います。
そして専門性を高める機会を充実すべく、グローカル・スタディーズ・プログラム(GSP)として系統的に位置づけています。
自然科学や科学技術に対する興味・関心を高め、科学的・数学的な思考力や物事を論理的に考察・分析する能力を錬磨し、より専門性を高める機会と捉えています。
教養科学科2年次生の取組として、10月28日(金)、大阪公立大学の八木繁幸教授を講師にお迎えして、「化学発光から化学を学ぶ」という授業を実施しました。
内容は、炎色反応の実験とルミノール反応の実験、さらにルミノール反応の実験を元に警察の鑑識官になったつもりで、血液のしみこんだハンカチを探し出すというものでした。最後に、ウミホタルの発光現象の実験も行いました。
2022/11/01
2022/10/11
2022/10/11
2022/10/11
2022/10/11