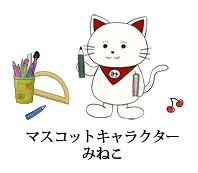学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 「音楽で人を幸せにする」~ギタリ...
「音楽で人を幸せにする」~ギタリスト八木雅彦さんへのヒアリング~
八丁浜からほど近く、
古い町並みが美しい通りをしばらく進むと、
立派な蔵が姿を現す。
この蔵、外観は立派な日本家屋であるが、
中に足を踏み入れてみると、
想像していたのとは異なる雰囲気の空間が広がっている。
レコーディングができるブースや、
作曲・編曲をするための機材、ギターなどの弦楽器。
この部屋の主は、本格的に音楽に携わっている人だ、
ということがすぐに分かる。
そう、この部屋の主こそが、今回のメイン。
ギタリストの八木 雅彦さんである。
八木さんにお話しを聞くのは、
音楽大学の作曲コースを志望している高校生。
彼女は、幼い頃からエレクトーンを弾いており、
作曲の経験もあるという。
しかし、作曲をする際に
どうしても自分が好きな音楽の系統が似通ってしまい、
中々ブレイクスルー出来ないという理由から、
作曲や音楽そのものについて、少し異なる観点から考えるため、
八木さんへのインタビューに挑んだ。
〈インタビューの様子〉
―こんにちは! 初めまして。
今日はお時間をいただき、ありがとうございます。
実は、今日お話しを聞くことをとっても楽しみにしていました!!
私は、音楽大学の作曲コースを目指しているんですが、
自分がこれまであまり触れてこなかったジャンルの音楽に触れたくて、
今回このような機会をいただきました。
これからの作曲活動に活かせるようにしたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします!
おお、すごいですね!
こちらこそよろしくお願いいたします。
何かの参考になれば嬉しいです。
―では、まず八木さんがここ丹後に移住されるまでの
ストーリーをお聞かせいただいてもいいですか。
生まれは京都府ですが、音楽活動をするのに
東京を拠点にして生活を送っていました。
ですが、東京といっても住んでいたところは調布市というところで、
緑が多く、ごみごみしたところではありませんでした。
元々自然肌で、キャンプや釣りなどアウトドアが好きで、
地方移住には関心を持っていたんです。
4年前に知り合いができた関係で丹後に来たのですが、
海の近くに住めるこの環境に一目惚れして。
なんと言っても海が大好きなので、そこから時間があれば、
丹後に通うようになりましたね。
そうしているうちに知り合いが沢山できて、
あぁ、もうこれは住んでも大丈夫だな、と。
2022年に網野町に移住をして、ここにスタジオを構えました。
月の半分以上は、ツアーなどのため丹後を離れていますが、
丹後にいる間は曲作りやレコーディングなどをしています。
―こんなにすごいアーティストさんが、
普通にこうして丹後にいらっしゃることが、何だか信じられません......。
ツアー(ライブ)は、どれくらいの規模で行われるのですか?
箱(会場)によりますよ!
ライブハウスのような小規模のところもあれば、
2万人規模の大きな会場でやることもあります。
―2万人!?
ちょっと想像がつかないのですが、
そんな大勢の前でパフォーマンスをするってどんな感じなんでしょう?
緊張はしないのですか?
そうだねぇ......。
規模が大きいと、人は米粒みたいだからそこまで大きな緊張はないかも。
逆に小さい会場の方が、観客の表情も分かるくらい距離が近いから、
また大きいところとは違った高揚感を感じたりするよ。
まぁ、規模の大小に関わらず、いつもライブが開始する直前は、一番緊張する。
色んな感情がこみ上げてきて、
苦しいとすら感じることもあるのだけれど、そ
れでも始まってしまえば、自然とその感情は消えているかな。
音楽に身をまかせて、後は全力で楽しむだけ。
―すごいなぁ。私も軽音楽部ですが、人前でパフォーマンスするときは
いつもすごく緊張します。
緊張したときの対処法はありますか。
深呼吸をして精神統一することかな。
ライブ直前のルーティーンを行うこと。
メンバーで最終確認を念入りにした後、
ステージ裏で準備体操をすることが、僕のルーティン。
でも「緊張をしなくなったら最後や」とも思っていて。
良い意味で緊張感を持ち続けられる人でありたい、って思っているよ。
―すごい。かっこいいですね。
それでは、ここから音楽に関することについて
具体的にご質問させていただきますね。
まずは作曲について。
八木さんは、作曲するのにどのくらい時間がかかりますか。
曲にもよりますが、平均すると僕は遅い方だと思います。
時々、ぱっと何か降ってくるように思いつくこともありますが......。
―そうねんですね。
八木さんは、どうして作曲をするようになったんですか。
僕はもともとB'zやX Japanが好きで、
ギターに憧れて弾いてみたんだけど、
全然上手く弾けなくて。
それだったら、自分で弾ける曲を作ってしまおう、
というのが作曲するようになったきっかけ。
―うわぁ、何だかかっこいいですね!
自分で作ってしまおう、という思考がすごいです。
いや、弾けなかったからね(笑)
弾けたらかっこよかったんだけど......。
ー作曲する際のコツみたいなものはありますか?
どんな風にして曲のアイディアが浮かぶのでしょうか?
そんなポンポン思いついたら苦労しないんだけどんね(笑)
アイディアっていうのは、これまでどれだけ色々な
「音楽」に触れてきたか、だと思っていて。
とにかく多くのものに出会って、自分の中にストックしてきたものや、
好きな音楽、そういったもののエッセンスを組み合わせて、
アレンジし、新しい曲作りに活かす。
後は、散歩をしている時などにメロディーの1フレーズが
ぱっと浮かんでくることもあるので、
そんな時はすぐに携帯などに録音しておきます。
曲作りを進めていく上で、そういった引き出し(ストック)から
引っ張りでしてくることは多いので、
ちょっとしたフレーズでもすぐに記録をとっておくことを習慣にしています。
―なるほど。すぐに記録することが大切なんですね。
あとは自分の引き出しを豊かにするために、色々な音楽に触れる経験を積むことも
必要だということが分かりました! 私もまずはたくさん聴こうと思います。
では、八木さんの音楽観についてお聴かせください。
八木さんにとって「音楽」とはどういうものでしょう?
音楽とは、普段中々伝えられない想いだったり、
どうしても伝えたいけれど上手く言語化できないことだったりを伝えるための、
「もう一つの言葉」だと思っています。
伝えたい想いがあるからこそ、曲を作っているんですよね。
後は、やっぱり音楽って、誰にとっても平等じゃないですか。
文化とか背景とか関係なく、沢山の人たちにHAPPYになってもらいたい。
その一心で、音楽やってますよ。
―うわぁ、かっこいいです!!
「もう一つの言葉」というのが良いですね。
本当にその通りだと思います。
人でも動物でも、「音楽」って初めのコミュニケーションツールでしょ。
人間も言葉を話す前は、「音」でコミュニケーションをとっていた。
音楽のルーツをたどっていくのも、すごく面白いと思います。
動物は音楽と共にあったことが分かりますから。
―確かにそうですね。
歴史などにも関心があるので、そういったこともまた調べてみたいです!
因みに八木さんは、丹後に来られてから携わった曲において、
特に印象に残っているエピソードはありますか?
そうですね。それぞれ思い入れはありますが、
1つ挙げるとしたら2022年に実施された
「DESIGN WEEK KYOTO in 丹後・中丹」のプロモーションビデオを
制作したときのエピソードかな。
企画のテーマが"ローカルから世界へ"ということだったので、
曲のベースは丹後らしい機織りの「ガチャン、ガチャン」という
リズムと音を入れて、その上にアフリカの民族音楽っぽいメロディーをのせました。
そういう意味では、自然界、生活環境の中で発生する"音"全てが、
音楽になるんですよね。
―すごい! とっても面白いです!
丹後は自然が豊かだから、例えば「海の波の音」や「鳥のさえずり」、
「木々の葉が風で揺れる音」なども作曲の要素になりそうですね!
ここからは、ちょっと部活の相談もしたいのですが、聴いていただけますか?
もちろん! 何でも聴いてください。部活動は何をしているのですか?
―ありがとうございます。軽音楽部に所属しています。
バンド練習をしていて、メンバー間の熱量が違うことがあるじゃないですか。
そのせいでぶつかったりとか......。
八木さんは、そんな時どのようにその問題を乗り越えてますか?
その問題は、バンドにつきものだよね(笑)
僕の場合は、相手へのリスペクトを大切にしているかな。
やっぱり、価値観は異なっても、
みんな「音楽」で繋がっている。
相手のことをどれだけリスペクトできるかどうかが、鍵になると思います。
音楽的な部分での考え方のズレは、必ずどこかで生じるので、
その場合は"とりあえず一回試してみる"ということを大切にしています。
一度、意見を取り入れて全員で試したあとで、
採用するかどうかや少しアレンジするなどの決断をする。
根気強く、みんなで対話をする、というのが大事ですね。
―なるほど。時間をかけてでも、全員が納得のいく形になるまで
落とし込んでいく過程が大事ということですね。
因みに八木さんがバンドを組む上で一番大事にしていることは何ですか。
やっぱり一番大事なのは「チームで何をしたいか」
「どんな音楽を目指したいのか」について明確な目標を掲げることかな。
そこに向かって仲間で音楽を作りあげていくものだと思っているから、
本気で一緒にやっていけると思ったやつとしか、バンドは組まない。
そこに絶対妥協しない。"こういう音楽をこいつらとやる!"と
心から思える人を死ぬ気で探す。
志を共にする人たちと組まなきゃ、多分続かない。
―仲間と共に同じ目標を目指す、それってすごく大事なことだと、
実感しました。
本気で取り組める仲間と音楽する、っていうのも素敵ですよね。
これから個人としても、バンドとしても
音楽の技術面を上げていくために何かオススメの方法はありますか?
方法自体は沢山あると思うけど、
僕のこれまでの経験から大切だな、と思うことを伝えさせてもらうと、
まずは「自分がどういうアーティストになりたいのか」という理想像を
イメージすること。
その上で、今の自分に足りていない部分を磨いていくことかな。
突き詰めていくと、結局同じところに行き着くよね(笑)
足りていないところを磨くには、もうできるまで練習するしかない。
―そうですよね(笑)
八木さんがプロデビューされたとき、苦労されましたか?
そりゃあ、しまくりですよ(笑)
初めてプロとして出演したライブのことは、今でも忘れられません。
勿論、僕たち以外の出場バンドはみんなプロ。
明らかに自分達のバンドが一番下手くそだった。
それが悔しくて、もうそこから毎日猛練習しました......。
―そんなこともあったんですね......!!
私達も気合い入れて、練習頑張ります!
では最後の質問をさせてください。
八木さんの考える「才能」とは、どんなものだと思いますか。
「人の気づかないところに気づけるかどうか」
これが才能だと思います。
きっと誰もが何かしら人より秀でている部分を持っていると思います。
そのことに自分、もしくは他者が少し早く気づいた、
ただそれだけの差だと思っています。
自分の才能に気づくために、常日頃から色々なところに
アンテナを張ることが大事。
このことは音楽だけじゃなくて、
どんなことでも同じことが言えると思います。
勉強や他の趣味なんかも、
自分はどんなことを得意としているのかについて考えたり、
周囲の人からよく言われることなどに着目しながら、
自分の才能を見極めていくといことも大切かもしれませんね。
ーなるほど!
自分と向き合うことって、結構辛い時間でもあったりするので、
怖かったりもするのですが、
「得意」を見極めることが才能の発掘に繋がるかもしれない、
というのは本当にそうかもしれない、と思いました!
とっても学びになるお話しをありがとうございます。
これから、自分だけの音楽を作れるよう、
より一層努力していきます!
その想いがあれば、きっと素敵な音楽家さんになれると思います。
頑張ってくださいね。応援しています!!
こうして夢のようなアーティストとの対談は幕を閉じたのであった。
〈コーディネーターより〉
いやぁ、今回もすごい方にお話しを聴くことができました。
まずプロのアーティストの仕事現場を直接見学できること。
こんなにすごいことが、この丹後の地域でできるということ。
このことに幸せを感じずにはいられませんでした。
なんと言ってもこの突き抜けた探究心。
これまで高校生を連れて、本当に様々な分野の方々に
お話しをお聞かせいただきましたが、どなたにお話しを聴いても
毎度感動で胸がいっぱいになります。
八木さんの「音楽」に対する熱い想い。
「音楽」を通して、沢山の人に幸せになってもらいたい。
誰かを救う、背中を押す、そんなアーティストになる。
八木さんは、どれだけ苦しい時があろうとも、
一切この理想、ゴールに対して妥協をしなかった。
それを叶えるための努力を惜しまなかった。
リズムを鍛えるのにダンスが良い、と聴けばダンスも習いにいった。
何も考えずともいつでも「自分の音楽」を奏でられるようになるまで、
練習をし続けた。納得のいく音楽ができるまで、考え続けた。
自分の音楽の引き出しを豊かにするために、
全く未知のジャンルの音楽や伝統文化に
触れるようになった。
「自分の音楽で楽しめるようになったのは、40代に入ってからです。
それまでは苦労もありました。
でも、これまでの全ての経験が今の僕を作っています。」
そうやって爽やかに話す八木さん。
笑顔で話すその背景には、きっととんでもない努力や多くの挫折がある。
「音楽で人を幸せにしたい」
音楽家としてプロデビューを果たし、
今や2万人規模の会場でライブを出来るようなアーティストであるが、
そこに慢心することなく、常に新しい音楽を生み出す努力や
世界へと飛び出すチャレンジを一切おしまない。
お話しを聴いていた高校生の背筋も、ピシッとのびる。
初めて触れる、プロの仕事。
きっと作曲を勉強しようとしている彼女にとって、大きな刺激となったはずだ。
これから沢山の音楽に出会って、知って、感じ、考え、悩み、歩んでいくこと。
そうすることで、彼女の見ている世界はぐんと広がり、豊かになる。
話しを聴いた後に
「俄然、音楽に対する学びのモチベーションが上がりました!」と
嬉しそうに話す彼女の姿を見て、
これからの成長がとても楽しみになったのである。