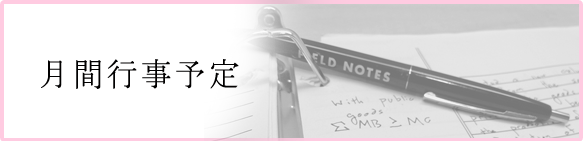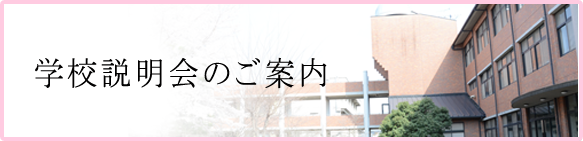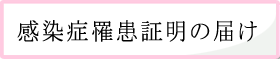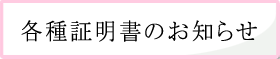日時:7月8日(月)3,4限
場所:桃山高校化学実験室
講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 芝原 寛泰 先生
銅(顆粒)に濃硝酸を加え、二酸化窒素を発生させます。
この操作は通常、ドラフトと呼ばれる換気装置のついた小室内で行います。
ここでは注射器を用いて、各グループ(2名1組)が発生気体を実験机上でミニ試験管に捕集しました。
実験1 ①ピストンを素早く押して加圧します。
加圧に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。
②ピストンを素早く引きます。
減圧に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。
実験2 ① 二酸化窒素の入ったミニ試験管を氷水にひたし,冷却しました。
冷却に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。
② 二酸化窒素の入ったミニ試験管を沸騰させた水にひたし,加熱をしました。
加熱に伴う二酸化窒素の褐色の変化を観察しました。
考察
二酸化窒素( NO2)褐色 、 四酸化二窒素(N2O4)無色
2NO2 ←→ N2O4
加圧をしたり、冷却をしたとき、左右どちらの向き反応が進み、新しい化学平衡の状態になったかを考察しました。
上の写真はミニ試験管を冷却しているところです。
下の写真は全体説明の様子です。
対象:2年自然科学科生徒全員
日時:6月24日(月)
場所:桃山高校化学実験室
講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 芝原 寛泰 先生
ヘスの法則とは、総熱量保存の法則とも言い、「物質が変化する時、出入りする熱量は、変化する前の状態と変化した後の状態だけで決まり、変化の 過程には無関係である。」 というものです。
実験1では塩化アンモニウム水溶液と水酸化ナトリウム水溶液を加え、温度変化を測定することにより反応熱(Q1>0)を求めます
。実験2では固体の塩化アンモニウムを純水に溶かし、温度変化を測定することにより反応熱(Q2<0)を求めます。
実験3では固体の塩化アンモニウムを水酸化ナトリウムの水溶液に溶かし、温度変化を測定することにより反応熱(Q3<0)を求めます。
実験1~3の熱化学方程式を完成させ、Q1、Q2、Q3の関係を求めます。(Q1=Q3-Q2を確認します。)
エネルギー図を用いて、3つの反応の関係について考察するとき、吸熱反応が含まれていたので難解でしたが、グループで討論することで理解が深まりました。
上の写真は温度を測定しているところです。
下の写真は全体説明の様子です。
対象:2年自然科学科生徒全員
日時:6月15日(土),22日(土)
場所:桃山高校地学・生物実験室
講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 田中 里志 先生
アンモナイトやコノドントなど様々な古生物(化石)についての講義を受けた後、巨椋池の粘土層から珪藻の化石を抽出してプレパラートを作成する実習を行いました。
今年は、事前に生徒による簡易ボーリングで粘土層の採取を行い全員が別々の試料を使ってプレパラートを作成しました。
巨椋池の粘土層は最上位は室町時代と決定できていますが、最下底はいつの時代か決定できていません。
今年の粘土層採取時に材化石を一緒に採集しており、これの放射年代測定を行う予定にしています。
この結果と併せることによって歴史時代の巨椋池の環境の変化がわかってくると思われます。
写真上はボーリングで得られた試料。写真下は田中先生のご講演の様子。
対象;1年生自然科学科全員
日時:6月15日(土),22日(土)
場所:近鉄向島駅周辺の田
講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 坂東 忠司 先生
向島の田は巨椋池干拓地で、豊富な生物が見られます。
坂東先生の御指導のもと、田で生物を採集し、最後に皆で持ち寄って、どのような生物がいるかを学びます。
このときに、外来生物の話や絶滅危惧種の話など、生物の多様性とその実態について知ることができます。
具体的にはミシシッピーアカミミガメの増加の話やトノサマガエルの減少の話等。また、田の生態系と田の生物の役割について学びます。
観察できた生物:カブトエビ、ホウネンエビ、カイエビ、カイミジンコ、トノサマガエル、ツチガエル、ヌマガエル、ウマビル、ナマズ、フナ、ミシシッピーアカミミガメ、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)等 生徒達は田の多様な生物に触れて楽しく学習することができました。
対象:1年自然科学科生徒全員
日時:5月29日(水)
場所:桃山高校物理実験室
講師:京都教育大学教育学部理科領域教授 沖花 彰 先生
豆電球とLEDを乾電池で点灯させるとき、豆電球は乾電池1個で点灯するがLEDは乾電池2個でないと点灯しないことや手回し発電機でコンデンサーに充電させ、豆電球とLEDを点灯させる実験では豆電球は電圧が1.0Vでも短時間点灯するがLEDは1.0Vでは点灯しないこと、電圧が2.0Vの場合、豆電球の点灯時間は十数秒だが、LEDは30秒以上となり、LEDは消費電力が少ないことを体感させていただきました。
LED電球を分解したとき、LEDの素子を乾電池2個で点灯することを確認したり、基板の裏側の端子の電圧をオシロスコープで観察することにより、交流100Vをダイオードで半波整流、全波整流されている様子や変圧器とICで直流の一定電圧にしている様子を確認しました。
実験を通して丁寧にわかりやすく生徒に理解をさせていただきました。
生徒にとって大変充実した授業になりました。
上の写真はLED電球を分解したところです。
下の写真は半波整流を確認しているところです。
対象:3年Ⅰ類理系 物理選択者