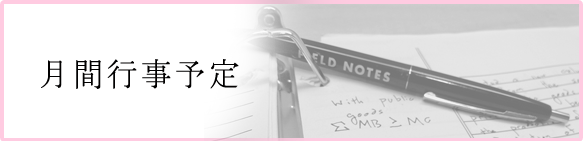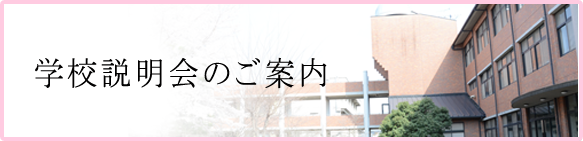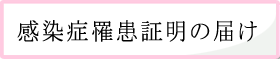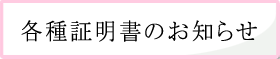第2学年自然科学科 国立民族学博物館でフィールドワーク
11月4日(金)、国立民族学博物館(吹田市千里万博公園)において、自然科学科2年生は、「GS教養Ⅰ」の授業の一環として、世界の多様な民族の文化、生活、宗教などについて学びました。メモを取ったり、写真をとったり、DVDの鑑賞をしたり、異文化への興味・関心を高め、理解を深めることができました。
10月17日18日の二日間、3年生自然科学科生物選択を対象にSSH事業「手動PCRでブタの品種鑑定をしよう」を、長浜バイオ大学黒田智先生に行っていただきました。マイクロピペットの使い方、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)、電気泳動法などを学び、生徒自身の手で実験を進めていきます。高価な専門器具を使った大学レベルの実習に、生徒は生き生きと活動しました。
9月26日(月)4限と6限にSSH講座「植物の簡易組織培養」が実施されました。
(対象生徒;3年生自然科学科生物選択生24名)
講師は 京都教育大学 梁川 正 名誉教授に来ていただきました。
植物の組織培養とは試験管やフラスコの中で植物の組織を培養し、植物体を再生するバイオテクノロジーですが、細菌やカビが入るため、通常はオートクレーブなどの滅菌装置で滅菌したり、クリーンベンチと呼ばれる無菌装置で操作するなどけっこう面倒な操作が必要です。梁川先生はこの点を改良され、家庭で使用されている漂白剤を用いて簡易に滅菌装置なしで培養することに成功されました。この技術を用いれば家庭でも比較的簡単に組織培養ができます。今回はその技術を生徒に伝授していただきました。
4限は培地を作成しました。皆で協力して通常培地と植物ホルモンの添加培地を、一人3つずつになるように作成しました。この方法では市販のストック用の袋に培地をいれています。高温で滅菌する従来の方法ではこのようなことは不可能です。
6限はいよいよ植物体を培地に植える作業を体験しました。植えたのはベンケイソウの葉とシンビジウムのPLBです。PLBとは芽の細胞の塊で、このまま通常培地に植えると細胞が増殖して植物体が再生してきます。
生徒達はつくった培地を持ち帰り、これから細胞が増殖していく様子と植物体が再生していく様子を家庭で観察します。
9月25日(日)にSSH講座「琵琶湖を探る」を実施しました。(参加者は希望者17名)
講師は 滋賀大学教育学部 石川 俊之 准教授 です。
朝7:45に桃山高校からバスで出発し、滋賀大学大津キャンパス近くの瀬田川にあるオブザベトリに到着しました。
そこで安全上の注意事項など簡単な説明をしていただきました。その後、ライフジャケットを着用して調査船「清流」に乗船し、琵琶湖の調査に出かけました。(午前中は湖上実習)
まずは南湖で水質、気象、の観測とプランクトンの採取、水底の泥の採取をおこないました。参加者は初めて見るような観測装置を使い、緊張しながら観測していました。特に湖底まで沈めると自動的に水深ごとの温度や水質を自動で計測してくれるクロロテックと呼ばれる装置は優れもので、データがパソコン上に写し出されると、琵琶湖の状態がよくわかりました。また、湖底の泥を触ってみましたが、15cm四方の泥を採取しただけでもいくつかの貝類が見つかりました。
その後、琵琶湖大橋を超えて北湖に移動し、ふたたび観測。ここではGS部の蜃気楼班による蜃気楼の観測も並行しておこなわれました。北湖では、ある程度の水深になると急激に水温が下がる水温躍層と呼ばれるものがはっきりデータに出ていました。最後に深層水を採取して皆で試飲しました。
オブザベトリに戻って昼食後は午後の観察と講義です。
まずは湖上で採集してきたプランクトンを観察しました。
その後、湖上で観測したデータをについての解析と、琵琶湖のことについて講義をしていただきました。
船の上での実習は、このような機会がないとできるものではなく、参加者一同貴重な体験をすることができました。
9月22日(祝)に龍谷大学深草キャンパスを拠点として地下鉄くいな橋付近の鴨川でSSH事業として「鴨川の水生動物と植物の生態と分類」の講座を実施しました(対象;希望者)
講師は 龍谷大学文学部教授 土屋 和三 先生(植物)
龍谷大学 非常勤講師 上西 実 先生 (水生昆虫)
のお二人です。
朝9時に龍谷大学深草キャンパスの実習室に集合し、まずは上西先生の水生昆虫とその研究の歴史についてお話を聞きました。津田 松苗 氏、今西 錦司 氏など、水生昆虫の研究の発展に重要な役割を果たされた研究家のお話が出てきました。その後、くいな橋付近の鴨川に行き、水生生物の採集と、植物の観察をしました。また、桃山高校で教鞭をとられていた先生が水生昆虫の研究をされていた話も聞かせていただきました。
土屋先生には、昔、カラムシという鴨川の河原にたくさんはえている植物の繊維から織物を作ったこと、中州のオオイヌタデは水の引いたわずかな時間に発芽、成長、結実をするというお話、クズやイタドリは海外ではやっかいな植物になっているなど植物にまつわる興味深いお話をいろいろしていただきました。
水生動物の採集では水生昆虫、魚類、プラナリアなど約40種の動物がとれました。
午後は上西先生のご指導のもと、採集した水生動物の同定とスケッチをしました。最後に土屋先生からシーボルトのフローラ・ヤポ ニカ,日本人の手による植物図譜のお話をしていただきました。現在の図鑑は絵を描ける人がいないので写真ばかりになり、わかりにくいというお話とか、植物の分類はDNAの解析が導入されて、大きく変化してきているという話をしていただきました。
盛りだくさんで参加者一同満足の講座となりました。
9月13日(火) 2,3,4時限 2年生自然科学科の生徒を対象に「エネルギーと発電技術」というタイトルで東京理科大学教授の川村 康文先生に実験実習を行っていただきました。風力発電ではサボニウス風車風力発電について説明をしていただき、小型のサボニウス風車を作成し、LEDライトを点灯させました。また、色素増感太陽電池では伝導性ガラスに酸化チタンを加熱処理したものに、ハイビスカスの色素をしみこませ、電極間にヨウ素液を加えることにより、太陽電池ができます。これをいくつか組み合わせることにより、模型の自動車を動かすことができました。生徒たちはどちらの実験も楽しく、興味深そうに取り組んでいました。
8月27日(土)午後に地域の小学生対象のおもしろ理科実験教室を開催しました。
内容は「坂を登る茶筒」「カラフルペークロ花びら」です。
「坂を登る茶筒」は茶筒にゴムや大きなナットで細工をし、ころがすとしばらくしたら逆回転して戻ってくるというものです。
「カラフルペークロ花びら」はペーパークロマトグラフィーの原理を利用して美しい花びら状の模様を濾紙につくり、うちわに貼り付けてカラフルなうちわをつくろうというものです。
全部で110名の参加者が楽しく制作し実験しました。「うわー、きれい」とか「うわー、不思議」とか歓声があがり、大いに盛り上がりました。
本校理科教員とGS部の部員の丁寧な指導のもと、皆うまく制作していました。
6月30日(木)6,7限に、自然科学科GS課題研究の経過報告会を本校コモンホールで実施しました。この経過報告会は、課題研究の進捗状況やこれから研究しようと考えている内容をお互いに報告しあうものです。発表の方法としてはポスターセッションの形式で実施しました。お互いに見た内容についてコメントシートを書いて研究に対するアイデアや改善点を出し合います。各班、他人からの意見を聞いて今後の研究についての展望が開けたことと思います。
6月22日、一年生自然科学科「GSロジック」の授業で、本校数学科の中村啓介先生に「論理的に考える」というテーマで講演をしていただきました。
これは3学期の「GSロジック」ディベート実践で、論理の立て方を数学的見地からアプローチしていく手法を身につけるための講演会です。最初は命題を真理値表を使って証明するところから始まり、最後には「GS自然科学」で以前に討論した「生命は定義できるのか」についての意見を見直し、改めて論理的矛盾点を指摘しあいました。今日、習得した手法を練習するためのものでしたが、本番さながらに意見が白熱し、3学期のディベートが楽しみだという声も多く聞かれました。
「GSロジック」ではこれからもディベート実践に向けて様々な取組をしていきます。次は9月に立命館大学の薄井先生をお招きし、出張授業をしていただく予定です。
6月21日(火)1組・4組、28日(火)2組・3組 1年生SSクラス対象に京都教育大学 教授 沖花 彰先生に分解してもののしくみを探る理科学習(鍵盤ハーモニカ)を実施していただきました。鍵盤ハーモニカはリードの部分が振動することによって音が出ています。音の高さはリードの長さや重さで変わることや鍵盤をおすと、空気の通り道ができて特定のリードだけが振動することを実験をしながら学習をしました。生徒たちはとても楽しそうに実験をしていました。