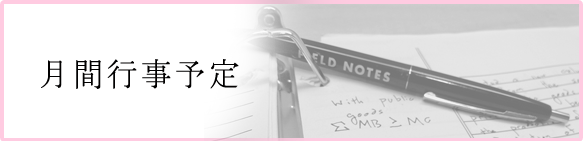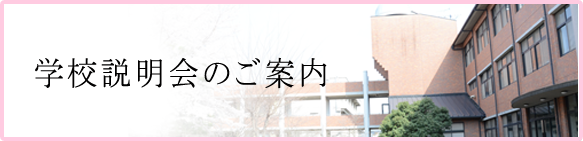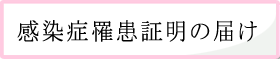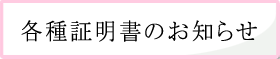9月26日に開催されました第9回千葉大学高校生理科研究発表会にて、「バナナの皮の"キリン化現象"に迫る」が優秀賞を受賞しました。審査員の講評として、「テーマの発想が良い」、「発展性のある研究である」、「アイデアがユニークでおもしろい」、「研究への熱意があり、よく努力している」、「研究内容や知識を自分のものにしている」など、励みになるお言葉をたくさんいただきました。アドバイスや御指摘をいただいた点についてもしっかり検討し、さらに発展させたいと思います。
本校SSHの取組であるGS課題研究(2年自然科学科)の成果発表会を開催いたします。本発表会は本校の教育活動の一環であり、自然科学科2年生の生徒が、GS課題研究やこれまでの教育活動の成果を口頭発表で披露いたします。
1.日時 平成27年 12月 23日 (水) 祝日 9:30~16:30(受付開始 9:00~)
2.場所 京都府総合教育センター 講堂棟 (桃山高校 西隣)
見学を希望される方は学校までお問い合わせください。 TEL 075-601-8387
11月14日(土)1年生自然科学科及び1年生普通科希望者対象に「地球環境と防災」をテーマに京都大学河川防災システム研究領域 教授 中川 一 先生にお世話になり、京都大学防災研究所 宇治川オープンラボラトリーで体験学習等を実施しました。
豪雨体験、流水階段歩行、浸水ドア開閉、土石流の学習、津波実験施設見学を行い、体験を通して災害時の対応を考えるきっかけになったと考えています。生徒達は流水階段歩行や浸水ドア開閉の体験がよかったようでした。
10月30日、一年生自然科学科の「GSロジック」の授業で、立命館大学教授の薄井道正先生をお招きし、「論理的・批判的思考力を鍛えるアカデミック・ライティングの技法」というテーマで講義をしていただきました。
「何のために文章を書くのか」から始まり、「観察の必要性」、「具体的な論述の仕方」などについて、時にはユーモアを交え、時には熱く語っていただきました。110分間の講義でしたが、生徒達は「よくわかっておもしろかった。」「自分にも書けそうな気がする。」「今度は実際に書いてみたい。」など、考え、書くことに対する意欲を大いに刺激されたようでした。
GSロジックは本校独自の新しい科目ですが、論理的に考え、表現することにこれからも様々な形で取り組んでいきます。
10月21日(水)の3時間目と10月23日(金)の3,4限と6,7限でDNA鑑定の実習をしました。
対象は3年生8,9組自然科学科の選択生物生徒23名の講座です。
講師は長浜バイオ大学の黒田 智 先生にお願いしました。
21日にまず概要の説明とマイクロピペットの使用法を教えていただきました。
23日3,4限では、白ブタ,黒ブタ,茶色ブタのDNAを配布していただき、手動のPCR法でDNAを増やしました。ブタのDNAにDNA合成酵素などを入れて温度の違う3つの水槽(うち1つは市販の電気ポット)に順番にいれていくというもので、大学や研究室では機械にさせているので、勝手にできあがるものを手順を理解してもらうためにこのような手動で行いました。時間をはかって、タイミングよく移動させねばならないので大変でしたが、うまくいきました。
23日6,7限ではアガロースゲルを用いた電気泳動をおこない、増えたDNAが何色のブタのものかを鑑定しました。まずは制限酵素をいれて、ふやしたDNAの特定の部分を切断(色の違うブタでは切れるところが違う)し、電気泳動にかけました。電気泳動にかけると、DNAの断片の大きさの違いでバンドのでき方が違い、何色のブタのDNAかを鑑定できます。
全員が何色のブタかを鑑定し、答え合わせをしました。その後、修了証をいただいて実験を終えました。
大学入試にも頻出するPCR法や電気泳動を体験できたので、受験に大いに役立つ知識がついたと思います。
講演および実習: 対象 2年自然科学科(89組)生物選択生 24名 日時 9月15日(火)6,7限 場所 桃山高校生物実験室
現地調査: 対象 希望者 日時 9月21日(月) 場所:滋賀県朽木安曇川上流
講師:龍谷大学講師 上西 実 先生
15日は上西先生の御講演と御指導の下、実体顕微鏡を用いた滋賀県の水生昆虫などの紹介や、水生昆虫と環境の関係性などを学習し、環境について考ました。
21日はバスで滋賀県朽木の安曇川上流に行き、水生昆虫の採集と観察をおこないました。自然豊かな場所での実習でした。
「京伏"水"学(きょうふしみがく)」の一環として「伏見の水探索」を毎月、実施しています。美味しい水が湧き出る地域として、またお酒つくりや歴史で有名な地域だけあって、いずれの採水地も多くの人でにぎわっていました。調査の途中、地元の伏見大手筋商店街を通りますが、この商店街も人でいっぱいです。地元民の愛する地域であることを実感できます。地元の学校(の一員)として、伏見桃山のことをもっと知りたいと思いました。
(今回の調査水:御香宮神社(御香水)、鳥せい(白菊水)、黄桜酒造(伏水)、長建寺(閼伽水)、月桂冠大倉記念館(さかみず)、乃木神社(勝水)の6種類を対象)。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
「京伏"水"学(きょうふしみがく)」の一環として「伏見の水探索」を毎月、実施しています。また、SSH(スーパーサイエンスハイスクール事業)の一環として、毎年、淀川水系の環境調査を実施しております。この2つの取組の共同プロジェクトとして、淀川水系の水質調査を行いました。琵琶湖を起点に、瀬田川南郷洗堰、鹿跳橋付近、天ヶ瀬ダム、宇治川(宇治橋下)の水を採水し、その場で各主成分の簡易測定を行いました。また、学校に戻り、より詳細な成分分析を化学的な手法を駆使して行いました。現場に出向いて水辺の環境を観察することで、地形に関する学習や生息する生き物の観察もできる、"総合サイエンス"となっています。今後もずっと継続していきます。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
日時:9月18日(金)4, 6,7限 対象;3年生自然科学科GS生物(選択生物)受講生徒22名
講師:京都教育大学名誉教授 梁川 正 先生
胡蝶蘭やシンビジウムなどのランの仲間は種子から栽培することが難しいので組織培養の手法を用いて栽培、販売しています。組織培養は植物の組織や種をフラスコや試験管のような容器の中の寒天培地(MS培地等)で培養し、分化させて植物の苗を育てる手法です。
一般的な方法では、オートクレーブで加熱滅菌し、クリーンベンチや無菌箱を用いて無菌操作を行わないと、細菌やカビにやられて失敗してしまい、ハードルの高い、しかもお金のかかる手法でした。しかし、市販の殺菌剤(キッチンハイター等)と市販の肥料(ハイポネックス等)を混ぜた寒天培地で滅菌や無菌操作を簡易におこなうことができます。
本講座では、その手法を実際に体験しました。
9月17日(木) 6限(1年4組),7限(1年3組)に物理実験室にて京都教育大学教育学部 教授 沖花 彰 先生にSSH事業「分解してもののしくみを探る理科学習(けん盤ハーモニカ)」を実施していただきました。鍵盤ハーモニカはなぜ鳴るのかを分解していきながら、音がでる仕組みを説明していただくことで、理解を深めることができました。生徒達は皆、興味深そうに実験実習に取り組んでいました。