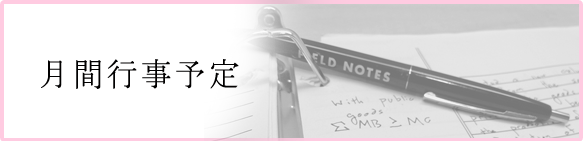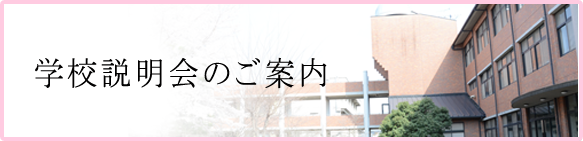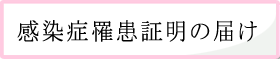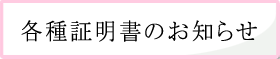日時:6月23日(月)1限(1年6組)、3限(1年7組)
24日(火)3限(1年4組)、5限(1年5組)
場所:桃山高校化学実験室
内容:テルミット反応の実験
講師:京都教育大学 教授 芝原 寛泰 先生
一般的には演示実験として扱われる、酸化鉄がアルミニウムによって還元され単体の鉄が生じるテルミット反応を、環境に優しいマイクロスケール実験(小さいサイズの実験)を2人1組で行っていただきました。生徒たちは「爆発して火花が散って、ビックリしました。」「酸化鉄の粉末が鉄の塊に変化するとき、実験卓上にセッティングした小さな空間であっても、その激しさを実感した。」というような感想を述べていました。
対象 1年生SSクラス
グローバルサイエンスベーシック課題研究発表会(1年)
日時:平成26年2月22日(土)9:00~11:00
場所:桃山高校視聴覚室
1年生自然科学科は学校設定科目「グローバルサイエンスベーシック」で行った課題研究の成果を英語でプレゼンする「英語による課題研究発表会」が本校視聴覚教室で行われました。
当日は、本校のSSH運営指導委員の先生方が審査にあたる中、生徒の保護者も多数参加されて盛大に行われました。
スライドや発表内容は全て英語で行われ、内容もすばらしいものであるとの評価をいただきました。
2月25日(火)には審査発表があり、最優秀賞、優秀賞、特別賞、奨励賞が6つの班に授与されました。
写真は発表の様子です。
日時:平成25年12月9日(月)
場所:大黒寺、御香宮、黄桜、乃木神社、鳥せいの湧水場、キンシ正宗、生物実験室
対象:2年普通科Ⅰ類理系
講師:キンシ正宗製造部長 田中 明 先生
この企画では、伏見の水をテーマにしました。
キンシ正宗の田中先生に、工場見学・酒造りについての講演を行っていただきました。
また伏見区各所の湧水を採取し、生物実験室で飲み比べをしました。
水の味の違いは中々わからない生徒もいましたが、専門的なお話をたくさんしていただき、生徒たちは熱心に聞いていました。
理科の知識が仕事に役立っている現場に触れることができ、理系の大学へ進学を希望する彼らにとっては非常に貴重な体験となりました。
写真上:生徒が水を汲んでいる様子
写真下:工場見学の様子
12月22日(日)京都府総合教育センターにて自然科学科2年生の課題研究発表会が実施されました。
口頭発表は桃山高校からは予選を通過した6チーム、招待発表として 「希少糖2013」(高知県立高知小津高等学校)、「小児用バファリンを作ろう」( 京都府立嵯峨野高等学校)がありました。
その後、会場のロビーを利用して、ポスター発表が開催されました。
桃山高校からは18チーム、高知小津高校、嵯峨野高校、洛北高校にも参加していただきました。
課題研究発表会の最優秀賞には「SUGOI しんきろう」、優秀賞には「ポリオールの結晶性を探る」、「湖東コールドロンの放射線による再証明」
グローバルサイエンス賞は「CRATER」、「物理エンジンを用いた遺伝的アルゴリズムに関する研究」、「プラナリアの記憶」が受賞しました。
いずれの発表も内容がも充実しているとともに、とてもわかりやすく説明をされていました。
対象:2年生自然科学科
日時:11月9日(土)
場所:京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー
講師:京都大学防災研究所 中川 一 教授
地震津波や台風等、水害に対する意識が高まる中で、水害時に起こる現象を実際に体験して学ぶSSHの人気講座である。
主に以下の4項目について先生方から解説を受けた後、実際に体験を行った。
生徒達は体験型の学習を通してとても良い刺激を受けている様子であった。
(1)地下ドア水圧実験
地下室や地下街が浸水したとき、ドアを開けて脱出できるのかを体験した。
50cm程度浸水すると急にドアにかかる水圧が大きくなり、ドアを開けられなくなることがわかった。
(2)降雨体験
時間雨量200mmの豪雨を、実際に傘をさして体験した。
(3)浸水車ドアの開閉実験
水没した自動車からドアを開けて脱出する体験をした。
通常のドアはもちろん、スライドドアでさえ水圧で開けられないことがわかった。
(4)地下階段浸水体験
地下鉄の駅階段を想定した実験設備で、河川からあふれた水が階段に流れ込んだ際の水の勢いを体験した。
写真上:浸水車ドアの開閉実験
写真下:階段浸水体験
対象:1年生自然科学科
10月30日(水)、31日(木)
場所:桃山高校物理実験室
講師:東京理科大学 理学部 教授 川村康文先生
10月30日、31日(木)に2年生自然科学科を対象にSSH講座「色素増感太陽電池の最先端」が行われました。
講師はエネルギー教育で有名な東京理科大学理学部教授の川村康文先生。
生徒達は、ハイビスカスの花の色素を使った太陽電池を自作し、それらを接続して車を走らせることに挑戦。
色素増感太陽電池で車を走らせるには高度な工作精度と良質な素材が必要。
生徒達はどのような工夫で電池としての性能を向上させたのかを学びながら車を走らせることに挑戦。
いくつかの班は成功したがうまくいかない班も。
制作をとおして電池の性能限界や実用性に目を向け学習していました。
対象:2年自然科学科
日時:11月16日(土)
場所:桃山高校物理実験室
講師:京都教育大学教育学部理科領域
准教授 谷口 和成 先生
前半ではデジタルマルチメータ、電源の使い方やブレッドボードの使い方を教えていただきました。
それらを用いて、直列接続された抵抗値の比と電圧の比が等しくなる電位分割の考え方を実習を通して教えていただきました。
また、可変抵抗と定抵抗を組み合わせた回路で定抵抗にかかる電圧についても丁寧に説明をしていただきました。
後半では温度や明るさが変化すると電気抵抗が変わるセンサー素子を利用し、生徒たちが設定した温度または明るさ(暗さ)で電子オルゴールが鳴り出すようにします。
センサーには温度や明るさによる特性があり、この特性を理解していないと目的が達成しにくくなります。
生徒達は試行錯誤を繰り返しながら、センサーの設計を行っていました。
自分達で設定を決められることもあり、達成感がある、とても充実した授業になりました。
上の写真 センサー設計の原理の説明
下の写真 光センサーの特性を測定中
対象:2年自然科学科
11月15日(金)2年生自然科学科の課題研究発表会(校内選考会)が視聴覚教室で開催されました。発表グループは18班あり、各班5分~7分で日本語で発表を行いました。
分野は物理、化学、生物、地学、数学でバラエティーに富んでいました。
上位6チームが12月22日(日)に京都府総合教育センターで開催される課題研究発表会に口頭発表します。
上の写真はクレーターについての発表スライド
下の写真はサリチル酸の蛍光構造についての発表スライド
対象:2年自然科学科
日時:10月21日(月)~23日(水)
場所:桃山高校生物実験室
講師:長浜バイオ大学 黒田 智 先生
21日(月)
マイクロピペットの使用法を学びました。
22日(火)
黒ブタ、茶色ブタ、白ブタのDNAサンプルを一人一本もらい、PCR法で増幅しました。
PCR法によるDNA増幅では3つの温度をそれぞれ電気ポットと恒温水槽でキープしました。
一回ごとでDNAが倍になるのでこの操作を全員で分担して繰り返しおこない、多量のDNAを得ました。
23日(水)
前日に増幅したDNAを制限酵素で処理し、電気泳動法で鑑定しました。
制限酵素でDNAの特定の場所を切断した後アガロースゲルに入れ、電気をかけ、その移動が3種類のブタの遺伝子で違うことを使って鑑定しました
。ほとんどの生徒が正解していました。
最後に修了証をいただいて終了。
楽しい実習でした。
対象:3年生自然科学科生物選択生
日時:9月21日(土)
場所:滋賀大学,琵琶湖湖上
講師:滋賀大学教育学部 石川 俊之 准教授
午前中は実習船「清流Ⅲ」に乗船させていただき、琵琶湖の南湖と北湖の二カ所のポイントで水質等の観測や、プランクトン、水の採取をしました。南湖では、風向、風速、透明度、水深に従って水温やクロロフィル量などがどのように変化するかを計測しました。
また、エクマン採泥器で湖底の泥を採取、湖底の生物(貝など)を観察するとともに、湖底の泥にさわってみて、その状態を調べたりしました。
また、プランクトンネットでプランクトンの採取もしました。
北湖でも採泥をのぞき、ほぼ同じような観測や採取をしましたが、さらに深層水を汲んで、コップにいれて飲むという体験をしました。
並行して、風船による気象観測(蜃気楼のときの温度分布のデータ取得が目的)もしました。
午後はオブザベトリに戻り、午前中のデータ解析や、プランクトンの観察をしました。
水温躍層(水温が急に下がる層)などがはっきり出ていて、湖沼の環境をしっかり学ぶことができました。
プランクトンは、ボルボックス、ビワクンショウモ、ミクロキスティス、ケンミジンコ等、多くの種類を見ることができました。
対象:希望者