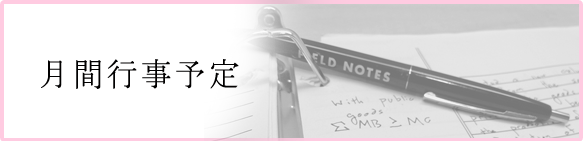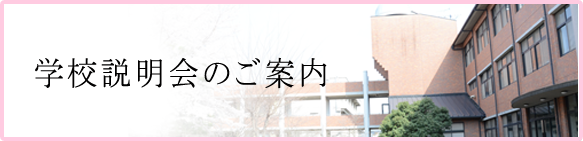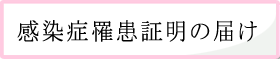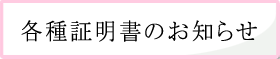「京伏"水"学(きょうふしみがく)」の一環として「伏見の水探索」を毎月、実施しています。また、SSH(スーパーサイエンスハイスクール事業)の一環として、毎年、淀川水系の環境調査を実施しております。この2つの取組の共同プロジェクトとして、淀川水系の水質調査を行いました。琵琶湖を起点に、瀬田川南郷洗堰、鹿跳橋付近、天ヶ瀬ダム、宇治川(宇治橋下)の水を採水し、その場で各主成分の簡易測定を行いました。また、学校に戻り、より詳細な成分分析を化学的な手法を駆使して行いました。現場に出向いて水辺の環境を観察することで、地形に関する学習や生息する生き物の観察もできる、"総合サイエンス"となっています。今後もずっと継続していきます。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
日時:9月18日(金)4, 6,7限 対象;3年生自然科学科GS生物(選択生物)受講生徒22名
講師:京都教育大学名誉教授 梁川 正 先生
胡蝶蘭やシンビジウムなどのランの仲間は種子から栽培することが難しいので組織培養の手法を用いて栽培、販売しています。組織培養は植物の組織や種をフラスコや試験管のような容器の中の寒天培地(MS培地等)で培養し、分化させて植物の苗を育てる手法です。
一般的な方法では、オートクレーブで加熱滅菌し、クリーンベンチや無菌箱を用いて無菌操作を行わないと、細菌やカビにやられて失敗してしまい、ハードルの高い、しかもお金のかかる手法でした。しかし、市販の殺菌剤(キッチンハイター等)と市販の肥料(ハイポネックス等)を混ぜた寒天培地で滅菌や無菌操作を簡易におこなうことができます。
本講座では、その手法を実際に体験しました。
9月17日(木) 6限(1年4組),7限(1年3組)に物理実験室にて京都教育大学教育学部 教授 沖花 彰 先生にSSH事業「分解してもののしくみを探る理科学習(けん盤ハーモニカ)」を実施していただきました。鍵盤ハーモニカはなぜ鳴るのかを分解していきながら、音がでる仕組みを説明していただくことで、理解を深めることができました。生徒達は皆、興味深そうに実験実習に取り組んでいました。
9月15日(火)13:30~16:20 5~7限 2年生自然科学科 物理選択者 対象に東京理科大学教授の川村先生に「エネルギーと発電技術」というタイトルで実験実習をしていただきました。サボニウス風力発電では風力発電について学習をした後、小型のサボニウス風車を作成し、発光ダイオードを点灯させました。色素増感太陽電池では、伝導性ガラスに二酸化チタンのペーストを塗り、高温で加熱することにより、酸化チタンに変化させます。その後、赤色色素につけ、各自1枚ずつセルを作成し、電子オルゴールを鳴らしました。生徒達は満足そうでした。
実施日:平成27年9月13日(日) 対象:希望者 講師:滋賀大学教育学部 石川 俊之 准教授
滋賀大学の調査艇「清流Ⅲ」に乗船させていただいて、琵琶湖の水質・生物・湖底堆積物を本格的な機器を使って調査させていただきました。調査地点は南湖と北湖の2カ所でそれぞれの水質の違いや特徴を学びました。また、北湖では、深層水を採水器を使って採取し、実際に飲む体験をしました。
調査の後、滋賀大学に戻り、調査データについてお話をしていただいた後、プランクトンネットで採集してきた琵琶湖のプランクトンの観察をしました。
「京伏"水"学(きょうふしみがく)」の一環として「伏見の水探索」を毎月、実施しています。今回、株式会社山本本家様(以下山本本家)の御好意で、白菊水を汲みだしている井戸を見学させていただくことができました。また、その場で水を採取し、分析もしました。
山本本家は、日本を代表する醸造メーカーで、清酒「神聖」の製造や居酒屋「鳥せい」の経営等で有名です。1677年に創業されたとても歴史のある会社で、今回、その歴史の一端を感じることができました。お忙しいところ、貴重な時間と機会を御提供いただきありがとうございました。
(調査水:御香宮神社(御香水)、鳥せい(白菊水)、黄桜酒造(伏水)、長建寺(閼伽水)、月桂冠大倉記念館(さかみず)、山本本家井戸(白菊水)の6種類を対象)。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
「京伏"水"学(きょうふしみがく)」の一環として「伏見の水探索」を毎月、実施しています。この活動を通して、科学に対する興味関心を喚起するとともに、地元の環境や歴史を再考したいと考え
桃山高校の立地する伏見区にはたくさんの湧水があり、その多くが名水として区民等に親しまれています。その水について、湧水ポイントに出かけ行き、味や見た目、水温、金属イオン量、COD等を調べました(御香宮神社(御香水)、鳥せい(白菊水)、黄桜酒造(伏水)、長建寺(閼伽水)、月桂冠大倉記念館(さかみず)の5種類を対象)。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
ております。
8月22日(土)午後、小学生対象のおもしろ理科実験教室がグローバルサイエンス部の生徒の協力のもと開催されました。「不思議なコマ」では渦巻きの模様がかかれたコマ、ベンハムのコマ(白黒)、にょろにょろゴマを作りました。回転している渦巻きをしばらく見てから視線を手のひらに移すと手のひらがウニョウニョと動くのを見たり、白黒のコマなのに回転するといろいろな色が見え、不思議(錯視)を体験してもらいました。
「ミニ潜水艦をつくろう」では500mlのペットボトルを利用し、金魚形の醤油差しを潜水艦に見立てて浮沈子を作りました。子供達はマジックで色をぬったり、きらきらシールをペットボトルに貼るなど、工夫をこらしていました。写真は実験の様子です。
8月3日(月)から7日(金)まで京都大学を中心に、(一部京都教育大学、島津博物館等)日英サイエンスワークショップ2015京都が開催されました。(宿泊;くに荘)
参加者は日本から23名とイギリスから21名の計44名の生徒です。開校式のあと、日英いりまじって班をつくり、京都大学や京都教育大学で大学の先生の指導のもと、ミニ研究をおこないました。また、宿舎での交流会や博物館(京大博物館と島津博物館)の見学もしました。最終日に京都大学の益川ホールで発表会と閉校式をしました。発表はすべて英語。研究中もイギリスの生徒とのやりとりはすべて英語でした。参加した日本の生徒達は英語でイギリスの生徒達と親しく話が出来るようになり、また、発表も堂々として質問にも英語で受け答えできるなど、大変大きく成長したな、と実感できるすばらしい取り組みでした。
期末考査明けの7月6日、一年生自然科学科の「GSロジック」の授業で、京都教育大学准教授の佐竹伸夫先生をお招きし、「論理・推論・証明について」と題し、講演をしていただきました。証明問題の演習を交えてのご講演でしたが、専門用語が飛び交い、哲学にまで及ぶレベルの高い内容に対し、「難しかったけどおもしろかった。」「大学の授業はこんな感じなのだと思った。」「真は本当にあるのかという問に興味がわいた。」など生徒達は大いに知的好奇心を刺激されたようでした。GSロジックは本校独自の新しい科目ですが、論理的に考え、表現することにこれからも様々な形で取り組んでいきます。