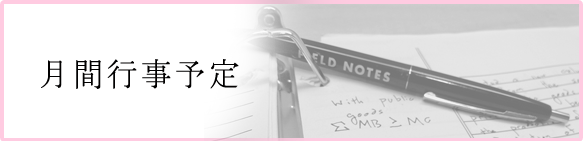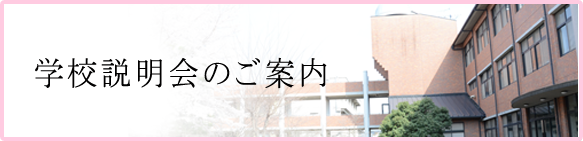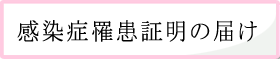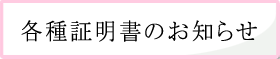6月25日(木)6,7限に 京都教育大学 教授 沖花 彰 先生に「分解してもののしくみを知る理科学習(電磁誘導)」の実験実習講義を3年生普通科理系物理選択者にしていただきました。 IH調理器のプレート上の各部分の磁場を磁化させた釘を使って調べたり、ストローに導線を巻いた豆球を使って明るくなる場所や向きを探索することによって磁場の様子や電磁誘導について理解を深めました。生徒達は楽しそうに実験を行っていました。
6月22日(月)6,7限にコモンホールにて課題研究経過報告会を行いました。グループで研究している内容をポスターにまとめたものを発表するポスター発表形式で実施しました。生徒達は説明を聞き、質問をしたり、研究のアイディアを出すなど今後の研究に役立つ報告会になったと考えています。
研究内容は以下の通りです。
1班 人間の視覚情報について
2班 Mathmaticaによる画像処理
3班 三脚動物(シミュレーション?)
4班 偏光板
5班 ジャイロ効果の謎
6班 マグヌス効果
7班 料理の科学
8班 最強の電池を捜せ
9班 光触媒
10班 アリの偏食
11班 クスリ
12班 アリ
13班 となりのゾウリムシ
14班 クマムシ
15班 ブラインシュリンプの孵化率
16班 善兵衛への挑戦
17班 古宇治川の流れを探る
18班 京都に眠れる水
19班 絶対焼かない(日焼け)
本校グローバルサイエンス(GS)部の生徒が、京都サイエンスフェスタ(6月14日、京都大学)にて日頃の研究成果を口頭発表しました。(研究タイトルは以下の5題。)
・巨椋池の古環境を探る
・琵琶湖の下位蜃気楼の発生条件(奨励賞受賞)
・バナナの皮のキリン化現象にせまる(奨励賞受賞)
・サリドマイドは植物にも効くか?
・巨椋池干拓地の放射線測定による分析
いずれの発表も素晴らしく、大学の先生や高校教員を含むたくさんの聴衆の前で、堂々と日頃の成果をアピールできました。また、GS部の生徒が当日の会場司会を務めたり、積極的に質疑応答に加わったりするなど、その存在感もアピールできました。上記5題の研究以外にもたくさんの研究が進行しており、今後、様々な発表会でその成果が披露できればと思います。GS部の活躍から目が離せません!
京都サイエンスフェスタは、京都府立高校生による課題研究発表会です。スーパーサイエンスネットワーク京都校(京都府立のSSH校科学技術に関する興味・関心を喚起するとともに、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の育成を目的に実施されております。
私達が普段使っている水道水は、どこからきて、どこへ流れていくのか、ご存じですか?水道水を作る浄水過程で行われている凝集沈殿を行い、水道のしくみを学びます。
対象;1年生自然科学科
実施日;6月13日(土) 6月20日(土)
講師;京都学園大学 准教授 辻村茂男 先生
場所;化学実験室
鎌倉時代~室町時代に巨椋池に堆積した粘土層(巨椋池粘土層)から珪藻化石を抽出し観察することで、過去の巨椋池の古環境を探ります。
対象;自然科学科1年生
実施日; 6月13日(土) 6月20日(土)
場所;地学教室
講師;京都教育大学 教授 田中里志 先生
「京伏"水"学(きょうふしみがく)」の一環として「伏見の水探索」を実施しました。
桃山高校の立地する伏見区にはたくさんの湧水があり、その多くが名水として区民等に親しまれています。その水について、湧水ポイントに出かけ行き、味や見た目、水温、金属イオン量、COD等を調べました(今回は、乃木神社(勝水)、御香宮神社(御香水)、鳥せい(白菊水)、黄桜酒造(伏水)、長建寺(閼伽水)、月桂冠大倉記念館(さかみず)の6種類を対象。)。曇り気味の少し暑い日でしたが、みんなしっかり頑張っていました。
この活動を通して、科学に対する興味関心を喚起するとともに、地元の環境や歴史を再考したいと考えております。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
SSHの取り組みの1つとして、桃山サイエンスゼミ(MSS)を行いました。放課後に希望者が集まって科学的な内容に関する英文記事をグループで読みました。講座の最後には、記事に関する自分の感想を英語で伝え合いました。
5月16日(土)に立命館大学びわこ・くさつキャンパスにて開催されました第62回日本生化学会近畿支部例会にて、GS部から2題の研究発表を行いました。
研究タイトル① 『サリドマイドは植物の生長にどのような影響を及ぼすか』
研究タイトル② 『バナナの皮のキリン化現象について』
両研究とも、化学と物理の視点で生物(生命現象)にせまろうとする内容です。昨年度辺りから本格的に進めている研究で、少しずつですが、結果が蓄積してきております。高校生の発想を大切にしながら、なるべくオリジナリティーのある研究ができればと考えております。今後の展開が楽しみです。
写真1枚目は『サリドマイドは植物の生長にどのような影響を及ぼすか』の発表のときの写真
写真2枚目は『バナナの皮のキリン化現象について』の発表のときの写真
本年度から本校のオリジナル学問として「京伏"水"学(きょうふしみがく)」を提案し、その活動を開始しております。その活動の一環として「伏見の水探索」を実施しました。
桃山高校の立地する伏見区にはたくさんの湧水があり、その多くが名水として区民等に親しまれています。その水について、湧水ポイントに出かけ行き、味や見た目、水温、COD等を調べました(今回は、御香宮神社(御香水)、鳥せい(白菊水)、黄桜酒造(伏水)、長建寺(閼伽水)、月桂冠大倉記念館(さかみず)の5種類を対象。)。
快晴の日で、とても気持ちよく水探索ができました。
さて、長建寺の住職様が本校の卒業生であることを偶然知りました(住職様、我々の不勉強と失礼をお許しください)。その縁もありこの日急遽、後輩たちにミニ講義をしていただきました。また、月桂冠大倉記念館では館長様の御厚意で、さかみずを無料で採取させていただきました(もちろん、御香宮神社でも、鳥せいでも、黄桜酒造でも、無料で採取できました。)。本当にありがとうございました。
この活動を通して、科学に対する興味関心を喚起するとともに、地元の環境や歴史を再考したいと考えております。
写真1枚目は御香宮神社にて御香水を採取しているところ。
写真2枚目は長建寺にて閼伽(あか)水を採取しているところ。
写真3枚目は月桂冠大倉記念館にて"さかみず"を採取しているところ。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
平成27年2月21日(土)10:00~ 視聴覚教室にて1年生 Global Science Basic 課題研究発表会
が開催されました。地球の磁場、過冷却、モーリッシュの死環、クレーターについて
英語で身振り手振りを交えて実験した内容を発表しました。
わかりやすく、すばらしいプレゼンでした。
最優秀賞にはgroup 7 Crators が輝きました。
多数の保護者にもご参加いただき、ありがとうございました。