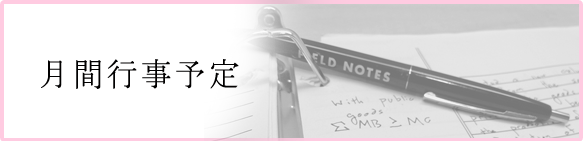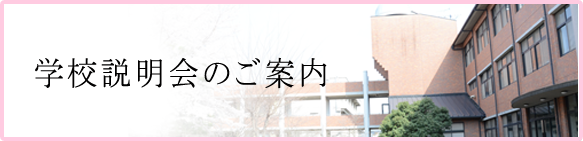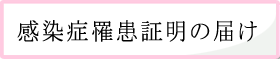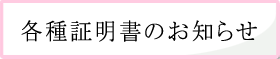6月11日(土),18日(土)に1年生自然科学科対象にSSH講座として「地球の歴史を化石から探る」が実施されました。
講師は京都教育大学教授 田中 里志 先生 です。
この講座では、巨椋池に堆積した粘土層から珪藻化石を抽出し観察することで、過去の巨椋池の古環境を探りました。最初、地学教室で先生の説明の後、プレパラートの作成をし、生物実験室に移動して顕微鏡観察をしました。
6月11日(土),18日(土)に1年生自然科学科対象のSSH講座、「水質を良くする微生物たちを観察する」を実施しました。京都学園大学 教授 金川貴博 先生 にお願いしました。
京都市域の水道水はほとんどが、琵琶湖の水です。琵琶湖の水には滋賀県の生活排水がはいっています。また、大阪の水道水は淀川の水で、京都をはじめ、上流の生活排水がはいっています。従って生活排水をしっかり浄化しなければなりません。下水処理施設では、微生物の力を借りて、この処理をおこなっています。この講座では、水の浄化に使われる微生物の塊である活性汚泥について学びました。
まずは金川先生のご講演のあと、生物実験室で活性汚泥の中にいる微生物を顕微鏡で観察しました。ツリガネムシ、繊毛虫類、ワムシ類、センチュウ類、有殻アメーバ類、クマムシなど、多くの動物と、細菌叢がたくさん見られました。さらに化学実験室に移動して、活性汚泥の沈降の様子をグラフ化する実習をおこないました。
その後のお話で、汚水中の有機物が細菌にとりこまれ、それを動物がエサとして食べ、これを魚が食べ、さらにそれを鳥が食べると、「山へ帰る」ことになるのだと教えていただきました。
京都教育大学 教授 沖花先生にもの物を分解して、その仕組みを知る理科学習(電磁誘導)の実験実習を下記日程で実施していただきました。
6月3日(金)6,7限 3年1・2組(普通科理系)物理選択者
6月 7日(火)6,7限 3年3組(普通科理系) 物理選択、
6月10日(金)5,6限 3年4組 (普通科理系) 物理選択者
釘を磁化し、これでIH調理器の磁場の様子を確認していきます。また、ストローに豆電球のリード線を巻き付け、豆電球が明るくつくようにするにはどのようにするとよいかを試行錯誤します。磁場の様子を想像し、IH調理器の内部の構造を予想し、正しいかどうかを分解することによって確認しました。生徒たちは自分で予想したり、考えながら仕組みを知ることができて、楽しかったようです。ありがとうございました。
6月1日(水)「空気電池の特徴を探る」というタイトルで京都教育大学 名誉教授 芝原 寛泰 先生に 2年自然科学科 8組(5限)、9組(4限)を対象に実験実習を実施していただきました。電池の活性化をはかる気体が何であるかを実験を通して、理解する内容で生徒たちは興味深く実験を行っていました。
2月6日(土)午後 京伏水学の一貫として、キンシ正宗製造部長の田中 明 氏の御指導のもと、キンシ正宗の酒蔵を見学させていただき、その後、伏見の水を6カ所でくんで学校に戻り、きき水をおこないました。きき水では、6カ所の湧き水と、水道水や超硬水との比較もしました。また、田中先生から伏見の水について御講演をいただきました。希望者対象。
「京伏"水"学」は、京都市伏見区の水環境と歴史を核とした学際的総合科学として、本校が提唱しているものです。
2月6日(土) 1年生8組9組の生徒が本校視聴覚室においてグローバルサイエンスベーシックの授業で取り組んできた課題研究の発表会をおこないました。発表はベルリッツから派遣していたネイティブの外国人の方々に御指導いただき、すべて英語でおこないました。
テーマは生物分野として「モーリッシュの死環」(樹木の葉に線香の火を押し当てると線香の火のあたったところを中心とし、酸化酵素の働きで円形に茶色く変色して輪が出来る現象)、物理分野として「ウォーターバルーン」(水風船をいろいろな高さから落とす)、化学分野として「過冷却」(凝固点を過ぎて冷やしても凝固せず、液体の状態を保つ現象)、地学分野として「月のクレーター」、数学分野「フェルミ推定」(調査するのが難しい現象を、いくつかの手がかりを元に論理的に推論する手法)がテーマとして与えられ、それぞれについて班ごとの工夫をして発表しました。
平成28年2月1日(月)(2年8組)2月8日(月)(2年9組)1限~3限、自然科学科2年生を対象に、京都教育大学 准教授 谷口 和成 先生をお招きし、実験実習講座 「科学的に考える」とは?を物理実験室にて実施していただきました。「トリッキーな軌跡」では足跡の図から、観察したことをグループで話し合い、発表し、事実と推測とを区別します。「ブラックボックス」では現象を見て、観察及び推測を述べ、現象がどのように起こっているのかを説明する仮説を立てます。また、その仮説を検証する方法を考えます。科学的に考えるとは仮説を立て、検証を行うことの繰り返しであることを学習しました。課題研究を行って来たので、イメージができ活発な議論ができたと思っています。
12月23日(水) 祝日、GS課題研究(2年自然科学科)の成果発表会が京都府総合教育センター 講堂棟で開催されました。
今年度は19班すべてが以下の発表タイトルで口頭発表を行いました。
1 マグヌス効果 -新たな変化球を求めて-
2 古宇治川の流れを探る
3 日焼け
4 クマムシの生態調べてみた。
5 真空パックの応用 ~保存と調理~
6 アリの味覚
7 偏光板
8 深層心理とサブリミナル効果
9 となりのゾウリムシ
10 薬と食品の飲み合わせについて調べてみた
11 ブラインシュリンプの孵化率向上を目指して
12 京都に眠れる水
13 光触媒と太陽光 ~水浄化への挑戦~
14 伏見の夜空 The darkness of the sky in Fushimi
15 最強の電池を探れ ~~
16 三足生物の歩き方
17 アリの生態 -アリの好むエサ、飼育を通してわかったこと-
18 数字で見る「目の付け所」
19 知られざるジャイロ効果の謎
20 呈色反応2015(高知県立高知小津高等学校)
今回も高知県立小津高等学校を招待し発表を行っていただきました。
奨励賞は以下の通りです。
7 偏光板
11 ブラインシュリンプの孵化率向上を目指して
17 アリの生態
18 数字で見る「目の付け所」
19 知られざるジャイロ効果の謎
ご参加していただいた教育関係者、保護者の皆様に、お礼申し上げます。
11月28日に開催された京都大学サイエンスフェスティバル2015―科学の頭脳戦―において、「バナナ果皮の"キリン化現象"からドーパミンの重合メカニズムをさぐる」が見事、京都大学総長賞を受賞しました。山極総長からトロフィーをいただく際、次のようなお言葉をいただき感激しました。「身近な題材を取り上げていて良かった」、「バナナのキリン化という着想が面白かった」、「研究途中であっても仮説をきちんと検証しようとしていた」、「チャレンジングな内容で素晴らしかった」、というような内容です。賞をいただくのが目的で研究をしている訳ではありませんが、このように見える形で評価をしていただけると、励みになると同時に自信になります。この研究は、まだまだ発展途上です。ユニークな研究へと成長させていきます。
なお、京都大学のフェイスブック(Facebook)に、発表時の様子や山極総長からトロフィーをいただく様子が紹介されています。
10月25日に開催された第12回 高校化学グランドコンテスト最終選考会にて、「バナナ果皮の"キリン化現象"からドーパミンの重合メカニズムを探る」が金賞を受賞しました。化学に特化した発表会であり全国から精鋭が集結していましたので、そのレベルの高さに圧倒されましたが、一生懸命発表することができました。なお、本研究発表の内容は、高校生・化学宣言という書物に掲載されます(予定)。