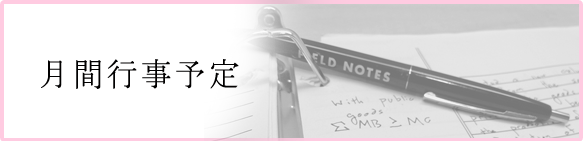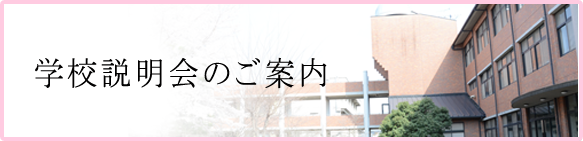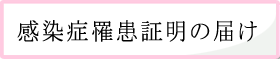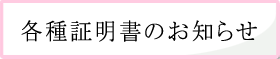12月24日~26日、茨城県つくば市において、桃山高校、京都教育大学附属高校、洛北高校、立命館守山高校が参加するつくばサイエンスワークショップが行われました。本校からは1年生4名が参加し、物理、化学、地学分野に分かれ、研究施設で実験・実習を行いました。最終日には、それぞれの研修内容をまとめた発表会を実施し、交流を深めました。
SSH課題研究発表会(自然科学科2年)が12月23日、京都府総合教育センター講堂棟で開催されました。舞台での発表は校内選考で選出された6チームと高知県立高知小津高校の計7本でした。いずれの発表も分かりやすく、とてもすばらしいものでした。また、ロビーではポスター発表(全18班、グローバルサイエンス部、小津高校)が行われました。写真は舞台・ポスター発表、表彰式の様子です。
SSHセンサープロジェクト
日時:12月13日(土)
場所:桃山高校物理実験室
講師:京都教育大学教育学部理科領域准教授 谷口 和成 先生
前半ではセンサーを設計するための基礎となる電位分割についての考え方を実習を通して教えていただきました。
また、可変抵抗と定抵抗を組み合わせた回路で定抵抗にかかる電圧がどのように変化するのかについても学習をしました。
後半では温度や明るさが変化すると電気抵抗が変わる素子を用いて生徒たちが設定した温度または明るさ(暗さ)で電子オルゴールが鳴り出すように定抵抗の値を決めて回路を作成しました。予定通りに鳴ったところや何回も修正してうまくいった班もありました。とても充実した授業になりました。
対象:2年自然科学科
11月25日(火)第2学年自然科学科の課題研究発表会(校内選考会)を実施しました。テーマごとに18班に分かれ、この春から取り組んできた課題研究の成果を発表しました。それぞれに実験や観察の工夫がみられ、研究活動に試行錯誤している様子が伝わってきました。選考会を通過したグループは、12月23日(火)に京都府総合教育センターで行われる課題研究発表会で口頭発表を行います。
11月15日(土)、京都工芸繊維大学にて、第2回京都サイエンスフェスタがあり、本校第2学年の自然科学科とグローバルサイエンス部がポスター発表を行いました。自然科学科の課題研究や、グローバルサイエンス部の日頃の研究成果など、他校の生徒とも交流を深めることができました。
11月8日(土)、一年生自然科学科と普通科SSコースは、京都大学の防災研究所を見学しました。地下街に水が流れ込むことを想定した流水階段や、浸水したドアの開閉など、実際の体験を通して、災害時の状況を知る事ができました。これらの経験を活かして、今後の防災に対する視点を養ってほしいと思います。
9月28日(日)
対象;希望者
SSH事業の一貫として毎年滋賀大学教育学部の 石川 俊之 准教授を講師とし、琵琶湖の湖上実習を実施しています。今年は参加者15名で実施しました。当日は絶好の天気でよい実習となりました。清流Ⅱに載せていただき南湖と北湖の観測点で気象、水質の観測とプランクトン採集などの実習を体験させていただきました。(写真1)後半風が強くなり、予定していた深層水を飲む体験を中止することになり、その点は少し残念でした。午後は採集したプランクトンの観察をしました。(写真2,3)
講師;長浜バイオ大学 高大連携事業推進室 黒田 智 先生
日時;10月14日(火)~16日(木)にかけて
対象;3年8,9組(自然科学科)生物選択生24名
白ブタ、茶色ブタ、黒ブタのどれかのDNAサンプルを一人ずつもらい、それをPCR法で増やして電気泳動法で鑑定をするという実習を行いました。
マイクロピペットなど大学で使用するような機材をすべて準備していただいて、本格的なDNA鑑定の実習をさせていただいたので、受講した生徒は研究者になったような気分を味わうことができました。のべ5時間にわたる実習を受講し、最後に一人ずつに修了証もいただいて、満足度の高い実習となりました。
8月30日(土)午後、小学生対象のおもしろ理科実験教室がグローバルサイエンス部の生徒の協力のもと開催されました。「空気で遊ぼう」ではブロアを使った演示実験で、ペットボトルやお椀を浮かせたり、傘袋を用いたロケットを作成し、飛ばしました。「植物の炭づくり」では松ぼっくりやししとうを缶の中に入れ、炭を作りました。子供たちは、とても楽しそうに実験をおこなっていました。写真は実験の様子です。
8月11日~13日に、SSH事業の一環で2泊3日の四国巡検を行いました。初日は、香川県藍住町で藍染め体験を行い、五色台で高知県小津高校と交流会を行いました。二日目は、五色台の地形調査や自然生物観察などのフィールドワークを行いました。最終日は、愛媛県今治市のタオル製造工場、タオル美術館を見学しました。