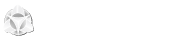令和7年7月18日(金)1学期終業式は熱中症対策の為、放送で行いました。
野村校長は式辞で、災害に備える心構えについて話しました。
震災後福島県を2度訪れ、
福島県立富岡高等学校の教員から様々な状況を聞き、
日頃から災害を意識して自分の命を守ることはもちろん、
地域の人達を支援するために何ができるのかを考えることの重要さを改めて感じた
自身の経験を紹介しました。
それをふまえ生徒達に、
夏休み期間は特に熱中症に注意して自然災害から十分自分の身を守ることと、
日頃から誰かの指示を待たないで、
自ら考え行動することを意識するよう伝えました。
式辞の後は、生徒指導部長中川先生と図書部長石丸先生の講話がありました。
7月10日に、全国大会に出場する生徒への、同窓会及び教育後援会からの激励金贈呈式が行われました。
◆全国大会
【ウエイトリフティング部】
第4回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技会(石川県)
個人 3年 木村 花凜
野村校長からは、全国大会への出場のお祝いと、これまでの努力に対する労い、また、大会では落ち着いて競技に臨み十分に力を発揮できるようにとの激励と期待の言葉が贈られました。
各出場者は感謝の気持ちや大会への抱負を語りました。
【ウエイトリフティング部】
日々サポートしてくれる先生や友人、家族への感謝を忘れず、これまでの集大成として力を十二分に発揮し、良い結果を報告できるように頑張ります。
大会出場者へのご声援をよろしくお願いします。
6月13日に、全国大会・近畿大会に出場する生徒への、同窓会及び教育後援会からの激励金贈呈式が行われました。
◆全国大会
【美術部】
第49回全国高等学校総合文化祭(香川県)
美術・工芸部門 3年 片畑 日茉梨
◆近畿大会
【ウエイトリフティング部】
第58回近畿高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会(和歌山県)
個人 3年 木村 花凜
【弓道部】
第78回近畿高等学校弓道大会(和歌山県)
個人 3年 箱崎 勇雅
個人 3年 山下 友愛
【体操部】
第79回近畿高等学校体操競技大会(兵庫県)
個人 1年 番家 小春
個人 3年 笹原 帆乃夏
野村校長からは、全国大会・近畿大会への出場のお祝いと、これまでの努力に対する労い、また、大会では落ち着いて競技に臨み十分に力を発揮できるようにとの激励と期待の言葉が贈られました。
各出場者は感謝の気持ちや大会への抱負を語りました。
【美術部】
全国大会出場において、温かい励ましや贈り物をいただきありがとうございます。
全国から集まる素晴らしい作品を観て学び、今後の作品製作に活かしていきたいと思います。
【ウエイトリフティング部】
日々サポートしてくれる先生や友人、家族への感謝を忘れず、これまでの集大成として力を十二分に発揮し、良い結果を報告できるように頑張ります。
【弓道部】
友人や先生から学んだ様々なことや自分が身につけたことを、近畿大会の舞台で全力で出して頑張ります。
また、支えてくれる家族や様々な方への感謝を忘れないように日々努力していきます。
【体操部】
3年生は悔いの残らないように、1、2年生は次に繋がる大会にしたいです。
大会出場者へのご声援をよろしくお願いします。