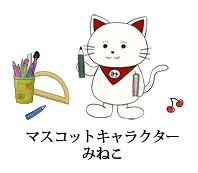学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 「食の影響」について考えたい!~...
「食の影響」について考えたい!~夢に繋がる一歩を~
食が私たちに及ぼす影響について探究している二人の生徒がいる。
彼女たちには共通の夢がある。それは、将来管理栄養士になることだ。
探究学習においては、活動しているうちに最初に立てたテーマの内容が変わることがしばしば起こるのだが、
彼女たちにいたっては、一貫して食に関するテーマを突き詰める姿勢を崩さなかった。
根底に「栄養職について視野を広げること」と「食がもたらす影響や新しい繋がり」を
探っていきたいという気持ちがあったからだ。
そもそもどうして、管理栄養士になりたいと思ったのだろう。
話を聞いてみると、二人の育った環境が食に対する興味を引くきっかけを生み出したことが分かってきた。
一人は、福祉施設を経営する両親の元で育ち、
食事の管理がいかに重要なものであるのかを身をもって知ったという。
自分が管理栄養士になれば、いずれ家族を支えることができる。家族思いの彼女の優しさに心が温かくなる。
もう一人は、母親が料理好きでたくさんの美味しい料理やお菓子を作ってくれたことが大きく影響している。
「母が楽しそうに料理を作る姿を見て、作ることにも興味が湧き気がつけば進んで手伝うようになった」
と話す彼女の顔は、何だかとても生き生きしている。
食が母と娘にとって大切なコミュニケーションの手段であった。
そして二人に共通しているのは、食べることも作ることも好きだということ。
だけど食べ過ぎても健康に良くない。そしてその逆もしかり。
「バランスのとれた食事を美味しく、楽しく健康的にとること」
その重要性を人々に伝えていくのも栄養管理士の大事な仕事だ。将来の目標に向けて、
一歩踏み出すための取組がスタートした。
活動のとっかかりとして、二人がヒアリングの対象に選んだのが
弥栄町でシェアスペース兼シェアキッチン「LINKU」を運営する福田透子さん。
面白かったのは、彼女たちが管理栄養士という職業だけに囚われずに幅の広い視点から
食を見つめようとしている点だ。
福田さんは管理栄養士ではなく、フードコーディネーターという立場で食に携わる仕事をしている。
フードコーディネーターは、「食」がテーマのビジネス全般にスペシャリストとして関わる仕事。
レストランのメニュー開発や食品メーカーの新商品の開発、
お店の食品売り場でのイベント企画や売り場改善など多岐にわたる。
また食べ物を作って提供することに止まらず、食器やグラスの選択、テーブルクロス、花一輪の添え方まで、
食の空間を作り上げる演出家としての能力も求められる。
福田さんは、自分が管理栄養士として食の大切さについて説いたり、
料理教室の講師として誰かに料理を教えたりするタイプではない、と話す。
そういった人たちが輝ける場を演出すること、そういった人たちを支える役割を担いたい、と。
福田さんのお話を聞くことで、いかに食の世界が広いのかに気づく彼女たち。
今までは、栄養バランスのとれた食事を作ることに重きを置いた考え方をしていたが、
違った角度から食を捉えることで、また新しい人の輪を生み出すことができることを知り、
益々食の可能性を感じるのであった。
その後、さらにもう一人に話を聞くことに。
地域の食材を生かした加工食品を開発する会社「丹後バル」を起業し、
管理栄養士としても活躍する関奈央弥さん。
彼女たちが一番気になるのは、やはり今後の管理栄養士の活躍の場について。
「関さんは、管理栄養士としてどんなことを大切にしているのですか?」
その質問に対して「私は食育こそ、国民一人ひとりの健康の質の底上げに必要な者であると考えています。
ただ食の大切さを伝えるだけではいけない。
その人のこれからの行動自体を変えられなければ意味が無いと思っています。
人の心を動かす食育というのをいつも心がけています」と関さん。
命あるものとして生きている限り、食は切り離すことのできないものであるからこそ、
全ての人に寄り添った形での食のサポートができるのが、管理栄養士の魅力の一つだという。
食と「美味しく、楽しく、そして健康的に」付き合うための提案をし、世の中を良くしていく存在。
命と向き合うため、責任は大きいがその分大きなやり甲斐のある仕事だ、と楽しそうに話す関さんの姿は、
きっと彼女たちの未来を明るく照らしてくれたはずだ。
彼女たちは、最終のゴールとして
「一人でも多くの人に食について興味をもってもらい、自分で健康管理が出来るような提案をする」
ことを目標としている。
そのためには、彼女たち自身がまず食に触れ、食を楽しみ、その奥深さを実感する必要があること。
そして、その楽しいという熱量を誰かに伝えられるようにすること。
伝える術は、いくらでもあるがまず何か、彼女たち自身が小さなアクションを起こすことを期待している。
どんなことだっていい。今まで自分たちが調べてきたこと、学んできたことを切り口に
「食にまつわる様々な逸話について掘り下げる座談会」を開催する、
生産者と消費者を繋ぐような取組を考えてみる、
栄養バランスのとれた料理を地域の人たちと実際に作ってみる...など、やり方は無限にある。
そして、そんなアクションを応援するために地域があるのだ。
将来、彼女たちが自分なりに考えた「新しい管理栄養士の形」を表現しながら
食の分野で活躍していることを願って。