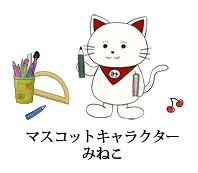学校生活School Life
- HOME
- >
- 学校生活
- >
- いさなご探究
- >
- 本屋に行けば医者がいる!? カフ...
本屋に行けば医者がいる!? カフェに行ったら薬剤師!? 「これから医療従事者たちは、地域に出る時代だ!」~地域で活躍する
○"ぶっとんだ"医師と薬剤師との出会い~出会いは地域の交流センターで~
始まりは、私が3年生の進路検討会議に参加させてもらったこと。
今の3年生はどうやら医療系の進学を希望する人が多い。今の状況も影響していそう。
でもこんな状況だから、現場での実習が中々できないし、とにかく生徒たちのそもそもの視野が狭いので、
何とか医療の現場で働いている人たちからリアルなお話を聞かせていただけるような企画を作ってくれないか。
3年生の学年部長を始めとして、担任団の先生方からそんなお願いをされたことがきっかけだった。
せっかく企画をするのであれば、高校生たちに面白い話を聞かせてあげたい。
え!?世の中にはそんな取り組みがあるの? 何で何で? どうして?
すごい! 面白そう!
人はこうした感情が生まれたとき、初めて他者の話に耳を傾ける。
「もっと知りたい」という感情が世界を広げてくれる。
だからこそ、よくある「現場の実情と課題、仕事のやりがい」みたいな話で終わらせたくはなかった。
「はい!それはぜひやりましょう。x.000
何としてでも"面白い現場の人"を連れてきます!」
そう啖呵を切ったものの、私は肝心な事を忘れていた。
「そう言えば私、"面白い"医療従事者の方とか知らんやん......」
困った私が向かったのは、京丹後市未来チャレンジ交流センター roots。
ここに行けば、たくさんの地域の方との交流が生まれるので、医療分野に関しても何かしらの繋がりができると思ったのだ。
そして、その予想は的中。
めちゃくちゃ面白い人たちに会ってしまいました!!
最初に出会ったのは、薬剤師の船戸 一晴さん。
確かrootsに本を寄贈しに来てくださったときに出会ったのが最初だった。
話を聞くと本業は薬剤師なのにDJをしたり、ラジオパーソナリティーをしたり、他にも色々と地域と関わりながら活動されているという。
どういうことだ!? すごくすごく面白いじゃないか!!
これは絶対に高校生にもお話を聞かせてあげたい。
そこでちらっと話を持ちかけてみた。
「あの~、今ですね、将来医療関係の方に進学を考えている生徒がたくさんいるのですが、現場のリアルなお話や、その面白い活動についてもしよろしければ、高校生たちにお話をお聞かせいただくことなどできないでしょうか...?」
「お!それは、それは嬉しいですね!ぜひ僕で良ければ!」
な、なんと!
本当に大人のみなさん、「高校生のためなら!」と動いてくださるので、
いつも感謝の気持ちでいっぱいです。
そしてさらに奇跡の出会いが。
その時、船戸さんが寄贈してくださった本が何冊かあったのだけど、その中の1冊が
『ケアとまちづくり、ときどきアート』だった。
「この本を書いている一人は、豊岡で面白い活動されていますよ〜」
そこで聞いたのが、守本 陽一さんの話だった。
普段はお医者さんなのに本屋やったり、屋台引いて町を練り歩いたりしているらしい。
そんなおもろい変わった人が世の中にはおるんやなぁ...なんて、その時は終わったのだけど、その数日後まさかのご本人に会うことになるのだ。
その日もたまたま用事があって、rootsに寄ったのだが、そこに守本さんがいた。
名刺をもらったのだが、そこには
「医師」と「ケアと暮らしの編集社代表理事」という肩書きが並んでおり、私の頭の中は?でいっぱい。で、よくよく話を聞いてみると
前回船戸さんからお話を聞いていた人のことだと気がついた。
あ、医師で本屋で屋台の人ね!!
そこで盛り上がったのが好きな出版社のこととか、
行ってみたい本屋、ゲストハウスの話で、めちゃくちゃ面白くて意気投合して...。
でも、これrootsで出会ってたからよかったなって。
もし、「医師」と「患者」の立場で出会っていたら、
きっと今友人の関係にはなっていなかったと思う。
やっぱり、出会う場所って大事だな、と。
そんな素敵な二人と出会った場所で、
医療関係に関心を持っている、その方面に進学を考えている高校生たち向けに
お二人をお招きして、「地域医療」を考える企画を実施できることになりました!
医療を地域全体で。
町をみんなで元気にする。
医療従事者たちは、これから町に出ていく時代だ!!
そんな風に考えて、素敵な活動をされているお医者さんと薬剤師さんのトーク。
絶対に面白い。
○イベントまでにゲストのお二人について知ろう!~活動に関する記事や取材記事を読む~
今回、ご協力をお願いしたゲストのお二人は名前を言えば「あ、知ってる!」と言われるような医療業界を始め、この界隈ではとっても有名な人たちで。
プロフィール
守本 陽一さん
一般社団法人ケアと暮らしの編集社 代表理事
公立豊岡病院組合立出石医療センター総合診療科医員
1993年、神奈川県生まれ、兵庫県出身。家庭医。学生時代から医療者が屋台を引いて街中を練り歩くYATAI CAFE(モバイル屋台de健康カフェ)や地域診断といったケアとまちづくりに関する活動を兵庫県但馬地域で行う。2020年11月に、一般社団法人ケアと暮らしの編集社を設立。社会的処方の拠点として、商店街の空き店舗を改修し、シェア型図書館、本と暮らしのあるところだいかい文庫をオープンし、運営している。共著に「ケアとまちづくり、ときどきアート(中外医学社)」「社会的処方(学芸出版社)」など。
船戸 一晴さん
京丹後市網野町生まれ。熊本大学薬学部卒。
新卒でゆう薬局グループ(京都市)へ入社し、薬局薬剤師として現在18年。
京丹後市での新店舗開局に併せて2008年に丹後へUターン帰郷。
音楽・映画・本・ラジオ好き。
2010年からFMたんごへ参加し、現在はFMたんご/FMまいづる2局で番組を担当。
DJとしては京都市内でのプレイ経験の他、ミツバチ朝市や丹後酒フェスなどイベントでDJプレイをおこなう。
今まで様々なメディアで取り上げられてきたということもあり、名前で検索を書ければああまたと記事が出てくる。そんなわけで、ある程度参加者には事前にお二人についての予備知識を入れておいてもらった方が、企画の進行がスムーズだろう、ということで、お二人の活動に関するいくつかの記事を読んできてもらい、それに関する感想と質問を一つずつ考えてきてもらった。
ちょうど中間テスト後だということもあり、課題を出すのには気が引けたのだが、流石は峰高生。参加希望者のほぼ全員が課題を提出してくれた!
さすが!! 意識がとても高い。
しかも、こちらの予想以上に感想をしっかり書いてきてくれて、本当に感動した。
ゲストのお二人にも事前に共有すると、驚かれると共にとても喜んでくれた。
○イベント当日
そして来る5月29日土曜日。
いよいよ企画が実施される日。今回の企画は、オンラインとオフラインを掛け合わせたハイブリッド型。rootsには5人の高校生が来てくれて、オンライン上には社会人の数名を合わせると20名以上の参加者が!! 関心度が高いテーマだということが分かる。
初めは医師の守本さんのお話から。
テーマは「小規模多機能な公共空間による新しいケアのカタチ」
今後、後期高齢者が増加していく中で医療と地域の繋がりを築いていかねばならない、という考えから「もっと日常に近いところ、暮らしの延長線上でのコミュニケーション」を生み出すための活動を精力的に実践されている。
それが「来る」「行く」「ある」のケア。
健康についてなど考える機会となるイベント、所謂「来る」取組はよく聞くが、面白いのは「行く」「ある」新しい形のケア。
医療従事者自らが病院を飛び出して、町を練り歩きながら自然と地域に溶け込む仕掛け(屋台を引いて珈琲を配る)「行く」ケアや医療に関わる人が文化的施設を地域で運営することで、気がつけば健康や医療について人々が考えるようになったり、そこに行けば文化的資本や人、地域と繋がりを持てる、その場に「ある」ケア(本屋の経営)の実践を地域の中で創り出しているのだ。
医療では治す「cure」も大切だが、人に寄り添う「care」については特に今後考えていかねばならない重要な視点であるという。
続いて薬剤師の船戸さん。船戸さんも守本さんと同じく、医療とそうではない分野の掛け合わせをすることで地域全体の健康意識を底上げさせる取り組みをされている。それが音楽やラジオといったカルチャーとの融合だ。日常の中に、町の中に自然にあるカルチャーの中にポンッと医療の話題が溶け込んでいることで「あぁ、これからそういったことも考えなきゃいけないよなぁ」と目が向くようになる。
そのほかにも出張講座やカフェやサロンの運営、異なる職種に就く医療従事者たちとの交流会などを通して、町全体の医療を充実させる。
様々な活動を通して船戸さんが大切にしていることは「地域の人と繋がり、繋げて、互いの顔が見える関係性づくり」をすること、「薬剤師だけでなく、地域の皆でケア活動」を行うこと、「行政の取り組み、地域薬剤師会活動への参加」を積極的に行ったりすることだ。
お二人の「地域を良くしたい!」という共通の想いは、間違いなく今後社会を変える第1歩となるだろう。
お二人のお話を聞いた上で、ある高校生からこんな質問が出た。
「僕も将来、地域と深く関わりながら働きたいと思っているのですが、人が集まる空間を
形成するために大切なことはありますか?」
その質問に対してまず守本さんは
「人を巻き込んで何かをしたいと思ったとき、一番大事にしたいのは"その集団から最も遠いところにいる人のケアがいかにできるか"ということかな。
関わりたい、といって自ら積極的にこちら側に入ってきてくれる人は良いけれど、関わってみたいけれどそこまでがっつりというわけでは...、というように人によって関わり方についてはグラデーションがあるので、その輪の一番遠い距離にいる人たちとの関わり方をきちんと考えてあげること。取りこぼさないようにすること。
それから、そのことに関係してくるんだけれど、"関わりしろ"をきちんと設けてあげることが大事じゃないかな。その人がどの程度の熱量で、どんな府に関わっていきたいと感じてくれているのかをきちんと把握をして、その程度に合わせて様々な関わりしろを作ってあげる。そうすることで、色んなタイプの人が気持ちよく参加してくれるようになると思う」
船戸さんは
「企画やコミュニティを作る際、自己満足にはならないように意識しているかな。
参加してくれる人が最終的にどんな風になってほしいか、を思い描きながら企画を立てるようにしているかな。他者の気持ちにまで想いを馳せることが大切だと思う」
グラデーションに合わせて関わりしろを作ったり、自己満足に終わらず相手のことを深く考えたり、関わる人が多くなればなるほど大変そうだが、コミュニティ作りはこれからの時代、とくに必要な要素となってくるだろう。
最後にお二人が高校生へ残してくれたメッセージ。
「勉強も遊びもしっかりやろう。何かに一生懸命取り組む行為が大切」
「好奇心を持って色んなことを知ろうね。同時に好きなことや趣味をとことん楽しもう。
そうすることで誰かの好きなことにも関心をもてたり、尊重できる人になれるでしょう」
また、選択肢が沢山あることも教えてくれた。
病院で働くことだけが正解ではない。こうして地域と深く関わりながら働くこと、行政に入ること、国際貢献するために海外へ行く道だってある。
◎参加してくれた生徒たちの感想
視野を広げて、自分だけの道を歩んでいってほしい。
それぞれの道でみんなが輝けますように。私たちはいつだって君たちを応援している。
最後になりましたが、ゲストのお二人に改めて感謝を込めて。
素敵な時間をありがとうございました。