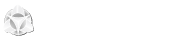2021/03/19
2021/03/17
3月15日(月)1年教養科学科の人文・社会学系統は京都府北部へのフィールドワークを実施しました。晴天に恵まれフィールドワークには最適な1日でした。
今回の目的は、京都府を南部から北部まで移動し、自分たちの住むこの京都の大きさを体感するとともに、北部の文化に直接触れることで、京都府を文化的な観点から俯瞰することでした。
他府県への旅行には出かけても、意外に京都府北部へは行ったことのない生徒も多く、京都府北部の景色は非常に新鮮だったようです。
伊根の舟屋を訪れましたが、知識としてはその存在は知っていても、実際に自分の目で見る経験はあまりできません。それも、今回は船上から伊根湾を周遊して、ガイドの方からの丁寧な解説までついていましたので、舟屋の歴史や背景がよく分かったと思います。次に世界ユネスコ遺産にも登録されている舞鶴引き揚げ記念館を訪れました。ここでは語り部さんと呼ばれている方が各班に付いていただき、展示品の説明から引き揚げについての物語を、文字どおり語りかけてくださいました。
生徒たちはそもそも引き揚げとは何かということから始まって、現代日本が成立する以前の日本の歴史について、資料と共に直接理解をすることができたのではないかと思います。
最後は舞鶴湾を見下ろす高台に登って全員で記念撮影をおこないました。京都府北部の景色に癒やされ、また近代の歴史を実感した、密度の濃い1日になりました。
2021/03/16
2021/03/16
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/14