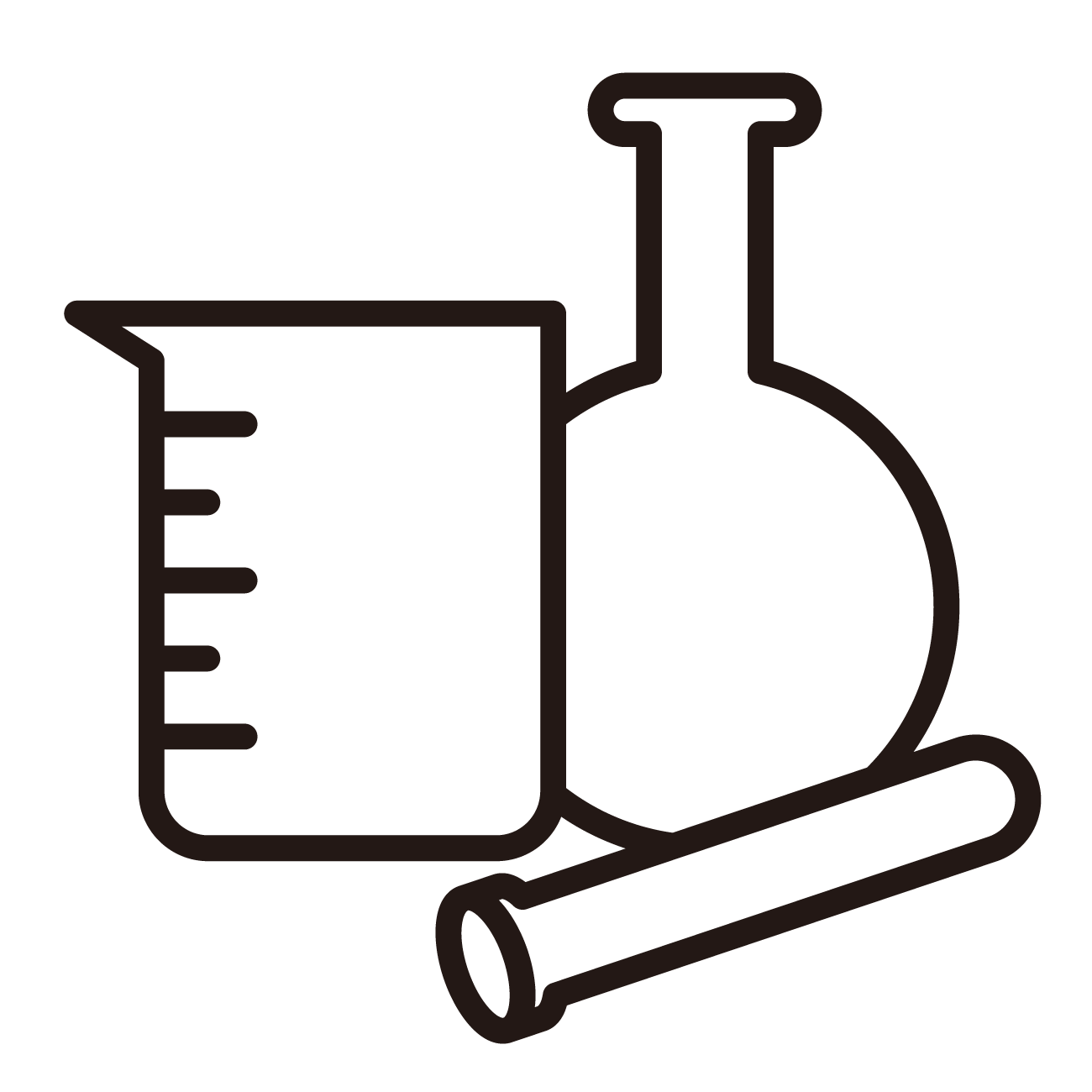自然科学部は、高校生22名(1年生6名、2年生7名、3年生9名)、中学生9名で、毎週月・水・金に地学実験室で活動しています。昨年度は、令和5年度に引き続き、生物班、物理班、情報班に分かれてそれぞれの探究活動を進めました。
生物班は、トビムシ類やダニ類などの土壌動物を、今年度導入したツルグレン装置を使って調べました。岳南グラウンドの山間部の土壌と、第一グラウンドの乾いた土壌の違い、雨天時・晴天時の違いを調べました。定量評価に課題が見られたため、今年度は目的を明確にして調査していきたいです。また、令和5年度より、環境DNA解析による由良川の魚類群集調査を実施しており、昨年度は由良川下流域を中心に調査を行いました。2年間の研究成果をまとめて、10月に日本水産学会秋季大会でポスター発表を行い、最優秀発表賞(1位/22校)を受賞することができました。さらに、11月に環境DNA学会つくば大会でオンライン発表を行い、最優秀賞(1位/12校)を受賞することができました。研究の過程も重要ですが、成果をまとめてどのように発表するかなど、表現力の重要性も再認識することができました。
校外活動としては、夏休みに西はりま天文台における天体観測を昨年度も実施しました。あいにくの天気で、日本最大級の望遠鏡で壮大な夜空は観測できませんでしたが、飯盒炊飯などを楽しむことができました。また今年も「由良川のサケ放流事業」に参加し、発眼卵から稚魚になるまで校内でしっかりと育て、3月には由良川に放流する予定です。
昨年度は、カイコ幼虫の飼育にも挑戦しました。綾部市を中心に栄えた、かつての養蚕業の文化に触れることができました。カイコ幼虫の飼育、特にエサとなる桑の葉の確保が大変でしたが、中学生と高校生が一体となり、全校体制で取り組むことができたのは、大変よかったと思います。これからも中学生と高校生が一緒に取り組めるようなイベントを考えていきたいと思います。
自然科学部全体では、生物系の探究活動は一定の活動成果が見られましたが、物理班のムペンバ実験、情報班のプログラミング探究については、発表できる成果が乏しいので、今年度は積極的に活動していきたいと思います。3年生の中には、探究活動の経験を大学入試の総合型・学校推薦型選抜に生かすなど、自身の希望進路実現に絡めることができました。今後も、生徒の主体性を大切にしつつ、校外発表でも通用するハイレベルな探究活動を進めていきたいと思います。
【自然科学部】学会発表で最優秀賞受賞など(2024年度の活動)