10月8日(水)に、6年生が校外学習に出かけました。今回の学習の目標は、「福知山の発展に尽くした明智光秀の功績や歴史の様子を知り、地域に住む一人として、地域を大切にする気持ちを育む。」です。訪問先は、猪崎城跡、福知山城、蛇ヶ端御藪(明智藪)、金刀毘羅神社、御霊神社でした。
まず、城山にある猪崎城跡へ行きました。猪崎城は、織田信長に丹波平定を命じられた明智光秀が攻略した塩見氏の居城でした。小高い山上に築かれた山城で、中核部分の主郭(近世城郭でいう本丸)は、東西約45m・南北約50mあります。



現在も多くの遺構が残っており、1学期に登った友渕城(西の古城)とはまた違った趣がありました。(友渕城についての記事は、令和7年7月4日「6年三和創造学習 西の古城に登りました | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」をご参照ください。)猪崎城の土塁(敵の侵入を防ぐ城壁)や曲輪(城域を形作る平坦な区画)、矢倉台は、明確に判別できるくらい残っていました。特に土塁は、たとえ大軍が攻め上ってきたとしても、少人数で容易に撃退できるという気持ちにさせられました。






山城は、領国への侵入者をいち早く発見するために高い場所にあります。よって、見晴らしがいい!猪崎城も例に漏れず、福知山市内を一望できるほどの見晴らしでした。此岸、対岸の山々には、塩見氏の城が点在していたとのことで、改めて戦国の世は、平素から戦闘に備えていたのだいうことが分かりました。



次に、バスで福知山城へ行きました。戦国時代に明智光秀が丹波平定を果たしてから取り組んだ治水事業は、福知山の人々にとってとても大きな出来事でした。光秀は、「暴れ川」由良川の洪水を防ぐために、大堤防を築いて川の流れを90度変えました。それが蛇ヶ端御藪です。その大事業が成される前は、由良川が現在の福知山城下から市内へ流れ込んできていました。光秀の治水事業が、後の福知山の発展につながったのです。
天守閣からは、対岸の猪崎城、これから向かう蛇ヶ端御藪を臨むことができました。こうして上から確認してから、徒歩で蛇ヶ端御藪へ向かいました。



藪の中には、竹をはじめ、様々な木々が生い茂っていました。今でも福知山市街を水害から守ってくれているのだと思うと、光秀の偉業を強く感じました。
京街道から福知山へ入る南の玄関は、京口門という門が築かれ、24時間体制で警備されていたそうです。門の西側には、番所が置かれていました。京口門は、洪水の度に濁流が押し寄せることから、川の監視所も兼ねていました。
丹波と京を結ぶ要衝である福知山は、由良川水運が発展の原動力となりました。上船渡口、下船渡口を確認しながら堤防を歩きました。
音無瀬橋を越えて寺町の金刀毘羅神社に来ました。金刀毘羅、金刀比羅、琴平、事比羅、金比羅…と称される神社は、香川県の金刀比羅宮を総本宮とし、大物主神を祀っています。商売繁盛や水難よけなど、いろいろとご利益のある神で、親しみを込めて「こんぴらさん」と呼ばれることがあります。江戸時代に船運が盛んになり、その信仰が広まると、日本各地に分社が建てられました。福知山市の金刀毘羅神社は、由良川の丹後口門近くにあります。鳥居横には、かつて番所があったそうです。



神社前の道路は、カクカクと屈曲しています。これは、「遠見遮断方式」と言われるもので、城下町の防護策の一つです。道を屈曲させることで、侵入してきた敵は、先が見えづらいのです。
玉垣には、「大阪御堂筋 上村重助」といった問屋の名前が記載されていました。事前学習で学んだ大阪との関連をここに見ることができました。(事前学習についての記事は、令和7年10月8日「6年三和創造学習 校外学習事前学習を行いました | 福知山市立三和小学校・三和中学校(三和学園)」をご参照ください。)



バスに乗車し、明智光秀が祀られている御霊神社に着きました。光秀には、主君である織田信長を倒したことから逆臣のイメージがあります。しかし、由良川の氾濫を防ぐ堤防を築き、城下町建設に当たり地子銭(土地税・住宅税に相当)を免除するなどの善政を行いました。朽木植昌が福知山城主だった宝永2(1705)年、植昌は、現在の福知山市商工会館付近にあった榎の下の稲荷神社に、光秀の霊を合祀しました。それまでは、宇賀御霊神を祀る稲荷神社と、光秀を祀る菱屋町の常照寺と分かれていました。稲荷神社は、光秀を合祀したことから「御霊神社」と呼ばれるようになりました。御霊神社は、広小路の拡張に伴い、大正7(1918)年、現在の地に移設されました。



本殿北脇には、恵比寿神社があり、さらに北側には、堤防神社があります。福知山は、豊かな由良川の流れに多大な恩恵を受けてきました。しかし、由良川は、時として大洪水となり、流域の人々に大きな災害をもたらすことが度々ありました。そこで、治水事業を着々と進めていったことで、次第に水禍から遠ざかっていきました。堤防神社は、治水事業の進展と堤防の愛護と感謝、そのよりどころとして昭和59(1984)年に建立されました。堤防が御神体となっている神社は、全国でも非常に珍しいとのことです。洪水との縁が深い福知山ならではの神社です。



本殿北脇の恵比須神社は、御神体が、光秀の筆による「和久左衛門太夫長利追及下知状」(福知山市指定有形文化財)です。現在、恵比寿神社には、全部で5柱が祀られています。中でもユニークなのが、大正4(1915)年に京都太秦の「蚕ノ社」と呼ばれる木嶋坐天照御魂神社より養蚕大神を迎えて合祀していることです。恵比寿神社の脇には、「蚕乃社」と彫られた石柱が建てられています。福知山で養蚕がいかに大切にされてきたかがうかがえます。


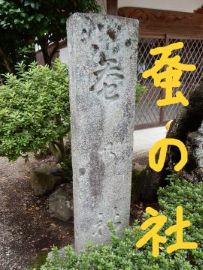
この後、短時間自由に見学する時間が与えられました。その時に子どもたちの心を捉えたのが、堤防神社の西側にある叶石でした。この石は、「子持ち石」とも呼ばれており、この神社に奉納された霊石であるとのことです。悲願成就の霊験を讃え、誰言うとなく叶石と呼ばれるようになったそうです。多くの子どもたちが石の前で手を合わせていました。



神社前の御霊公園には、昭和28(1953)年9月の台風13号による被害を後世に伝えるために、市街地を覆った水の水位20m69cmを記した標識が建てられています。自分たちの頭上を遙かに超える水位に、子どもたちは驚いていました。
蛇ヶ端御藪、光秀を祀る御霊神社、浸水位標識、堤防神社。これらを結ぶことで、明智光秀が治水事業に力を注いでいた理由、そして、福知山に残した功績を実感することができた半日でした。今回も大変勉強になりました。吉田先生、ありがとうございました。


