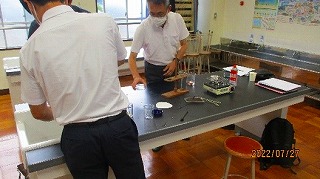令和4年度 第1回理科部会活動報告
1 研究主題
『主体的に問題解決に取り組む児童の育成』
~わかる・できる・つながる理科教育づくりを通して~
2 活動報告
1)日時・場所
令和4年7月27日(水)13時~ 南丹市立八木西小学校
2)内容
・令和4年度 活動方針・計画について
・講義
「全国学力・学習状況調査からみえる授業づくり」
講師:京都府南丹教育局 指導主事 松岡 里佳 様
・実技研修
「梅干しから白い塩を取り出そう」
3)講義にて
・「自然の事物・現象をどのような視点で捉えるか」について、量的・関係的な視点、質的・実体的な視点、多様性と共通性の視点、時間的・空間的な視点で、理科における「見方」を明確にすることができた。
・「問題解決の過程において、どのような考え方で思考していくのか」、比較、関係付け、条件制御、多面的に考えることの大切さを再認識することができた。
・令和4年度全国学力・学習状況調査「理科」小学校6年、中学校3年生の問題を実際に解くことで、求められている力や授業作りの視点を捉えることができた。その中で、子ども達の思考をどのように活性化させるのか、ディスカッションをうながす授業を展開することの大切さを学ぶことができた。
4)実技研修にて
・科学的な問題解決能力を養う実験の一つとして活動したが、「習得した知識等をもとに仮説を立てる」や「仮説検証のための実験を考案する」や「考案した実験を実践し、結果を分析する」ことの大切さを実感することができた。
・失敗の実験結果から、「なぜ?」「どうしたらいいのか?」など、問いが継続する授業展開の大切さも感じた。
令和4年度 第2回理科部会活動報告
1 研究主題
『主体的に問題解決に取り組む児童の育成』
~わかる・できる・つながる理科教育づくりを通して~
2 活動報告
1)日時・場所
令和4年10月5日(水)13時40分~16時30分 南丹市立八木東小学校
2)内容
・授業研究 5年「雲と天気の変化」
授業者:南丹市立八木東小学校 山内 誠 教諭
・実践発表 3年「風とゴムの力のはたらき」実践のあゆみ
発表者:京丹波町立瑞穂小学校 田中 敏夫 先生
3)公開授業・事後研究会
・実験や観察において目的を児童に認識させるだけでなく、目的(今回では、天気の変化の仕方のきまりを見つける)を達成するためにどのような情報が必要なのか、児童自らが考える授業展開は大切である。
・興味や関心がもてるように、教師がどのような情報を集めるのか教材研究に努め、児童が探究したくなる発問をすることが能動的な学びにつながる。
・児童の考えを出発点とすることで、グループ交流では自分の考えを分かりやすくタブレットを用いて説明したり、考え直したりする姿が見られるなど、主体的な学びとなる。
・雲の動きや変化の様子を記録に残し、天気の規則性について考えの根拠を伝えるツールとして、ICT機器は有効である。
・単元を通して身につけた天気に関わる知識や技能を学校生活や日常生活の中で活用できるようすることも大切である。
4)実践発表
・単元導入時には、これまで体験したことを話したりや動画を見たりすることで児童の興味や関心を高めることが大切である。
・遊びを通して、実感を伴って学ぶことができるようにするとともに、記録をしながら科学的(量的・関係的視点)に追究させ、実験から得られた結果を考察させることが大切である。
・遊びや活動の中で感じた疑問点や確かめたいことを実験するためには、より正確に調べる方法や確かなデータが必要であることを押さえることで、比較する条件を整えていく。
1 本年度の成果と課題
(1) 成果○夏季研修会より
<講義>
・「自然の事物・現象をどのような視点で捉えるか」について、量的・関係的な視点、質的・実体的な視点、多様性と共通性の視点、時間的・空間的な視点で、理科における「見方」を明確にすることができた。
・「問題解決の過程において、どのような考え方で思考していくのか」、比較、関係付け、条件制御、多面的に考えることの大切さを再認識することができた。
<実技研修>
・科学的な問題解決能力を養う実験の一つとして活動したが、「習得した知識等をもとに仮説を立てる」や「仮説検証のための実験を考案する」や「考案した実験を実践し、結果を分析する」ことの大切さを実感することができた。
〇研究授業・実践発表より
<研究授業>
・実験や観察において目的を児童に認識させるだけでなく、目的を達成するためにどのような情報が必要なのか、児童自らが考える授業展開は大切である。
・グループ交流では自分の考えを分かりやすくタブレットを用いて説明する姿が見られたように、考えの根拠を伝えるツールとして、ICT 機器は有効である。
・単元を通して身につけた知識や技能を学校生活や日常生活の中で活用できるようにすることも大切である。
<実践発表>
・遊びを通して、実感を伴って学ぶことができるようにするとともに、記録をしながら科学的(量的・関係的視点)に追究させ、実験から得られた結果を考察させることが大切である。
(2) 課題
・研修会では、授業で使った実験器具や教材などを交流する機会にすることも検討する。
・学習終了後、学んだことを生活の中でどのように生かせるのか、また効果的に生かせる場面をどのように設定するのかなど、つながりのある学びについて検討する。
2 次年度への申し送り
(1)授業研究会について
・科学的な見方・考え方を伸ばし、問題を科学的に解決する授業の在り方の追究や主体的・対話的で深い学びの充実など、学習指導要領のポイントに即した授業づくりについて追究していく。
(2)夏季研修について
・教師自身が関心や意欲を高め、安全で正確な実験を行う技量を身に付けるために実技研修を継続していく。
・それぞれの部員がもっている知識や技能を生かした研修を検討する。
令和3年度
第1回部会報告
【日時】 令和3年7月28日(水)13:30~17:00
【会場】 南丹市立美山小学校 参加者 15/19名
【内容】
1挨拶・自己紹介
2協議
・副部長の委嘱
・本年度の研究テーマについての確認
・研究活動(活動の重点)についての確認
・研究部会の計画の確認
3研修会
・講義(13:40~14:30)
「主体的・対話的で深い学び」を実現する理科の授業づくり
府小研研究協力校(令和2年度研究発表)の実践に学ぶ
講師:舞鶴市立明倫小学校 教諭 猿橋 健志 様
教諭 川端 健介 様
・実技研修(14:40~16:40)
「理科観察・実験の実技研修」
「由良川水系の指標生物による環境調査」※出合橋下
【研究の成果】
・教師自身が「理科」を楽しみ、「理科のおもしろさ」を引き出す授業づくりの在り方や科学的な見方や考え方を見いだす授業づくりを問題解決の過程を工夫し設定することが大切であることを学ぶことができた。
・新学習指導要領の考え方に基づいた、児童の気付きや疑問を生かすための手立てを先進的な取組について情報共有できた。・フィールドワークを通して、野外観察に必要となる指導の視点を見いだしたり、観察の技能を高めたりするとともに、観察・実験を通して体験的に学習すること重要性を再認識することができた。
令和元年度
第3回 理科部会 報告
令和元年11月20日(水)に南丹市立八木西小学校において、第3回理科部会を行いました。内容は、公開授業、事後研究会、実践発表、実践交流でした。
1 授業研究会:第3学年「電気で明かりをつけよう」
「電気を通すものと通さないものについて自分の考えを表現することができる。」が本時の目標でした。
児童は、提示されたものを見て、電気を通すか通さないかを予想し、理由も明確にして積極的に発言していました。また、グループで協力して実験を行い、予想とは違った結果が出た際には、驚きの表情を見せていました。1時間の授業を通し、意欲的に学習に取り組んでいました。
2 実践発表:「流れる水のはたらき」について
実際に授業で使用された実験装置を紹介しながらの実践発表でした。その後の実践交流では、指導者が難しいと感じる理科の実験について交流し、正確に実験をするにはどうすればよいか協議できました。