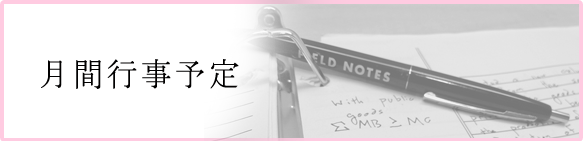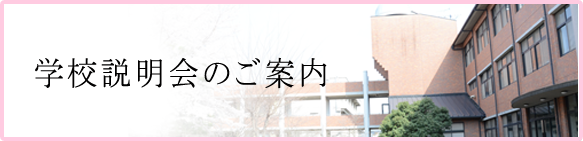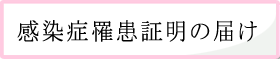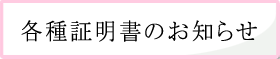今年は桜の開花が予想よりも急に早くなり、本校中庭の桜は3月19日の修了式に開花してしまいました。
修了式では、桜の開花に触れて、桜は夏に花芽が形成されたあと休眠し、寒い時期を越して気温の上昇により開花すること。
人も外からは見えないけれど、しっかり準備して貯えたものが節目の時に花開くというお話をしました。
今年は2月までが寒かったため梅の開花が遅れ、急に暖かくなったため桜の開花が早まり、梅と桜が同時に咲くという珍しい光景になりました。(ニュースでは30年ぶりと言っていました)
卒業式の式辞を考えるとき、「梅の香りが漂い...」と始めようとすると、3月1日に梅が全て散ってしまっている年もあれば、満開の年もあり、その年の様子をみて式辞の冒頭を変更しています。
ところで、「おもしろ気象学」の著者 倉島 厚 さんは、その著書の中で春の植物の開花について、次のように述べておられます。
「東京や大阪では梅の開花は2月、桜3月末、藤が5月はじめというのが平均で、梅の開花から藤の開花まで約3ヶ月かかる。
それが新潟県あたりにいくと、1月半に縮まり、北海道ではこれらの花がみんな同時に咲くのです」。
桜の開花前線は1月下旬に沖縄を出発し次第に北上します。
そしてゴールデンウイークの頃、津軽海峡を渡り北海道にたどり着きます。
北海道では、東京や大阪などで3ヶ月かけて順に咲いていく花が一斉に花開き見事な光景になるそうです。
これが「北国の春」なのだそうです。
是非一度その時期に行ってみたいと思っています。
桃山高校では、昨年ちょうど入学式の頃桜が満開でした。
今年は散ってしまいそうで少し残念です。
中庭をはじめ40本以上の桜があり見事な光景となります。
1号館2階の職員室や3階の教室からの眺めは最高です。
日が落ちると街灯に照らされ夜桜が仕事の疲れを癒してくれます。
桃山高校ならではの楽しみです。
3月29日、八分咲きの桜に誘われて校内(中庭)を歩くと、ウグイスの囀りが聞こえてきました。
2月下旬の土曜日中庭の桜の木の蕾は固く、メジロの群れが戯れていました。
この気温からすれば、今年も入学式には満開の桜が入学生を迎えてくれるものと思っていましたが...。
自然の変化はなかなか予測できないものです。
週間予報までは、そこそこ予測できても中・長期予報は、まだまだ難しいものですね。
桃山丘陵の四季の変化はなかなか情緒があります。
そうした自然の豊かさや美しさを入学する1年生にも感じてほしいと思っています。
京都府立桃山高等学校全日制課程 平成24年度 第65回卒業証書授与式 式辞
厳しい寒さもようやく和らぎ、光の中に春を感じられるようになりました。
梅もようやく開花をはじめたこの佳き日に、第六十五回卒業証書授与式を挙行いたしましたところ、お忙しい中を多くのご来賓の皆様並びに保護者やご家族の皆様方のご出席をいただき、卒業式を挙行できますことを、教職員一同大変嬉しく思っております。
厚くお礼申し上げます。
ただいまは、356名の皆さんに、卒業証書を授与いたしました。
保護者の皆様方には、お子様が、本校での三カ年の課程を無事修了され、本日の晴れの卒業の日を迎えられましたこと、さぞ、お喜びのことと存じます。
教職員を代表し、心からお祝い申し上げますとともに、本校にお寄せいただいたご理解とご協力に対しまして、深く感謝を申し上げる次第でございます。
卒業生の皆さん、ご卒業誠におめでとうございます。
みなさんにとっては、ついこの間、桃山高校の門をくぐったという思いがあるのではないでしょうか。
皆さんは、教科の学習はもとより、ホームルーム活動や部活動、学校行事等を通して、友達や先生と交流を図り、心と知識を育みながら、多くのことを学んだことでしょう。
皆さんは今日を境に、それぞれの道に進んでいくわけですが、高校生活で学んだことを糧として、確かな足取りでこれからの人生を、歩んでほしいと思います。
それでは、卒業にあたり皆さんの前途を祝し、私の思いを述べさせていただいて、餞の言葉にしたいと思います。
「宇宙は数学の言葉で書かれている」近代科学の父と言われるガリレオ・ガリレイは1623年の著書にこう記しました。
宇宙で起きる出来事は、みな数式で表現できるルール、すなわち法則に支配されているとガリレオは考えたのです。
ガリレオの時代から、科学者たちは観察と実験と思考を重ね宇宙に潜む様々な法則を解明してきました。
そして、昨年7月、物が持つ質量の起源として1960年代に存在が予言された「ヒッグス粒子」とみられる粒子を発見したという発表がありました。
宇宙が生まれたとき、あらゆる粒子は質量を持たず光の速さで飛んでいましたが、空間を満たしたヒッグス粒子の抵抗を受けて動きにくくなり、その動きにくさが質量につながったと考えられています。
その質量を持った物質で私たちの体もできています。
宇宙の中で私たちに見えているものは、僅か4%で、残りの96%は、まだ正体不明のダークマターやダークエネルギーと呼ばれる見えないものでできています。
この見えないものが何であるかはまだわかっていませんが、ヒッグス粒子の存在が明らかになれば、この見えないものが何であるかが解明される日も近いのではないかと考えられます。
私たち人間は、宇宙の中の一つの存在です。
私たち人間にも見えているところと見えていないところがあります。
数式で表現できるかどうかは、まだ、わかりませんが、私たちの生き方にも法則のようなものがあるように思います。
それは、周りの人の存在があって自分の良さが活かされるということです。
「情けは人のためならず」という言葉があります。
情けは人のためではなく、いずれは巡り巡って自分に返ってくるという諺です。
人のため社会のために何ができるかを考える生き方こそ自分が活かされ成長できることになるはずです。
「立場は人が求めるものではなく、立場が人を求めている」という言葉もあります。
皆さんも自分だけが良くなりたいと考えるのではなく、しっかりと学び、周りの人や社会の中で活かされ、役に立てる存在となることを目指してほしいと思います。
司馬遷の史記に「鶏口となるも、牛後となるなかれ」という言葉があります。
「大きな団体や組織の中にいて、ついて行くことよりも、たとえ小さな団体や組織の中でも、先頭に立っていくほうが良い」という意味で使われています。
現在の社会は、厳しい経済状況の中にあります。
一般的に、売上高や営業利益が高い企業が賞賛され、取り上げられることが多いですが、「日本で一番大切にしたい会社」という本の中で、著者の坂本光司さんは、あまり目立たなくても、利益をあげながら素晴らしい社会貢献をしている企業を取り上げています。
働くことの意味、会社という存在の意味を深く教えてくれるとともに、喜びを感じて働く社員の姿があり、胸を打つ現実のストーリーが描かれています。
これからの社会を支える皆さんが、先頭に立って、桃山高校で培った力によって、少しでもよい社会、明るい世界が作り出せるよう、それぞれに努力して活躍されることを期待しております。
現在の社会は、変化のスピードが速く、情報が溢れています。
その中から正しい知識をしっかりと身につけ、的確に判断し、活かしていくことが必要です。
学ぶときには、安易にインターネットに頼るのではなく、古典や名作などにより自分の知識や考え方を見直したり、社会の常識、科学の知見などをもとに自らの考えを検討することも大切にしていただきたいと思います。
人類の歴史は、自然災害とその復興の歴史でもあります。
特に阪神大震災以降、地震の活動期に生きることとなった私たちは、地震、気象など自然の仕組みをしっかりと学び様々な場面で的確な判断をする必要があります。
地球規模で発生する自然災害を止めることはできません。
しかし、しっかりとした知識を学び備えを行っておけば被害を小さくすることはできます。
これからの科学技術の進歩とともに自然現象や防災に関する知識を私たちは学び続けていかなくてはなりません。
皆さんの高校での学びは終わりますが、社会人となっても学び続け自然と人間との共生を考え続けてほしいと願っています。
私が座右の銘としているサミュエル・ウルマンの詩「青春」には「青春とは人生のある期間をいうのではなく、心の様相をいうのだ」という言葉があります。
「年を重ねただけで人は老いない。
理想を失うときに初めて老いが来る」とも言っています。
これはウルマン八十歳の時の詩です。
どうか皆さん、いつまでもプラス思考で明るく前向きに、喜びと感謝を持ちながら生涯学び続ける気持ちを忘れず、健康に留意し、この桃山高校で学んだことを基礎にして、「あせらず、あわてず、あきらめず」これからの人生を粘り強く、したたかに、また、しなやかに生きてほしいと思います。
それでは最後になりましたが、保護者の皆さまには、重ねてお祝いを申し上げ、卒業生の新しい旅立ちをともに暖かく見まもりつつ、皆さんの前途のご健康とご活躍と、そしてご多幸を心からお祈りいたしまして式辞といたします。
平成25年3月1日
京都府立桃山高等学校
校長 滋野 哲秀
「秋の野に、咲きたる花を、指(および)折り、かき数ふれば、七種(ななくさ)の花」
山上憶良
※ 秋の七草:萩(ハギ)・桔梗(キキョウ)・葛(クズ)・藤袴(フジバカマ)・女郎花(オミナエシ)・尾花(オバナ/ススキのこと)・撫子(ナデシコ)
9月25日火曜日 大きな行事である体育祭が無事終了しました。
先に終了した文化祭を含め、多数の保護者の皆様にもお越しいただき厚くお礼申し上げます。
「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉どおり、今年も秋分の日前後を境に朝夕はさわやかになりました。
体育祭当日も日中は暑くなったものの熱中症や大きな怪我もなく競技が進み、生徒の歓声がこだまし、競技の態度や声援を送る姿に桃山高校生らしい頼もしさを感じつつ成功裏に終えることができました。
体育祭前日まで早朝からクラスごとに大縄飛びの練習をする光景が校内のあちこちでみられ、文化祭・体育祭を通してクラスのまとまりがより深くなったことと思います。
高校の文化祭は9月のはじめに実施する高校が多く、夏休みから取り組みが本格的にはじまり体育祭でこのクラスづくりに欠かせない大きな行事が閉幕となります。
お盆を過ぎた夏休み、校内のあちこちで進学補習の合間に文化祭の演劇の練習に励む三年生の声が聞こえ、通りすがりにそっと眺めると、台本を持ちながら台詞覚えの練習をしていました。
毎年繰り返される光景です
が、こうした行事を取り組む中で人間的にも大きく成長していく姿をみると学校の持つ役割の大きさをしみじみと感じます。
練習の始まった暑い夏から、体育祭までの毎日、練習を終えて帰る生徒を見送る西の空は次第に日没が早くなり、いつしか鮮やかな夕焼け空のグラデーションが錦秋の到来を告げていました。
春に芽を吹き、夏を越して実りを迎える植物のように、生徒たちにも夏を越えて大きな実りがあったことでしょう。
秋分の頃に咲くヒガンバナ。今年は暑かったため少し開花が遅れているようです。
桜前線のようにヒガンバナ前線があっても面白いな。と思います。
そういえば、右の写真の「ゼフィランサス」という植物は、ユリ目ヒガンバナ科で私の好きな花です。
所用があって本校のお隣にある京都府総合教育センターに出かけた際、通路横に咲いているのを見つけま
した。
「ゼフィランサス」とはラテン語で「西風の花」梅雨の頃から秋まで、開花時期は長く、写真の右の方にある蕾が下から伸びてきてピンクの愛らしい花を咲かせます。
ひっそりと咲いているため足を止めて眺める人は少ないかもしれません。
同じヒガンバナ科にもこんな可愛い花があります。
8月10日(金)都市部で気温が高くなるヒートアイランド現象の調査に行ってきました。
大住中学校の生徒14名と本校グローバルサイエンス部の生徒11名、さらに気象予報士会学生会の協力による共同観測です。
この調査のきっかけは、ともに気象予報士の資格を持つ大住中学校の阪本先生(理科)と本校の村山保先生(理科)が日本気象予報士会の研修会で出会い、気象予報士会関西支部の学生会員も協力してくれて実施することとなったものです。
多分、気象予報士会としても全国初の試みです。
私も気象予報士の一人として調査を見てきました。
この日は、晴れて気温が上がり京田辺の 15 時のアメダスは近畿で最高の 35 ℃でした。
(下の紫色で 35.0 と表示されているところが京田辺)
正午から午後3時まで、本校の生徒が気球を上げて上空8kmまでの風向を測定し、同時に11カ所で10分おきに約3時間、気温と風向を調べました。
観測後、大住中学校で報告会が行われ、正午から午後1時の間にヒートアイランド現象と思われる状態になっていることがわかりました。
午後1時以降、気温は市街地で高くなっていることは明らかですが、全体に吹く風に支配され風向からヒートアイランド現象を判定するのは難しい状況となりました。
後日、詳細なデータの分析がされると思いますがこのような共同研究ができたことは大きな前進でした。
当日の調査は京都新聞、洛南タイムスの記事にも取り上げられ、SSHの普及活動の一環として、更に外部の研究組織との連携という点でも今後の成果が期待できる取り組みとなりました。
8月8日~9日に横浜で開催されたSSH生徒研究発表会の様子を見に行ってきました。
私は全ての日程に参加することはできず、8日のみの参加でしたが、全国SSH178校の工夫を凝らしたポスター発表を見ることができました。
生徒は他校のブースを回りポスターを見ながら研究の説明を聞いたりと活発な交流を行いました。
本校からは生徒20人と教員4名が参加してくれ、ポスター発表と口頭発表を行いました。
本校のブースを見に来る参加者に対する説明と発表ブースでの口頭発表を熱心にしてくれていました。
本校の発表は「巨椋池の自然放射線量測定による復元」で、グローバルサイエンス部の生徒が巨椋池干拓地周辺で自然放射線量の詳細な調査を地道に行い、上流域の花崗岩の詳細な調査も行ってまとめた研究です。
巨椋池内部と外部の自然放射線量の高低は旧巨椋池の水深分布とほぼ一致し、池の北部は宇治川上流の花崗岩地域、池の南部は木津川上流の花崗岩地域から運ばれてきた堆積物が原因であると突き止めた研究はレベルの高い研究内容でした。
ポスターも発表直前まで何度も練り直し、とても上手くまとめられていました。
残念ながら代表校には選ばれませんでしたが、その次の奨励賞を受賞しました。
みんなで野外調査をしっかりと行い積み上げてきた研究は、発表校の中で私は一番だと思っています。
夏休み中もポスターを前に議論を交わしながら発表に向けて取り組んだ暑い夏。
きっとすばらしい思い出として残ることでしょう。
お疲れ様でした。