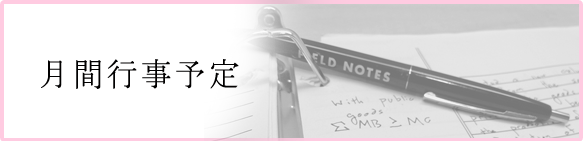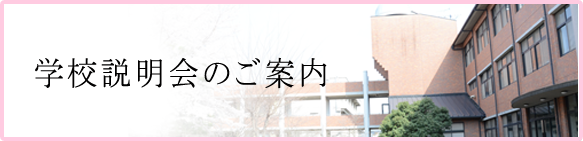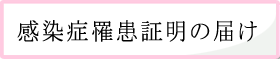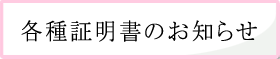7月4日(木)同窓会の方々によって、車石についての説明が書かれたプレートが設置されました。
生徒だけでなく教職員も由来等を知らない人がいると思います。
来校された多くの人に親しんでほしいです。
6月29日と30日の二日間みやこメッセにおいて京都市乙訓地域公立高等学校合同説明会が開催され、私も相談員として参加してきました。
短い時間で十分説明できない点もあり申し訳なく思っております。
また是非本校の説明会にご出席いただいて理解を深めていただければ嬉しいです。
ご来場ありがとうございました。
入試制度改革とともに本校の普通科は、Ⅰ類、Ⅱ類という類が無くなり普通科として新たにスタートします。
期待に応えられるような準備をして来年の入学生を迎えたいと思っています。
7月5日に期末考査が終了し、夏休みが近づきました。
梅雨明けも発表になり、熱中症が心配ですが、夏休みでないとできないこともたくさんあると思います。
今から、しっかり計画を立てて有意義な夏休みを迎えてほしいと思います。
7月7日は七夕でした。七夕の星と言えば、織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)です。
こと座のベガという星は明るさの基準となっている星でもあります。
最初、北極星を2等星として定義しましたが、その後変光星であることがわかり、ベガを0等級と定めました。
地学の授業では教えていました。
夏は、星空のよく見えるところに旅行する機会もあるかもしれません。
そっと星空を見上げて、きらめく星空のロマンに心をときめかせるのもいいかもしれませんね。
梅雨も後半となりました。
例年梅雨末期の集中豪雨が心配な時期です。
祇園祭の頃が、ちょうど例年梅雨明けの頃となります。
早かった今年の梅雨入りですが梅雨明けはどうでしょうか。
残念ながら今の天気図ではその気配はまだ見えません。
来週からは1学期の期末テストです。
しっかりと取り組んでほしいと思います。
6月25日火曜日にお隣の総合教育センターに会議のため出かけていました。
通路横に今年もゼフィランサスが咲いていました。
思わず、足を止めて写真に収めました。
これから秋まで、次々と新しい芽が伸びてきては花を咲かせてくれることでしょう。
ゼフィランサスという花の名前の由来は、ギリシア神話のゼフィロスという西風を司る風神だそうです。
粋な名前を付けるものですね。
昨年の夏、総合教育センターの前で当時2年生の女生徒数人に出会い、花の名前をゼフィランサスと言うといったことを話していると、即座に「ゼフィロス=西風の神ですね」と返事が返ってきました。
ギリシア神話を読んだことがあるのかな。
知識の豊富な生徒たちです。
一つの話題でもこれだけいろんな話が広がるのは素晴らしいことです。
教科書だけでなく豊富な知識を学んでほしいです。
栽培方法を読んでいると、雨の後に花芽が伸びて花が咲くらしく、水がないと根がしっかり伸びて、丈夫になるのだそうです。
水のやり過ぎは良くないと書いてありました。
適度に水を与えるのが良いそうです。
何でも、適度にというのがありますが子育てでも与えすぎは駄目だし、適度にというのは難しいものですね。
今日は6月22日土曜日8時15分です。
土曜補習に向かう生徒がどんどん登校してきます。
校長室の前も歩いています。
みんな元気に挨拶してくれます。
本当に元気で頼もしい生徒たちです。
自然科学科の 1 年生は、先週と今週の2回、巨椋池の生物観察と学校での珪藻化石の学習です。
昨日までの雨で巨椋池の実習が心配でしたが天気が回復してホッとしています。
8時頃、学校での講座をお世話になる京都教育大学の田中教授とティーチングアシスタントの学生さんにご挨拶したところです。
ところで今週18日の火曜日、同窓会の方々によって玄関の築山に配置されている「車石」の説明板を付けるため一部車石の場所を移動させて、わかりやすくする作業が行われました。
同窓会長をはじめ数人の同窓会員さん立ち会いのもと庭師さんが手際よく石を配置されました。
本校の同窓会誌は「車石」と名付けられています。
「車石」とは、江戸時代、大津の港に荷揚げされた米などの物資は、牛車(うしぐるま)によって東海道を京都まで運ばれていました。
しかし当時の街道は土道だったので、雨が降れば牛車の車輪が泥道に埋まり、思うように通行ができませんでした。
そこで、今から約 200 年前、牛車の車輪がぬかるみにはまらないよう、大津-京都間3里(約 12km)の道に、両輪の幅に合わせて2列に石を敷くという、一大土木工事が実施されたのです。
敷かれた石は、頻繁な牛車の通行によって擦り減り、U字型の凹みが残されました。
その石がいつの頃からか「車石」と呼ばれるようになったのです。
この車石は、今も街道沿いの各所に残されており、江戸時代の卓越した街道政策を今に伝える貴重な文化財といえるでしょう。.........大津市歴史博物館資料より抜粋......
同窓会の方から、築山に5個配置されていると聞いていたのですが、何度見ても4個しかわかりませんでした。
車石に詳しい同窓会の先生が5個とおっしゃるのでおかしいなと思っていたところ、ツツジの中に1個隠れているのが見つかりました。
いつの間にかツツジが成長して覆い隠していたようです。
庭師さんに取り出してもらうと中央に車の跡がくっきり付いた車石でした。
この石を含めて、築山に松を植えられた庭師さんの話では、もう1個あるらしく全部で6個あることがわかりました。
車石以外にも、桃山城に使われていた石も築山に配置され、家紋が入った石もあります。
本校の玄関の築山は文化財でできている築山なのです。
庭師さんによって車石を二つ、かつて車が通った時のように並べてもらい、イメージしやすいようになりました。
もうしばらくすると、説明版が築山の車石のそばに設置されて生徒だけでなく、学校を訪れてくださる方々にも見ていただけるようになる予定です。
ちなみに、車石は花崗岩でした。
やはり花崗岩特有の割れ方(節理)をするので、昔からこういうものには使いやすい石なのですね。
ようやく梅雨らしくなりました。
でも毎日降り続くと太陽が恋しくなりますね。
自然の変化はなかなか都合のいいようにはいかないものですね。
気象庁の週間アンサンブル予想図を見る限り、24日~28日頃までは雨マークの日が続きそうです。
梅雨の代表的な花といえば、植物では紫陽花ですね。
この紫陽花って調べてみると「ユキノシタ科」の植物です。
ユキノシタと言えば、生物の授業で「原形質分離」の実験に使ったのを思い出します。
あのユキノシタと紫陽花は同じ科だったのか!それを知ったのはつい数年前のことでした。
私は地学が専門なので、植物の分類と系統については専門ではなく、よくわかりませんが、びっくりするようなこともあれば、なるほどという場合もあり奥が深いです。
原形質分離とは、細胞内と外との浸透圧の違いにより、細胞外の濃度が高いと細胞内の水が外に出て、細胞壁から細胞膜が離れるという現象で、生物で学習します。
この実験に赤い色素を持つユキノシタを使います。
この実験で使わなければ私はきっと覚えることは無かった植物でしょうね。
高校生の頃、ユキノシタの話を祖父にすると、「ユキノシタは食べられるんやで」と教えてくれました。
天ぷらにするのだそうです。昔の人はいろいろ智恵がありましたね。
ちなみに紫陽花は食べられません。
教壇に立って生物を教えたとき、試験に、分離した細胞膜と細胞壁の間はどうなっているのでしょう?という問題を出したところ、「真空」という解答が何名かあり、唖然としたことがありました。
人に教えることは難しいです。
- 1 -
先週末から動向が気になっていた台風3号(Yagi)は関東の南に停滞して熱帯低気圧と
なり、衰弱しそうです。予想図では梅雨前線も消滅しそうになっています。
乾きすぎていて少しは雨を期待して
いたのに残念でした。
先週末から月曜日にかけての気象庁
の台風情報では上陸の恐れもありそ
うでしたが...。休校にならずホッと
しました。
台風情報は気象庁以外にアメリカ海
軍台風情報がホームページで公開さ
れています。暴風警報発令となれば
休校や帰宅指示等の対応が必要にな
るため、いつも両方の予想を見なが
ら対応の準備をしています。
昨年はこの時期に台風が来てし
まい暴風警報が発令されて、緊
急対応することになってしまい
ました。
今回の台風3号 Yagi の進路予想
は、先週末時点での予想でいえ
ば、アメリカ海軍情報が的中し
ました。台風を押し流す上空の風の動きも複雑で、台風の動き
を先まで完全に予想するのはなかなか難しいのですね。自然は
複雑系です。
だからこそ、そこに面白さがあります。
天気予報の のような天気のカテゴリー
だけを見て判断するのではなく、授業を通して少しでも気温が
どう変化し、朝から夜にかけて天気がどう変化するのかなど、
天気図などの情報をおおまかにでも理解できるようになると天気予報を見るのも面白く
なると思います。
気象予報士の資格を持っている人には理系の人だけでなく、大学の経済学部など出身の
人も結構おられます。- 2 -
ところで、桃山高校は、今、面談週間です。中間テストの成績も含めて放課後はあちこ
ちで保護者との面談が行われています。しっかりと信頼できる関係をつくってほしいと
願っています。
1学期がスタートし、2ヶ月あまりが過ぎました。今の
1年生はまだこれからですが、今までの実力テストのデ
ータをみると桃山高校の生徒は良く伸びているのがよく
わかります。今年の4月以降の学習の成果はどうでしょ
うか。楽しみです。
部活動でも、いくつかの部で近畿大会や全国大会への出
場が決まりました。大きな舞台で実力を発揮してほしい
です。
生徒の力は、まさにゴールフリーです。どこまで伸びるか予想がつきません。それだけ
にとっても楽しみです。
4月の新緑の頃、玄関付近のカエデに花が
咲いていました
6月のはじめにふと見上げると、もう種子
がかなり大きくなっていました。
毎日の生活は地道ですが、いつしか大きく
成長するものですね。
5月27日から教育実習生が来ています。
2週間(保健体育は3週間)の実習も大詰めの研究授業を迎えました。
出張もあり、全ての授業を見ることはできませんが、参観すると初々しさに溢れ、私も発問の仕方や板書などいろいろ試行錯誤した頃を懐かしく思い出します。
生徒に感想を書いてもらうと上手く授業ができなくても褒めてくれたり励ましの言葉をくれます。
生徒の優しさに感謝です。
採用試験を突破して、いい先生に育ってほしいです。
6月はどの学校でも教育実習とともに衣替えの時期となります。
今年は梅雨入り宣言が早かったのですが、晴れが続くようだと梅雨が明けてから梅雨入りの修正があるかもしれないですね。
梅雨と冬の南岸低気圧の雨雪判定についてのお天気予想は難しいです。
この時期は梅雨前線の位置が100km南北に移動すると、がらっと変わってしまいます。
西から東に移動する低気圧や高気圧だけでは読み切れず、天気予報が変わることが良くあります。
他の時期よりも直近の予報を見ることが大切な時期です。
新緑からほぼ一月。
学校の木立は夏の日差しを遮り涼しい木陰をつくってくれています。
真夏と違い、まだ爽やかな風が通り抜けています。
日差しは強くても梅雨前線より北側の乾いた空気の中にいるからですが、前線の南に入ると一気に湿度が高くなります。
「夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを
雲のいづこに 月宿(やど)るらむ 清原深養父(36 番)」 百人一首には夏の歌が4首あります。(最も多いのは秋です)
6月21日は夏至。この歌にはこの時期の季節感が良く表現されているなといつも思います。
他に夏の歌は、2番、81番、98番です。
平成26年度から入試制度が変更になるため、5月25日と6月2日、京都国際会館で京都市乙訓地域合同説明会が開催され、多くの中学生や保護者に本校の教育内容と入試の変更点を説明させていただきました。僅か8分間ではなかなか全てを伝えることは難しく、学校での説明会にたくさん来ていただき学校を直接みてくれると嬉しいです。
今日5月23日は中間考査の2日目(3年生は3日目)です。朝、手にノートやプリントな
どを持って試験に備える生徒の姿が目に付きます。1年生にとっては入学して初めての
定期試験です。出来具合はどうでしょうか?
試験後の午後、そっと廊下を歩いてみると学校に残って勉強している生徒が多数います。
最近はファーストフード店で勉強している高校生を見かけることも多く、落ち着いて勉強できる場所は人によって様々なのでしょう。
本校の自習室もお奨めです。
たくさん生徒が残って勉強しています。
今週は良く晴れて、廊下を歩くと自然の乾いた風が流れ、とっても気持ちの良い日が多いです。
桃山丘陵にある本校からの景観は、ほっとした安らぎを与えてくれます。
仕事の合間に校舎を歩き景色を眺めるのが私は大好きです。
北東側には本校のテニスコートと桃山城があり、北側に目を移すと京都市街地全域が目に入ってきます。
北山、西山まで、とてもよくわかります。
京都の市街地全域を南から眺められる場所は他にあまりないと思います。
積乱雲の移動もよくわかります。
一般には今日のような晴れた日を「五月晴れ」と言いますが、本来の意味は、旧暦を使用していた時代の言葉のため、梅雨の晴れ間のことを指す言葉だったようです。
今日の地上天気図を見ると本州付近は日本海に中心をもつ乾いた高気圧に覆われています。
梅雨前線は日本の南にあり、前線が北上してくると梅雨入りとなりますが、週末までは近畿地方は高気圧の通り道となって安定した晴れの日が続きそうです。
前線の南側には湿った夏の高気圧が見えています。
梅雨前線も台湾付近で少し北に盛り上がり、次第にこの前線が北上すると梅雨入りです。
ひょっとすると少し早いですが梅雨入り宣言となるかもしれませんね。
来週火曜日は球技大会です。何とかお天気がもってほしいです。
遠足などに続いてクラスの交流を深める行事です。歓声がこだまし、高校生らしい溌剌とした爽やかなプレーが見られることを期待しています。
今年のゴールデンウイーク後半は、気温の低い日が多く「先生ヒート○ッ○ いつまでいりますか?」と良く聞かれました。
確かに気温の低い日がありましたが、今年だけが特別というわけではありません。
昔から「八十八夜の別れ霜」といい、遅霜がこの頃までは可能性があると言い伝えられてきました。
八十八夜とは、立春から数えて八十八日目のことで今年は5月2日でした。
春は気温の寒暖の差が大きく、そのことを理解して服装の調節をしてほしいと思います。
真夏のような気温になったかと思えば霜が降りるような気温にもなるということを。
八十八夜の前日(5月1日)は、本校の遠足、1年生自然科学科は、スーパーサイエンスキャンプでした。
遠足の行き先によっては、(特に北山方面など)時雨の寒い一日になってしまいました。
担任から寒いという予告はしてくれたと思っていますが、ゆっくりと新緑を楽しむとはいかなかったかもしれません。
私は、自然科学科の1年生のスーパーサイエンスキャンプに同行してきました。
天気の回復が遅れ、残念ながら望遠鏡で星を見ることはできませんでしたが、研究員の方から、宇宙についての講義と夜はクイズを交えたトークで楽しませてもらいました。(1日目)
この天文台は大撫山という山頂にあり、視界は、ほぼ360度という好条件です。
夕食後、宿舎から食堂まで歩いていると野生のタヌキとバッチリ目が合いました。
私は、ある大学のサークル(星空研究会)の指導をしていた関係でここに来たことがあるのですが、ここで学生と星空を眺めたり星の写真を撮ったりしていると、いつも、ゆったりとした時の流れを感じます。
残念ながらこの望遠鏡で星を見ることはできませんでしたが、研究員の方に、望遠鏡を動かして、光を集める仕組みを教えてもらい、反射鏡を直に見せ解説していただきました。
翌朝、霧の出そうな晴れた風の弱い朝は、雲海がみられるとのことで山頂の天文台に5時に行きましたが、この日は少し風があったため右の写真のような南側の場所にのみ小さな雲海ができていました。
朝食後、天文台を出発し、兵庫県佐用町にある「スプリング8」を見学し、様々な最先端の研究現場を実感しました。
下は、アルミ板を当てて、渦電流による不思議な力を実感しているところです。
1日目のオリエンテーションで、スマートフォンを持っている人は気象庁のレーダーをホーム画面において使うことをすすめました。
帰りのバス車内で時雨が降ってきたとき、「生徒がレーダーにないのに雨が降っている」と友だちと話していました。
2km以下の雨雲はレーダーに捉えられない特性があることやレーダーに映っていても雨が降ってこないこともあり、それは、雨が途中で蒸発し地面まで到達しないこともあるなど、「なぜ、そうなるのか」を考えることが大切なのだということを伝えると納得した様子でした。
このキャンプや遠足が、これからのクラスづくりにどのように活きてくるか楽しみです。
新緑が美しい季節となりました。
桃山高校の緑は校舎に良く映え、落ち着いた学びの場を演出してくれます。
見事な花を咲かせた桜は、葉桜となり、ケヤキやハナミズキとの調和が心を和ませてくれています。
どこからかウグイスの囀りが毎日聞こえています。
晴れた昼休みには、生徒が中庭でお弁当を広げながら談笑するいつもの光景があります。
何を話しているのかわかりませんが、とっても楽しそうです。
青春の平凡で和やかな一コマです。
この時期、会議で学校のお隣にある京都府総合教育センターに出かけることが多く、会議を終えて学校に戻ろうとしていると、部活動で正門を出入りする生徒や学校から帰る途中の生徒によく出会います。
本校の生徒は、本当によく挨拶してくれます。
1年生はまだ、私を見たことはあるけれど誰なのか正確にわからず、ためらいがちに挨拶する生徒もいます。
不思議なもので直感で何年生なのかがわかります。
4月25日午後5時頃 学校への坂道をのぼり正門に入ろうとすると「校長先生 お帰りなさい」と笑顔で生徒が声を掛けてくれました。
とっても嬉しいものです。
どうしたらこんなにいい子に育つのだろうと。ここまで育ててこられた保護者の方をその子の姿から想像しています。
いよいよ明日からゴールデンウイークに入ります。
連休の間の5月1日は遠足、1年生自然科学科2クラスは30日~1日の1泊2日でスーパーサイエンスキャンプです。
お天気が気になります。
部活動でも連休中に試合が組まれている部があり、1年生も部活動との両立など学校生活に慣れてくると思います。
中学校の生活から早く抜けだし桃山高校の真の生徒に育って力を発揮してほしいと思います。
4月9日入学式を無事終え、平成25年度の1学期が始まりました。今日11日は健診で、校内を健診各会場に移動する生徒の声があちこちから聞こえてきます。
昨日、廊下を歩いていると、女子生徒が、「校長先生 模試悪かった」と話しかけてくれました。
「模試で大学の合格が決まるのではないから、模試を練習問題だと思って解けるようにしていけばいいよ」と答えました。
「うん そうする」といって笑顔で去っていきました。
模試や問題集などきちんとこなして目標を達成してほしいです。
生徒は本当に素直です。......大人は?
校内のソメイヨシノは6日土曜日の春の嵐ですっかり桜吹雪となりました。
「花さそふ 嵐の庭の 雪ならで
ふりゆくものは 我が身なりけり
百人一首 96 番 入道前太政大臣」
5日金曜日は良い天気で静かに花が舞い
「ひさかたの 光のどけき 春の日に
静心(しづごころ)なく 花の散るらむ
百人一首 33 番 紀 友則
という光景でした。
桜が終わると、ハナミズキが開花します。
校長室の窓を開けると煉瓦づくりの3号館と中庭が見えるのですが、赤色のハナミズキが開花し始めました。
体育館前の白いハナミズキも開花しています。
いよいよ初夏の光景に変わります。左の写真右側はすっかり花が散った枝垂れ桜、ハナミズキの向こうはカエデです。
更にその向こうには竹林があります。
竹の色も茶色くなってきました。
竹の葉の落葉が始まります。
タケノコが出る頃になると竹の葉は散り始めます。
これを「竹の秋」と言いますがもう少し経つと時期は麦の収穫の時期となります。
麦秋と言います。
どちらも私たちが一般に言う秋ではなく「竹の秋」は春の季語、「麦秋」は初夏の季語です。
秋という文字には、落葉とか収穫という意味もあるのだそうです。
真新しい制服に身を包んだ1年生が少し学校に慣れてくると直ぐゴールデンウイーク、体育系部活動の総体、中間考査がやってきます。
早く高校の生活に慣れて思う存分、力を発揮してほしいと思います。
校内にはタンポポがたくさん咲いていますが、中庭に白花タンポポがありました。
西日本には比較的多く、中国地方の山間部にいくと、タンポポの花の色と言えば白、という地域もあるそうです。
そういえば、自然科学科の課題研究で校内のタンポポ分布をテーマにしたグループもありました。
私も授業を教えていた頃、4月のはじめの授業で校内の植物分布を1時間かけて行っていました。
タンポポやシロツメクサなどは、みんなよく知っているのですが、下の植物などは知らない生徒が多いです。
大人も名前だけは知っていても実物はあまり意識して見たことがない。という人が多いのではないかと思います。
3枚の写真は食堂横(1号館前)に群生していました。
どこにでもよく見られる「ホトケノザ(仏の座)」という植物で、葉の形が仏が鎮座している台のように見える気もしますね。
ところで、この写真の種を春の食用になる七草の「ホトケノザ」だと誤解している場合があり、注意が必要です。
(実は私も専門家に教えてもらって知りました。)
食用となる春の七草「ホトケノザ」は、これではなく標準和名をコオニタビラコというキク科の草です。
若い葉を食用とし、湿地を好み、田や周囲のあぜ道などに多く生え、初春の水田ではロゼット葉を広げて地面に這いつくばった姿で見られます。