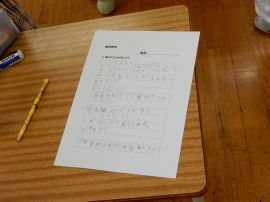9月25日(木)に、京都府農林水産部農政課(食の安全・食育係)によるきょうと食いく先生等派遣事業の一環で、中出で万願寺甘とうを栽培されている北山様に来ていただき、「万願寺甘とうを知っていますか?」と題した授業をお世話になりました。「万願寺甘とうを栽培するときの工夫や育て方について知る。」というのが今回の授業の目的でした。
初めに、北山さんから、「万願寺甘とうはどれでしょう?」と3枚の写真から正解を選ぶクイズが出題されました。意外にも獅子とうがらしと間違える児童が多かったことに驚きました。
万願寺甘とうは、ナス科の野菜で、ナスやトマト、ピーマンと同じ仲間です。今から約100年前、舞鶴市万願寺地区の嵯峨根さんが、「めずらしい物ができるよ。」と、親戚からもらった種を植えたのが栽培の始まりだったということです。
嵯峨根さんが最初に栽培を始める → 近所の人も栽培を始める → 万願寺地区で食べきれず、舞鶴市内へ販売 → 舞鶴市内でも栽培が広がる → 舞鶴市内でも消費し切れず、京都・大阪・神戸へ販売 → 万願寺甘とうが足りなくなったため、舞鶴・福知山・綾部でも栽培が始まった という流れで広まっていきました。万願寺甘とうが好まれた理由は、①大きくて目立つ。 ②辛くない。 ③美味しい。 の三つです。獅子とうがらしが5~9cmなのに対し、万願寺甘とうは10~23cmあり、しかも辛くなくて美味しいのです。人気が出るのも頷けます。



ここで、子どもたちにとうがらしが入った袋が配られました。万願寺甘とうと獅子とうがらしが数本入っていました。子どもたちは、大いに興味をそそられたようで、大きさを比べたり、定規で実際に測ってみたりしていました。実物を手にすると、そのサイズ感、ボリュームの違いが実感できました。とても良い勉強ができました。
続いて、野菜が健康に育つためにやっていることとして、①野菜に合った土づくり ②苗の植え付け ③植え付け後の管理(植え付け~45日) ④定植(45日〜90日) ⑤定植(90日〜) の仕事について教えていただきました。温度の管理や、病気や虫から守ることの重要性を知ることができました。
また、良いものをつくるために実の数を抑える「摘果」が大切だということも分かりました。万願寺甘とうの場合、1本の木に32個以上果実がつくと、木が疲れてしまいます。木が疲れると、売り物となる果実がつかないので、つき過ぎた果実を減らします。すると、残った果実に栄養がたくさん届くので、元気に育つのだそうです。これは、3年生が体験した三和ぶどうの栽培にも通じるところです。
質問コーナーでは、次のように答えていただきました。その一部を紹介します。
Q1「収穫は、何月頃ですか?」 → A1「3月に植えて、4月の終わりから5月の頭に取れ始め、11月頃まで続きます。」
Q2「1年に何回取れますか?」 → A2「6日から7日起きに花が咲き、どんどん実がつきます。ビニールハウスで暖房をすれば、1年中収穫が可能です。」
Q3「育てていて一番大変なことは何ですか?」 → A3「育たないことです。根を張るはずが、張らないなどです。」
Q4「小松菜の栽培では、黒いシートを掛けたりしますが、何か工夫されていますか?」 → A4「苗の横に水用のホースを通しています。日中、日光で水が温まり、湯たんぽのような役割をしてくれます。」
Q5「一番工夫していることは何ですか?」 → A5「たくさんの実をできるだけ長く取りたいので、肥料や水をやることを大切にしてます。また、摘果によって大きな実ができるようにしています。ほかには、ビニールハウスの屋根が開くようになっていて、中が暑くなり過ぎないようにしています。」
Q6「美味しい食べ方は何ですか?」 → A6「天ぷらや、オーブントースターで素焼きにしてしょう油や削り節をかけるのが美味しいです。塩昆布炒めも良いです。」
Q7「何で辛くないのですか?」 → A7「辛い遺伝子を抜くことで辛くなくなります。まず、辛くないとうがらしとピーマンを交配させると、辛いものと辛くないものができます。その辛くないものとピーマンを交配させると、辛くないものが前の世代よりも多くなります。これをどんどん繰り返すことで辛くなくなっていくのです。このことは、中学校の理科で習います。」









万願寺甘とうについて詳しく知ることができ、それを栽培する農家の方の工夫や苦労についても知ることができました。北山様、ありがとうございました。万願寺甘とうを食べる時は、北山様の話を思い出しながら、しっかり味わいたいと思います。