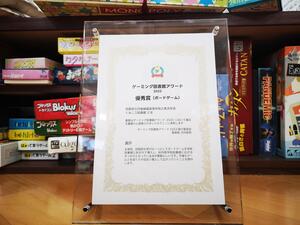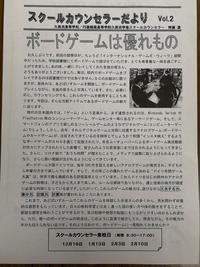学校図書館と図書放送委員会では、前期・後期の図書放送委員とすべての先生方に、その読書遍歴から他の人にも読んでほしいイチオシ本を紹介してもらう「オススメブックリスト」を作成しています。このリストに掲載された本は、一部の絶版本(完売して再販売が予定されていない本)を除き、原則すべて購入し、学校図書館に入ってすぐの本棚で1年間展示し特集しています。

このオススメ本の紹介、図書放送委員だけでなく、 他のみなさんも書いてみませんか?
「このはなし、 学校の友達とも語り合いたい!」というものがある 人はぜひ、その面白さを原稿用紙(どんな紙でも OK)にぶつけてください! そして友達に本を読んでもらい、語れる仲間を作りましょう。
たくさんの投稿、お待ちしています。
なお、オススメ原稿はどんな紙に書いてもらって もOKですが、学校図書館では原稿用紙も配布し ています。
「図書館でゲームをしよう!」というキャンペーンは、2008年にアメリカ図書館協会によって提唱されたのが、広く知られるところでは世界で初とみられています。久美浜学舎では前身の久美浜高校時代の2017年から、ボードゲームによるカウンセリングを実施していたスクール・カウンセラーの助言もいただきつつ様々な教育活動のなかでのボードゲームの有効活用を模索してきたことが評価され、2023年には第1回「ゲーミング図書館アワード」ボードゲーム部門にて優秀賞を受賞しました。
- 様々な人が集まりやすい図書館という「場」ならではのコミュニケーションの促進
- ゲームの背景にある世界観を、本で深掘りしようと促す、読書への入口として
2024年現在、約40種類のボードゲームを学校図書館に備え、授業で、学校行事で、昼休みや放課後のディスカッションで、と、様々に活用されています。

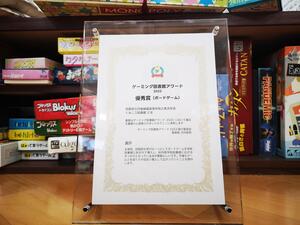
昨年度の人気ゲームは、カタカナを使わずにカタカナ語を説明するコミュニケーション・ゲーム「カタカナーシ」でした。国語科の授業やホームルームでも活用され、その楽しい学びを知った生徒達が放課後に他のクラスの友人を誘って、いっしょにゲームをしにきたこともありました。
今年度この4・5月では、みらい探究Ⅰや保健体育の授業で「クイズいいセン行きまSHOW」シリーズが活用されたほか、「ゼッタイギオンカン」「はあって言うゲーム」のようなコミュニケーションゲームは依然として人気があり、囲碁や将棋など昔ながらのゲームを教え合う姿にも心温まります。
さらに今年は「ドクター・エウレカ」「スティッキー」「アルティメット・カウントゲーム」などの集中力を必要とするゲームも好まれていて、「図書放送委員会でボードゲーム企画をしたい!」「文化祭のクラス企画の待ち時間に、ボードゲームを使ってアイスブレイクしたい!」という相談もちらほら。嬉しいですね。

しかし、みんなの「○○したい!」をサポートするボードゲームも、多くはひとりではできません。もし興味がある人は、この機会に勇気を出して、友だちやクラスメートを誘って学校図書館に足を運んでみてください。
また、ボードゲームを探究活動や校外での発表に活用したり、新しいゲームを考案したり・・・・・・といった活動も、応援しています。そのような際に注意することのひとつに、著作権保護法があります。ボードゲームの著作権については、大学教員らでつくる有志団体「図書館とゲーム部」がまとめたこちらも参照してください。⇒ ボードゲーム企画の著作権
1学期、中間考査後の6月に、図書放送委員会ではお昼休みに学校図書館でボードゲーム大会を開催しました。連日10名前後の生徒と、日替わりで5~6名の先生方も足を運ばれ、学年や学科の枠を越えた交流が育まれました。



主催した委員長の金木喜生さん(3年・久美浜中学出身)は、5月の生徒総会で「やります!」と宣言し、期間中も校内放送で全校生徒や教職員に参加を呼びかけるなど、主体的に活動し、この取組について、次のように話してくれました。
「新入生が入学し、1年の始まりに図書館の本に興味を持ってもらうために、まずは図書館に足を運んでもらおうという目的で開催しました。友達や先生も来て、いつもとは違うコミュニティができ、盛り上がることができました。開催中は毎日図書館に多くの生徒が来て、中には本を借りている生徒もいたので、開催してよかったと思います。ただ1・2年生は参加が少なく、図書放送委員の声掛けをもう少しできたらよかったというのが反省としてあります。今後もこの取組を続け、図書館を盛り上げていきたいと思います!」
 校内放送で全校に参加を呼びかける金木さん
校内放送で全校に参加を呼びかける金木さん
2学期、図書放送委員会では、たくさんの生徒に気軽に学校図書館に足を運び、読書に親しんでもらいたいという想いから、国際的なボードゲームイベント「インターナショナル・ゲームズウィーク(IGW)」にあわせてボードゲーム会を企画しました。連日、お昼休みには図書放送委員をはじめとする生徒や、教職員もともに卓を囲み、ゲームを通して知のコミュニケーションを楽しみました。
11月中旬には、みらいクリエイト科2年生のホームルームでもボードゲーム会が行われました。また、スクールカウンセラーの齊藤先生からもボードゲームの効用について便りをいただくなど、図書放送委員会の企画後も影響はあちらこちらで続いています。
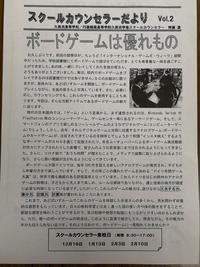
学校図書館には、常時30種類ほどのボードゲームがあります。コミュニケーションを楽しむゲームだけでなく、暗記力や瞬発力、暗算速度や空間把握力、判断力を鍛えるような学習に直結したゲームもあれば、自分の心を見つめて気持ちが安らぐゲームなど、その種類も多彩です。お昼休みや放課後を活用して、ぜひ試してみてください。


この記事の関連記事はこちら。⇒ 「図書館でゲームをしよう! IGW開催」
「図書館でゲームをしよう!」とは、2008年に米国図書館協会(ALA)が呼びかけて始まった国際イベント「インターナショナル・ゲームズ・ウィーク(IGW)」のキャッチコピーです。日本にも古くから囲碁や将棋といった卓上遊戯(ボードゲーム)がありますが、遊びながら論理的思考力を身につけたり、コミュニケーション能力を高めたりする効果があるとボードゲームは世界中に数多くあり、その奥深い世界観は読書の世界と通じるものも多々あります。インターナショナル・ゲームズ・ウィークには、世界各地の数千の図書館が参加し、様々なゲームイベントが開催されています。
11月4日からスタートしている学校図書館公開では、4日から12日の前期展期間に、インターナショナル・ゲームズ・ウィークに参加。30種類以上のボードゲームを用意して、学校運営に関わる府の職員や近隣校で探究学習に協力いただいている地域のNPO、地元の小学生など、この機会に図書館見学に来られた皆様の笑顔はじける学校図書館になりました。


また、10月に発足した後期図書放送委員会では、「クラスのみんなに図書館や読書に親しんでもらう」ことを活動目標に意見を募ったところ、「ボードゲーム会をしよう!」という提案があり、さっそく11月1日の生徒総会で呼びかけを行いました。上記と時期を合わせて今週をボードゲーム週間とし、お昼休みの学校図書館利用を呼びかけています。
11日(木)には、ボードゲームに詳しいスクールカウンセラーの齊藤先生も参戦されます。ひとりではなかなか遊べないゲームも、この機会にみんなで体験してみましょう!


図書放送委員会では、夏休みに先立ち、先生方にイチオシの本を紹介してもらった小冊子「オススメブックリスト」を発行しました。この取組は、およそ四半世紀前から毎年続けられている図書放送委員会のいちばん大きな事業で、今年も40冊以上の良書が紹介されました。先生方に原稿をお願いするだけでなく、図書放送委員も、友だちと語り合いたい大好きな1冊をそれぞれ紹介しています。
在校生のみなさんには、各クラスの図書放送委員が製本した紹介文の小冊子を配布していますが、そのうちの一部は、この図書館Blogでも夏休み期間中に掲載していきます。1冊の本から得た先生方の感動や学びを、みなさんもぜひ読んで体験してみてください。紹介された本は、今後1年間、学校図書館の特設コーナーに展示しています。

図書放送委員会は、各クラスから2名選出された生徒で構成される生徒会活動です。毎年夏休み前に発行する「先生&図書放送委員のオススメブックリスト」の制作や、文化祭での図書館企画、体育祭でのBGM放送などを行っています。
- 2021(令和3)年度以降の図書放送委員会の取組については、こちら
- 2020(令和2)年度 文化祭企画の様子は、こちら(旧久美浜高等学校ホームページ)